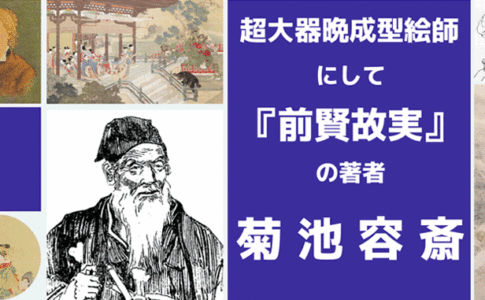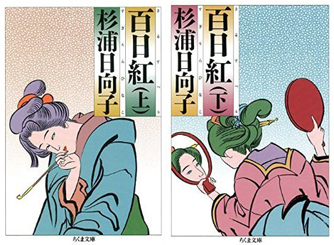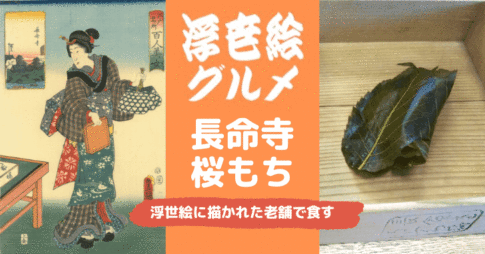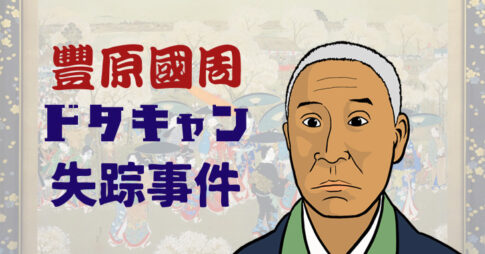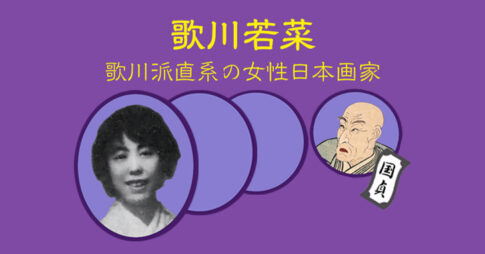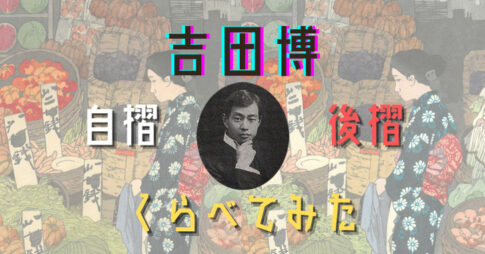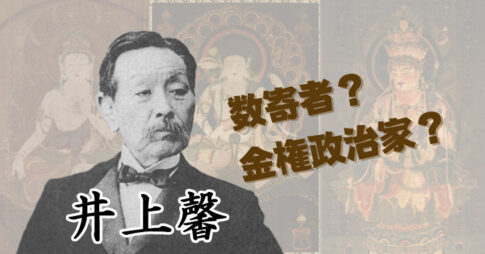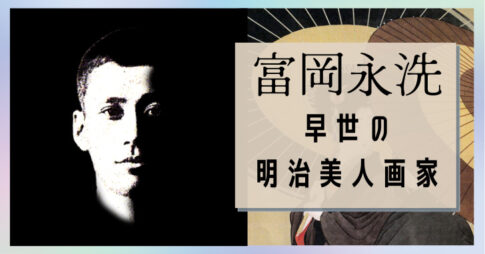昭和戦前期に出版されていた日本画専門雑誌。昭和16年9月以降、雑誌名を塔影から国画に変更した。ここに掲載した目次は国立国会図書館所蔵のもの。
第1巻(昭和16年(1941)9月~12月)
第1巻1号(昭和16年(1941)9月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(暁靄 絹尺五横) | 横山大観 |
| 題字 | 弘法大師 |
| 扉絵(海辺 絹二尺横) | 磯部草丘 |
| 口絵原色版 | – |
| 古画特集写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 日本民族の二美質 | 岸田国士 |
| 文化政策について | 尾崎士郞 |
| 国家と芸術 | 大串兎代夫 |
| 日本美術の性格 | 秋山謙蔵 |
| 民族の興隆と美術 | 保田与重郞 |
| 日本芸術と絵画 | 岡崎義恵 |
| 顧愷之女史箴図解説 | 原田尾山 |
| 女史箴図巻の思ひ出 | 漆原木虫 |
| 北に旅する(絵と文) | 奥村土牛 |
| 東北の旅より(絵と句) | 酒井三良 |
| 満州(絵と文) | 坂口一草 |
| 紅台(絵と文) | 山崎豊 |
| 大空の落書 | 飯塚友一郞 |
| 夏日断片 | 長谷川時雨 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 高木保之助氏逝く | 添田逹嶺 |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第1巻2号(昭和16年(1941)10月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(秋の庖仏印展) | 竹内栖鳳 |
| 題字 | 弘法大師 |
| 扉絵(仏印展) | 前田荻邨 |
| 口絵原色版 | – |
| 古画写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 戒壇院扉絵に就て | 田中一松 |
| 容斎伝中の一発見 | 添田逹嶺 |
| 戦争と芸術 | 関口俊吾 |
| 現代作家に寄す | 外狩素心庵 |
| 創作心理の開放を望む | 塩田力蔵 |
| 院展・青龍展に現れた時局色を焦点として | 神崎憲一 |
| 第廿八回院展を観て | 大山広光 |
| 青龍展を観る | 木村重夫 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 逝ける八木岡春山氏 | 添田逹嶺 |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第1巻3号(昭和16年(1941)11月)
| タイトル | 著者 |
| 川合玉堂原色作品集 | – |
| 風景写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 題字 | 弘法大師 |
| 扉絵 | 山口玲熙 |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
| 玉堂先生と三水会 | 清水澄 |
| 川合先生のこと | 永井柳太郞 |
| 画筆三昧の人 | 赤間信義 |
| 玉堂川合先生頌(漢詩) | 外狩素心庵 |
| 玉堂画伯 | 本間久雄 |
| 玉堂氏筆彩雨図について | 矢代幸雄 |
| 青葉若葉(俳句) | 川合玉堂 |
| 玉堂先生の偉大さの特質に就て | 神崎憲一 |
| 玉堂先生の畔に住みて | 中村吉右衛門 |
| 佳き日に詠める(短歌) | 川合玉堂 |
| 玉堂画伯と歌 | 佐佐木信綱 |
| 玉堂画伯の猫と虎 | 堀越島子 |
| 川合先生の俳句 | 星野麦人 |
| 磨ける珠 | 児玉希望 |
| 長流荘先醒金石志 | 加茂川酔歩 |
| 日本の風景と山水画 | 黒田鵬心 |
| 展覧会評 | – |
| 新刊紹介 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
第1巻4号(昭和16年(1941)12月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 題字 | 弘法大師 |
| 扉絵 | 森守明 |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
| 徽宗皇帝筆桃鳩図解説 | 田中一松 |
| 美術家と生活 | 高村光太郞 |
| 新日本美の創造 | 秋山謙蔵 |
| 思想的に見たる文展 | 浅野晃 |
| 思ひつく儘に | 村岡花子 |
| 第四回文展第一部所感 | 神崎憲一 |
| 第四回文展日本画観 | 大山広光 |
| 文展新人日本画評 | 木村重夫 |
| 文展鑑査感 | 野田九浦 |
| 文展無鑑査出品遠慮?無遠慮? | 池田遙邨 |
| 美術機構への提案 | 浅利篤 |
| 安南風物の語るもの | 佐波甫 |
| 玉堂先生の俳句の一特兆 | 神崎憲一 |
| 雪岱忌 | 内田誠 |
| 雪岱遺作展 | 大山広光 |
| 展覧会評 | – |
| 混沌たる文展評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
第2巻(昭和17年(1942)1月~12月)
第2巻1号(昭和17年(1942)1月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 子日遊図屛風 泉涌寺蔵 | 宇喜多一蕙 |
| 和気清麿図部分 帝室博物館蔵 | 菊池容斎 |
| 賀茂祭図部分 内藤子爵家蔵 | 田中訥言 |
| 勤王画家特集写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 世界史的転換期に於ける日本の理想 | 藤沢親雄 |
| 維新を顧みて国画の消息を語る | 市島春城 |
| 戦時下独逸の美術界 | 小塚新一郞 |
| 宇喜多一蕙斎遺事 | 相見香雨 |
| 田中訥言 | 山田秋衛 |
| 勤王画家森寬斎 | 吉副禎三 |
| 隠れたる勤王画人児島基隆 | 添田達嶺 |
| 維新志士と南画道 | 小室翠雲 |
| 板倉槐堂と武市瑞山 | 杉渓六橋 |
| 維新志士の遺墨 | 藤田徳太郞 |
| 勤王画家遺墨展 | 木村重夫 |
| 求道と唯美 | 亀井勝一郞 |
| 勤王敬神の画人鉄斎先生 | 西沢笛畝 |
| 展覧会評 | – |
第2巻2号(昭和17年(1942)2月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 御物蒙古襲来絵詞(模本二面)東京帝室博物館蔵 | – |
| 武士 | 小堀鞆音 |
| 前田犬千代初陣図(下絵二色版) | 小堀鞆音 |
| 鵯越図(下絵二色版) | 小堀鞆音 |
| 残雪(紙尺八横) | 山口蓬春 |
| 写真版 | – |
| 御物蒙古襲来絵詞(原本二十三面) | – |
| 北条時宗像(二面) | – |
| 武具(九面) | – |
| 表紙絵・扉絵 | 小堀鞆音 |
| 題字 | 弘法大師 |
| 歴史の創造と芸術 | 秋山謙蔵 |
| 元寇前後 | 遠藤元男 |
| 蒙古襲来と時代思潮 | 圭室諦成 |
| 北条時宗像解説 | 谷信一 |
| 蒙古襲来絵詞に就いて | 田中一松 |
| 蒙古襲来絵詞の妙味 | 荻野三七彦 |
| 蒙古襲来と鎧兜 | 後藤守一 |
| 宇喜多一蕙斎遺事(下) | 相見香雨 |
| 仏印より帰りて | 佐波甫 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
第2巻3号(昭和17年(1942)3月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 老子・西王母図屛風(部分) | 狩野山雪 |
| 雪の朝(絹二五横) | 伊東深水 |
| 春雨(絹二尺竪) | 児玉希望 |
| 蕃女(紙二六竪) | 山川秀峰 |
| 竹林(紙小品) | 飯塚琅玕斎 |
| 手古舞(素描二色版) | 鏑木清方 |
| 習作(素描二色版) | 鏑木清方 |
| 写真版 | – |
| 表紙絵・扉絵 | 鏑木清方 |
| 題字 | 弘法大師 |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
| 亜細亜新文化の創造 | 川面隆三 |
| 仏印に於ての日本画の批評 | 藤田嗣治 |
| 大東亜共栄圏と日本画 | 佐波甫 |
| 日本画と美的精神 | 久松潜一 |
| 中世に於ける新しき風景の成立 | 風巻景次郞 |
| 狩野山雪に就て | 土居次義 |
| 黒甜余録 | 秦一郞 |
| 竹(「四君子」考の一) | 木村重夫 |
| 竹芸術と飯塚琅玕斎 | 大山広光 |
| 展覧会批評 | – |
| 逝ける山村耕花氏 | 添田達嶺 |
| 画壇鳥瞰 | – |
第2巻4号(昭和17年(1942)4月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 写真版 | – |
| 浮世絵と時代風俗 | 江馬務 |
| 日本婦女図考 | 木村重夫 |
| 上村松園女史の画業 | 松本亦太郞 |
| 松園さんの研究 | 鏑木清方 |
| 時局と松園の芸術 | 吉副禎三 |
| 松園研究断章 | 神崎憲一 |
| 能面と松園さんの絵 | 金剛巌 |
| 春日の局を想出される | 中村梅玉 |
| 中支慰問の旅 | 上村松園 |
| 中支に於ける松園先生 | 秋田正男 |
| 旅に観た松園先生 | 三谷十糸子 |
| 母子今昔譚 | 上村松園・上村松篁 |
| 清元松の園生 | 高沢初風 |
| 女人凱歌 | 加茂川酔歩 |
| 展覧会批評 | – |
第2巻5号(昭和17年(1942)5月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 曙の洋(院展同人献納展) | 横山大観 |
| 水仙(院展同人献納展) | 安田靫彦 |
| 丹頂(院展同人献納展) | 小林古径 |
| 双鴨(院展同人献納展) | 奥村土牛 |
| 写真版 | – |
| 現代日本画と国民性 | 岡崎義恵 |
| 現代日本画論 | 金原省吾 |
| 現代日本画人観序説 | 神崎憲一 |
| 現代画家随論 | 木村重夫 |
| 日本画人献画献金愛国篇 | 豊田豊 |
| 画人の彩管報国 | 添田達嶺 |
| 日本画家報国会軍用機献納展 | 大山広光 |
| 院展同人軍用機献納展 | 斎田素州 |
| 展覧会批評 | – |
| 島の一蝶(長唄) | 高沢初風 |
| 絵絹購入票に就て | 大山広光 |
| 岡野栄画伯逝く | 田沢田軒 |
| 画壇鳥瞰 | – |
第2巻6号(昭和17年(1942)6月)
| タイトル | 著者 |
| 大東亜の文化行動 | 中村彌三次 |
| 大東亜新文化創建の秘鑰 | 野村重臣 |
| 大和絵の新領域 | 金井紫雲 |
| 画家と文章 | 木村重夫 |
| 桜に蒲公英(俳句) | 高浜虚子・児玉希望 |
| 雪(絵と唄) | 鏑木清方 |
| 麦の穂(絵と句) | 金島桂華 |
| 屏風の絵と和歌 | 窪田空穂・松本一洋 |
| 竹林にをりて | 吉田絃二郞・田中咄哉州 |
| 米艦の日本下士官 | 長谷川伸・三輪晁勢 |
| 花鳥風月 | 上司小剣・酒井三良 |
| 京の四季 | 神崎憲一・松本一洋・池田遙邨 |
| 「戦ふ銃後」を描く | 三輪鄰 |
| 工場地帯の栄養食配給所(絵と文) | 立石春美 |
| 農村讃(絵と文) | 東山魁夷 |
| 花嫁衣裳の共同使用(絵と文) | 村松乙彦 |
| 山国の翼賛運動(絵と文) | 岩淵芳華 |
| 黒甜余録 | 秦一郞 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 原色版 | – |
| 蒙古牛素描(部分、表紙) | 橋本関雪 |
| 厩写生 | 橋本関雪 |
| 駱駝素描 | 橋本関雪 |
| 夏草(紙尺七横) | 小野竹喬 |
| 夏菊(絹二尺横) | 徳岡神泉 |
| 写真版 | – |
| 扉絵 | 橋本関雪 |
| 題字 | 弘法大師 |
| カット | 小室翠雲・田中咄哉州 |
第2巻7号(昭和17年(1942)7月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 二色版 | – |
| 網目凸版 | – |
| 写真版 | – |
| 表紙絵(寒山寺御碑亭、原寸) | 小室翠雲 |
| 扉絵(蘇州西園にて、原寸) | 山口華楊 |
| 題字 | 弘法大師 |
| カット | 福田平八郞・田中咄哉州 |
| 美術の島国性と海国性 | 川路柳虹 |
| 絵から見た日本的技術の一つの特徴に就いて | 三枝博音 |
| 日本の南画と支那の南画 | 原田尾山 |
| 大東亜南画論 | 吉副禎三 |
| 大東亜共栄圏の建設と絵画芸術の使命 | 小室翠雲 |
| 南画私観 | 鈴木進 |
| 新南宗画への理念と実際 | 大山広光 |
| 親日画人王一亭翁を憶ふ | 土屋計左右 |
| 大陸無言行 | 宮崎井南 |
| 展覧会批評 | – |
| 金子堅太郞伯薨去 | 添田達嶺 |
| 画壇鳥瞰 | – |
第2巻8号(昭和17年(1942)8月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 網目凸版 | – |
| 写真版 | – |
| 表紙絵(大同石仏写生) | 前田青邨 |
| 扉絵(唐津虹の松原写生) | 田中咄哉州 |
| 題字 | 弘法大師 |
| カット | 小室翠雲・福田平八郞・田中咄哉州 |
| 芸術至上主義の否定 | 秋山謙蔵 |
| 目的芸術としての絵画 | 森口多里 |
| 古今遠近 | 西堀一三 |
| 日本画の戦争表現に就ての考察 | 大山広光 |
| 「大東亜戦争」展覧会に就て | 堂本画塾 |
| 共同制作の成るまで | 堂本画塾員 |
| 「大東亜戦争」展を観て | 神崎憲一 |
| 爪哇の芸術 | 川端龍子 |
| 「招蝶花」採集譚 | 加茂川酔歩 |
| 天心先生三十周年 | 黒田鵬心 |
| 金子伯と岡倉天心 | 塩田力蔵 |
| 展覧会批評 | – |
| 松本一洋氏の能楽「半蔀」 | 神崎憲一 |
| 画壇鳥瞰 | – |
第2巻9号(昭和17年(1942)9月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 二色版 | – |
| 網目凸版 | – |
| 写真版 | – |
| 表紙絵(芭蕉翁下図、部分原寸) | 川合玉堂 |
| 題字 | 弘法大師 |
| カット | 小室翠雲・福田平八郞・山口華楊・田中咄哉洲・山川秀峰 |
| 制作余談特集 | – |
| 隻語拾集録 | 神崎憲一 |
| 芸談襍記 | 木村重夫 |
| 美術家と眼 | 三輪鄰 |
| 大東南宗院の大陸進出 | 添田達嶺 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹内栖鳳画伯逝去 | 神崎憲一 |
| 画壇鳥瞰 | – |
第2巻10号(昭和17年(1942)10月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 鱥写生(部分原寸) | 堅山南風 |
| 山帰来鶯図 | 俵屋宗達 |
| 花籠図 | 尾形乾山 |
| 国華 | 田中咄哉州 |
| 湖畔晴日(早苗会展出品) | 松本一洋 |
| 重成出陣(早苗会展出品) | 勝田哲 |
| 流れ(晨鳥社展出品) | 山口華楊 |
| 写真版 | – |
| 題字 | 弘法大師 |
| 扉絵(つはぶき写生) | 堅山南風 |
| カット | 小室翠雲・福田平八郞・田中咄哉州 |
| 光悦の人と芸術 | 渡辺素舟 |
| 宗達に就て | 武者小路実篤 |
| 宗達雑話 | 谷信一 |
| 美術の保護と統制 | 中村彌三次 |
| 俳諧の軽みと絵画の軽 | 潁原退蔵 |
| 院展と青龍展の傾向に就て | 今泉篤男 |
| 在野二展の反発面と親和面 | 神崎憲一 |
| 院展の日本画所感 | 木村重夫 |
| 青龍社第十四回展所感 | 大山広光 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
第2巻11号(昭和17年(1942)11月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 急緩萬里(満州国献納画) | 川合玉堂 |
| 髪(満州国献納画) | 橋本関雪 |
| 祝ひ日(満州国献納画) | 前田青邨 |
| 愛児之図(満州国献納画) | 上村松園 |
| 熊沢蕃山 | 島田墨仙 |
| 街頭の印度人(原寸) | 山口蓬春 |
| 香港スタンレー砲台 | 山口蓬春 |
| 写真版 | – |
| 表紙絵(広東娘 原寸) | 山口蓬春 |
| 扉絵(小御所会議小下図) | 島田墨仙 |
| 題字 | 弘法大師 |
| カット | 小室翠雲・福田平八郞・田中咄哉州 |
| 生活と美術 | 井島勉 |
| 家庭生活と美術愛 | 伊福部敬子 |
| 縞と独楽文様の蒔絵に就て | 吉野富雄 |
| ゑそらごと | 麻生磯次 |
| 画室断想 | 島田墨仙 |
| 随想・その日その日 | 吉田尭文 |
| 夜明け前の文展 | 神崎憲一 |
| 文展に望むもの | 鈴木進 |
| 鑑査所感 | 小室翠雲 |
| 文展日本画批評便り | 大山広光・木村重夫 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
第2巻12号(昭和17年(1942)12月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| コロタイプ版 | – |
| 写真版 | – |
| 表紙絵(東本願寺天井絵下図部分) | 竹内栖鳳 |
| 扉絵(東本願寺天井絵下図部分) | 竹内栖鳳 |
| 題字 | 弘法大師 |
| カット | 小室翠雲・福田平八郞・田中咄哉州 |
| 栖鳳先生を偲ぶ | 牧野伸顕 |
| 遺邸秋霜の記 | 竹内逸 |
| 栖鳳追悼号掲出作解説 | 神崎憲一 |
| 思ひ出は尽きず | 西山翠嶂 |
| 昔のことなど | 上村松園 |
| 過去を追はぬ | 石崎光瑤 |
| 至り得ぬ境地 | 小野竹喬 |
| 十二三年前のこと | 金島桂華 |
| 開かれた眼 | 徳岡神泉 |
| 振向かれた御顔 | 池田遙邨 |
| 「栖鳳人形」 | 加茂川酔歩 |
| 竹内栖鳳葬儀 | – |
| 栖鳳先生と潮来 | 藤岡鉱二郞 |
| 足趾を辿る | 神崎憲一 |
| 竹内栖鳳制作略年譜 | – |
| 川村曼舟画伯逝く | 神崎憲一 |
| 曼舟先生の御逝去を悼みて | 中井宗太郞 |
| 御人徳を偲びて | 松本一洋 |
| 川村曼舟制作略年譜 | – |
| 展覧会批評 | – |
| 逝ける木村武山画伯 | 添田達嶺 |
| 画壇鳥瞰 | – |
第3巻(昭和18年(1943)1月~11月)
第3巻1号(昭和18年(1943)1月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 写真版 | – |
| 東洋の絵画の精神と戦争画 | 橋本関雪 |
| 日本画に於ける東洋的なもの | 鼓常良 |
| 画室より画室へ | 橋本関雪 |
| 南方に旅して | 三輪晁勢 |
| 支那の王城建築 | 木村素衛 |
| 満州国に使して | 松林桂月 |
| 「和」を懐ふこゝろ | 呉茂一 |
| 大東亜戦争と芸術 | 佐波甫 |
| 思想戦線における絵画 | 木村重夫 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
第3巻2号(昭和18年(1943)2月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 早春写生 | 川合玉堂 |
| 八重紅梅写生 | 福田平八郞 |
| 椿写生 | 福田平八郞 |
| 観音(院展同人軍用機献納展) | 小林古径 |
| 寬永期歌舞伎屏風 | – |
| 写真版 | – |
| 寬永期歌舞伎屏風二隻 | – |
| 展覧会出品 | – |
| 表紙絵(韮山江川邸前の松写生) | 田中咄哉州 |
| 葱坊主写生 | 堅山南風 |
| 題字 | 弘法大師 |
| カット | 小室翠雲・福田平八郞・田中咄哉州・山川秀峰 |
| 絵画と文学 | 池田亀鑑 |
| 写生と配合 | 木村重夫 |
| 雪の絵 | 西堀一三 |
| 新作画鑑賞界概観 | 神崎憲一 |
| 新発見の歌舞伎屏風 | 河竹繁俊 |
| 歌舞伎屏風について | 吉田暎二 |
| 杭州迎春行 | 宮崎井南 |
| 展覧会批評 | – |
| 尚絅会第二回展 | 佐波甫 |
| 朱兆会第一回展 | 神崎憲一 |
| 日東美術院展 | 木村重夫 |
| 画壇鳥瞰 | – |
第3巻3号(昭和18年(1943)3月)
| タイトル | 著者 |
| 題字 | 弘法大師 |
| カット | 小室翠雲・福田平八郞・田中咄哉州・山川秀峰 |
| 猫画双絶 | 秋山光夫 |
| 栖鳳の芸術 | 田中一松 |
| 国画の現代的課題 | 本荘可宗 |
| 心印の提唱 | 小室翠雲 |
| 勤王志士と絵画 | 佐波甫 |
| 美術家の報国運動 | 高橋健二 |
| 現代日本画家分布鳥瞰記 | 大山広光 |
| 全日本画家報国献納画展 | 木村重夫 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
第3巻4号(昭和18年(1943)4月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 正成鳳輦を迎へ奉る(日本歴史画展出品) | 菊池契月 |
| 神皇正統記(日本歴史画展出品) | 安田靫彦 |
| 相模太郞(日本歴史画展出品) | 中村岳陵 |
| 表紙絵(ぜんまい写生) | 中村岳陵 |
| 題字 | 弘法大師 |
| もつこく写生 | 中村岳陵 |
| 加茂川堤の松に桜写生 | 小野竹喬 |
| 写真版 | – |
| 「六玉川」六図 | 一立斎広重 |
| 展覧会出品 | – |
| 仙酔島写生 | 小野竹喬 |
| カット | 小室翠雲・福田平八郞・田中咄哉州 |
| 歴史画の現代的意義 | 遠藤元男 |
| 歴史画を描く | 中村岳陵 |
| 日本歴史画展を観る | 神崎憲一 |
| 一立斎広重筆「六玉川」 | 高橋誠一郞 |
| 柿崎夕陽(絵と句) | 田中咄哉州 |
| 神社画と敬神思想 | 佐波甫 |
| 南を描ける人々 | 金井紫雲 |
| 国画の道 | 木村重夫 |
| 明治美術の回顧 | 添田達嶺 |
| 展覧会批評 | – |
| 池上秀畝氏奉戴日作品展 | 神崎憲一 |
| 画壇鳥瞰 | – |
第3巻5号(昭和18年(1943)5月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 網目凸版 | – |
| 写真版 | – |
| 名古屋城の障壁画に就て | 田中一松 |
| 城の構成と美術 | 鳥羽正雄 |
| 芸術報国の道 | 安藤紀三郞 |
| 墨仙画伯の愛国精神 | 加茂川酔歩 |
| 日本芸術と悠久性 | 西堀一三 |
| 絵画と民俗 | 中山太郞 |
| 狭庭の春 | 富安風生 |
| 京都護国神社に奉納画を観る | 豊田豊 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
第3巻6号(昭和18年(1943)6月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 網目凸版 | – |
| 写真版 | – |
| 日本的美意識と絵画 | 山口諭助 |
| 表現の可能と限界 | 竹内芳衛 |
| 美術雑感 | 武者小路実篤 |
| 落葉のいのち | 浅野晃 |
| 北の鳥南の鳥 | 内田清之助 |
| 南の花北の花 | 松崎直枝 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
第3巻7号(昭和18年(1943)7月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 写真版 | – |
| 表紙絵(仏像素描 原寸) | 島田墨仙 |
| 題字 | 弘法大師 |
| 扉絵(石竹写生) | 白倉嘉入 |
| カット | 福田平八郞 |
| 基督と四人の聖徒解説 | 木村重夫 |
| 栖鳳作風覚書 | 春山武松 |
| 栖鳳回顧展所感 | 木村重夫 |
| 冷泉為恭の画論 | 森銑三 |
| 魚と日本画 | 田中茂穂 |
| 昆蟲と国画 | 大町文衛 |
| 現代日本画家生活素描(西山翠嶂、安田靫彦、川端龍子、石崎光瑤、兒玉希望、金島桂華、山口華楊、中村貞以) | 神崎憲一・木村重夫 |
| 工場巡回美術展の成果 | 志賀健二 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
第3巻8号(昭和18年(1943)8月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 写真版 | – |
| 表紙絵(鶴写生 原寸) | 石崎光瑤 |
| 題字 | 弘法大師 |
| 扉絵(赤ゲラの雛写生) | 石崎光瑤 |
| カット | 小室翠雲・福田平八郞 |
| 鶏頭花と芥子花屏風 | 田中一松 |
| 日本画の美しさについて | 平出英夫 |
| 真細の美 | 木村重夫 |
| 二つの話 | 山口青邨 |
| 洋画家の日本画 | 添田逹嶺 |
| 油絵画家の墨絵に対する疑問 | 江川和彦 |
| 島田墨仙自叙伝 | – |
| 逝ける島田墨仙翁 | 添田達嶺 |
| 現代日本画家生活素描(荒木十畝、松林桂月、上村松園、德岡神泉、小野竹喬、福田平八郞、松本一洋、白倉嘉入) | 神崎憲一・木村重夫 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
第3巻9号(昭和18年(1943)9月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 写真版 | – |
| 題字 | 弘法大師 |
| 扉絵(田師表小下図) | 島田墨仙 |
| カット | 福田平八郞・田中咄哉州 |
| 島田さんを憶ふ | 川合玉堂 |
| 島田墨仙翁の芸術 | 飛田周山 |
| 私の観た島田墨仙先生 | 添田達嶺 |
| 軽井沢に於ける島田墨仙先生 | 平井恒子 |
| 画題に現れた墨仙先生の精神 | 田中良助 |
| 島田墨仙制作略年譜 | 添田逹嶺編 |
| 羈旅の心 | 吉田絃二郞 |
| 空・川蝉・庭 | 恩地孝四郞 |
| 現代日本画家生活素描(大智勝観、宇田荻邨、池田遙邨、田中咄哉州) | – |
| 墨仙自叙伝 | – |
| 展覧会批評 | – |
| 中国画壇だより | 佐波甫 |
| 画壇鳥瞰 | – |
第3巻10号(昭和18年(1943)10月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 綱目凸版 | – |
| 写真版 | – |
| 題字 | 弘法大師 |
| 扉絵(農家写生) | 奥村土牛 |
| カット | 小室翠雲・田中咄哉州 |
| 美術の民族的基底と共栄圏的基底 | 井島勉 |
| 本居宣長の絵画論 | 久松潜一 |
| 院展日本画所感 | 田中一松 |
| 青龍社第十五回展 | 木村重夫 |
| 新生支那と現代日本画展 | 佐波甫 |
| 近詠 | 諸家 |
| 仏印現代美術展と安南の美術家達 | 江川和彦 |
| セレベス島 | 湊邦三 |
| 現代日本画家生活素描(小室翠雲、伊東深水、奥村土牛) | – |
| 墨仙自叙伝 | – |
| 今後の日本画の方向に就て | 江川和彦 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 橋本静水画伯逝く | 添田達嶺 |
第3巻11号(昭和18年(1943)11月)
| タイトル | 著者 |
| 原色版 | – |
| 網凸版 | – |
| 写真版 | – |
| 表紙絵(桔梗写生) | 堅山南風 |
| 題字 | 弘法大師 |
| カット | 小室翠雲・田中咄哉州・安田半圃 |
| 現代日本画に於ける明暗諧調 | 川路柳虹 |
| 若月の眉 | 風巻景次郞 |
| 決戦日本画論 | 吉副禎三 |
| 大震火災に焼失せる雅邦翁の遺作 | 橋本秀邦 |
| ジョクジヤとバリ島(絵と文) | 伊東深水 |
| 絵と獣 | 黒田長礼 |
| 平賀源内の洋画 | 暉峻康隆 |
| 塩渓月余(俳句) | 斎田素州 |
| 現代日本画家生活素描(森白甫、太田聴雨) | – |
| 墨仙自叙伝 | – |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |