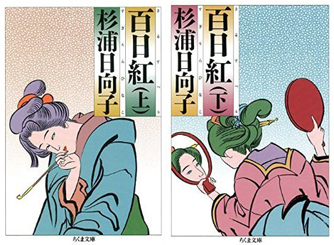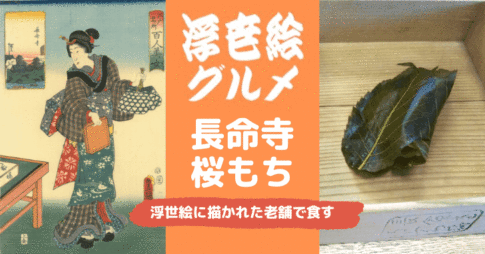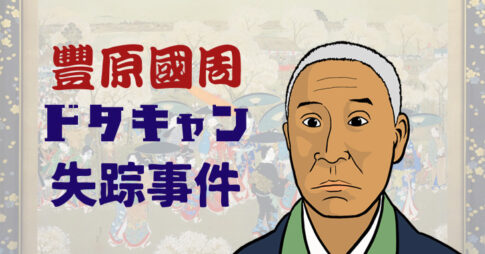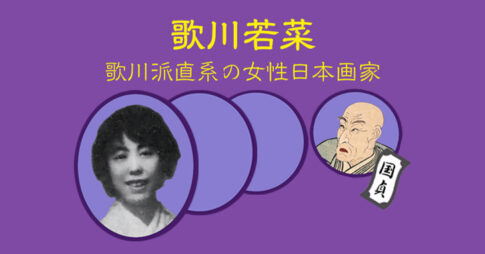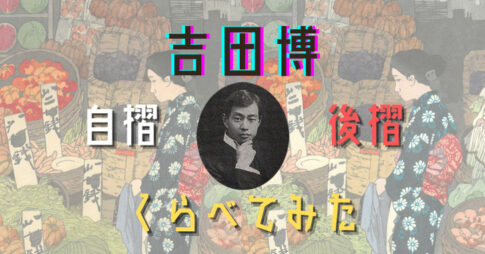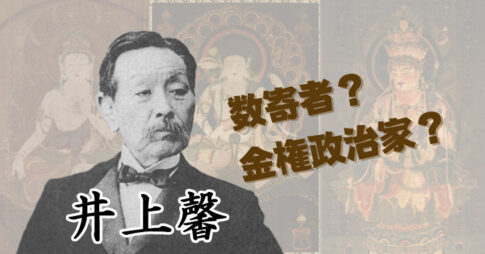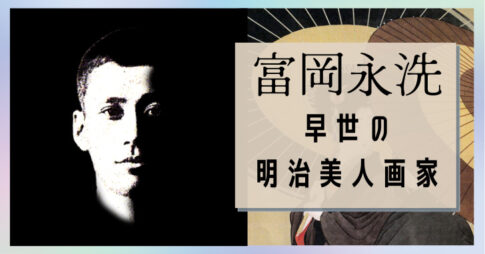昭和戦前期に出版されていた日本画専門雑誌。昭和16年9月以降、雑誌名を塔影から国画に変更した。今のところ公的機関での全巻所蔵はない。ここに掲載した目次は国立国会図書館所蔵のもの。
第9巻(昭和8年(1933)1月~12月)
第9巻1号(昭和8年(1933)1月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵 | 土田麦僊 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵 | 永田春水 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 古画写真版 | – |
| 鳥類生態写真版 | – |
| 芳崖・雅邦のスケッチ | 島田墨仙 |
| 新春画幅の展覧会概観 | 豊田豊・斎田素州 |
| 茶用画幅に就いて | 高橋箒庵 |
| 山水画の発達史上に於ける詩軸の地位 | 田中一松 |
| 菊池容斎に就いて | 竹内梅松 |
| 俳句 | 諸家 |
| 花鳥画と鳥類生態写真 | 内田清之助 |
| 顔見世 | 梶原緋佐子 |
| 材料の話断片 | 鏑木清方 |
| 日本画雑感 | 武者小路実篤 |
| 日本画での社会性 | 外狩素心庵 |
| 湖畔と池辺とを話題に | 西村五雲・金島桂華 |
| 画人風土記 | 添田達嶺 |
| 大阪の展覧会三つ | 大森富平 |
| 絵画と舞台と服飾座談会 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 俳句 | 諸家 |
| 編輯後記 | 楠生 |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・安田半圃 |
第9巻2号(昭和8年(1933)2月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵 | 山元春挙 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵 | 川崎小虎 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 古画写真版 | – |
| 菊池、西山両塾新年会演劇写真版 | – |
| 東西展覧会の概観 | 斎田素州・大森富平 |
| 小栗宗湛 | 笹川臨風 |
| 琉球の画家殷元良筆山水画に就いて | 比嘉朝健 |
| 牧谿の「鶴」と蘿窓の「鶏」 | 荻野三七彦 |
| 日本画での社会性 | 外狩素心庵 |
| 安寿姬の墓 | 山本火子 |
| 俳句 | 諸家 |
| ルッソからピカソへ | 福田平八郞 |
| 日本画とヴンゴオホ | 千家元麿 |
| 俳句 | 諸家 |
| 「芸術は表現也」と云ふ事に就いて | 神崎憲一 |
| 画人風土記 | 添田達嶺 |
| 川合玉堂氏の俳句と人と芸術 | 豊田豊 |
| 麦僊偏観 | 浜崎三夏 |
| 根岸氏の表装界勇退 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 編輯後記 | 楠生 |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・安田半圃 |
第9巻3号(昭和8年(1933)3月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵 | 松林桂月 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵 | 西沢笛畝 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 古画写真版 | – |
| 院展試作展を観る | 豊田豊 |
| 戊辰会展寸観 | 斎田素州 |
| 琅玕洞新作画展 | 豊田豊 |
| 美術観賞の過程 | 長與善郞 |
| 吃のお喋り | 榊原紫峰 |
| 祗園の枝垂桜 | 富田溪山人 |
| 京都美術界古老座談会 | 神崎憲一 |
| 短歌 | 中河幹子 |
| 橋本雅邦翁 | 岡倉覚三 |
| 雅邦先生の龍虎図小下絵に就て | 川合玉堂 |
| 雅邦作御浜御殿襖屏風小下絵長巻に就て | 添田達嶺 |
| 日本画での社会性 | 外狩素心庵 |
| 女流画家としての芸術観 | 梶原緋佐子 |
| 応挙、芦雪の襖絵 | 西沢笛畝 |
| 狩野一庵、一翁、一溪及び栄翁重政に就て | 添田達嶺 |
| 第十三回帝展(第一部)成績に関する具申書 | 島田墨仙・勝田蕉琴・水上泰生 |
| 俳句 | 諸家 |
| 榊原紫峰氏邸ニュース | 加茂川酔歩 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 岡本神草氏を憶ふ | 神崎憲一 |
| 編輯後記 | 楠生 |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第9巻4号(昭和8年(1933)5月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵 | 榊原紫峰 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵 | 水上泰生 |
| 口絵原色版 | – |
| 華山筆口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 華山の花鳥画に就て | 小室翠雲 |
| 華山と竹田 | 松林桂月 |
| 渡辺華山の芸術 | 添田達嶺 |
| 華山とゴッホ | 河野桐谷 |
| 華山雑感 | 竹内梅松 |
| 玉堂と春琴の印章 | 桑原双蛙 |
| 吉野花前記 | 早苗会々員 |
| 椿燃ゆる大島 | 藤井霞郷 |
| 幼き頃の想ひ出 | 上村松園 |
| 断片語 | 中河与一 |
| 林塢亭雑誌 | 小野竹喬 |
| 春宵女絵師彼是話 | 加茂川酔歩 |
| 俳句 | 諸家 |
| 展覧会批評 | – |
| 国性劇を観る | 斎田素州 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 森田恒友君の死 | 脇本楽之軒 |
| 編輯後記 | 楠生 |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第9巻5号(昭和8年(1933)6月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵 | 結城素明 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵 | 小室翠雲 |
| 口絵原色版 | – |
| 国宝障屏画写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 南画院第十二回展概観 | 豊田豊 |
| 白田舎第一回展寸感東台邦画会小品展概観 | 斎田素州 |
| 南画院展全作品評 | 小室翠雲 |
| 南画の鑑賞 | 添田達嶺 |
| 四季・花鳥・芸その他 | 榊原紫峰 |
| 門弟婚儀の挨拶腹案 | 川端龍子 |
| スタートを切り直せ | 田沢田軒 |
| 残月(画並文) | 小早川秋聲 |
| 瑞竹(画並文) | 安田半圃 |
| 天龍峽を下る(画並文) | 池上秀畝 |
| 野州川治行き(画並文) | 児玉希望 |
| 画と書との関係 | 池上秀畝 |
| 陶片集 | 富本憲吉 |
| 古名画の観賞 | 秋山光夫 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 編輯後記 | 楠生 |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第9巻6号(昭和8年(1933)7月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(観瀑) | 島田墨仙 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(唐黍) | – |
| 口絵原色版・口絵写真版 | 池上秀畝 |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 京都六大塾展概観 | 神崎憲一 |
| 絵画の生命 | 塩田力蔵 |
| 画境と歌境 | 倉田百三 |
| 応挙館に就て | 国井応祥 |
| 東京と京都 | 竹内栖鳳 |
| 四季引分の風邪 | 富田溪仙 |
| 魚釣り漫談 | 福田平八郞 |
| 画人風土記 | 添田達嶺 |
| 霊山探勝記(画並文) | 棚田暁山 |
| 歴史画と山水画 | 小村大雲 |
| 挿絵の心境を語る | 中村大三郞 |
| 俳句 | 諸家 |
| 京都各塾展覧会批評 | 神崎憲一 |
| 京都塾展への一面観 | 豊田豊 |
| 東京三塾展覧会寸評 | 斎田素州 |
| 輪番校長制の実現 | 神崎憲一 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第9巻7号(昭和8年(1933)8月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(不忍晩涼) | 小室翠雲 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(茄子) | 永田春水 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 古画写真版 | – |
| 東京の諸展覧会概観 | 斎田素州 |
| 画人春挙片影 | 神崎憲一 |
| 山元春挙君の作品 | 正木直彦 |
| 山元春挙さんと私 | 川合玉堂 |
| 春挙先生を憶ふ | 川村曼舟 |
| 山元春挙画伯略年譜 | – |
| 短歌 | 中河幹子 |
| 五つのもの | 高村光太郞 |
| 自分の好きな日本画家 | 武者小路実篤 |
| 画人風土記 | 添田達嶺 |
| 日本画壇の推移 | 黒田鵬心 |
| 現代画壇の諸問題を語る座談会 | 川崎小虎・矢澤弦月・豊田豊 |
| 俳句 | 諸家 |
| 愚かな感想 | 田中宇一郞 |
| 奈良で拾った話 | 浜崎三夏 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第9巻8号(昭和8年(1933)10月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(土) | 川端龍子 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(蟲の秋) | 町田曲江 |
| 口絵原色版 | 島田墨仙・山口蓬春 |
| 口絵写真版 | 川合玉堂・平福百穂・松岡映丘・永田春水・小室翠雲・西村五雲 |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 古画写真版 | – |
| 堂本印象氏の東福寺天井絵 | – |
| 回顧紛々 | 横山大観 |
| 大観の新らしさ | 長與善郞 |
| 院展の日本画所見 | 神崎憲一 |
| 院展新人の諸作 | 豊田豊 |
| 日本美術院史 | 添田達嶺 |
| 会場芸術の意義 | 川端龍子 |
| 青龍社を見て | 武者小路実篤 |
| 青龍展の問題作 | 斎田素州 |
| 青龍展入選画概観 | 坂口一草 |
| 青龍社五周年の回顧 | 添田達嶺 |
| 俳句 | 諸家 |
| 真個文人画 | 関如来 |
| 安信と琉球の自了 | 比嘉朝健 |
| 想片 | 速水御舟 |
| 写生旧懐(絵と文) | 池田遙邨 |
| スケッチブックを携へて(絵と文) | 上村松篁・水野深草・望月玉成・井上正晴・石島良則 |
| 飯坂、鬼怒川温泉 | 勝田蕉琴 |
| 展覧会批評 | 大森富平・神崎憲一 |
| 小茂田君と私 | 吉田幸三郞 |
| 噫、小茂田君 | 速水御舟 |
| 小茂田君の思ひ出 | 小山大月 |
| 小茂田青樹氏略年譜 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第9巻9号(昭和8年(1933)11月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(晩秋) | 西村五雲 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(栗) | 小室翠雲 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 堂本印象氏(東福寺本堂画龍) | – |
| 渡辺華山筆(諷諫偶意画卷) | – |
| 第十四回帝展日本画に就て諸家の批評並に感想 | – |
| 日本画の鑑審査と入選作品の主傾向 | 荒木十畝 |
| 山水画を語る | 川合玉堂 |
| 花鳥画縦横論 | 小室翠雲 |
| 人物画を語る | 鏑木清方 |
| 所謂南画の山水 | 松林桂月 |
| 帝展の数作に就て | 中河与一 |
| 特選を超ゆるもの | 神崎憲一 |
| 閨秀画家と其作品 | 豊田豊 |
| 文展出世作物語 | 添田達嶺 |
| 京このみ | 西村五雲 |
| 断想 | 小林古径 |
| 激湍の鮎 | 福田平八郞 |
| 石仏について | 室生犀星 |
| 俳句 | 諸家 |
| 華山筆諷諫偶意画巻 | 望月信成 |
| 展覧会批評 | – |
| 噫、蔦谷龍岬君 | 矢沢弦月 |
| 田村彩天君の事ども | 吉田秋光 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第9巻10号(昭和8年(1933)12月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(鯉網) | 野田九浦 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(山茶花) | 永田春水 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 水郷二題「潮来」「鹿島」 | 小室翠雲 |
| 鬼怒川峡谷「蒟蒻橋」「川治温泉」 | 今井爽邦 |
| 百穂没後の日本画壇 | 黒田鵬心 |
| 偈 | 関如来 |
| 平福君の芸術 | 結城素明 |
| 平福君を悼む | 鏑木清方 |
| 真画人百穂氏 | 川端龍子 |
| 百穂画伯の語った少年時代の想出の追憶 | 田沢田軒 |
| 平福百穂画伯年譜 | 添田達嶺編 |
| 平福穂庵の事ども | 添田達嶺 |
| 筆墨硯に就ての対話 | 正木直彦・河原田平助 |
| 絹と紙の話と師弟の間柄の話 | 上村松園 |
| 画家と貧乏 | 北野恒富 |
| 竹杖会の変革と早苗会の更正 | 神崎憲一 |
| 画人風土記 | 添田達嶺 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第10巻(昭和9年(1934)1月~12月)
第10巻1号(昭和9年(1934)1月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(竹林喜雀) | 竹内栖鳳 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(瑞春) | 小室翠雲 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 琳派特集写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第10巻2号(昭和9年(1934)2月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(春寒) | 鏑木清方 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(椿) | 水上泰生 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 文人画特集写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第10巻3号(昭和9年(1934)3月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(紅梅) | 菊池契月 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(春暖) | 松本姿水 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 大和諸寺仏像写真版 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第10巻4号(昭和9年(1934)4月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(雛) | 西山翠嶂 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(獅子) | 矢野鐡山 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 古画、蒔絵等写真版 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第10巻5号(昭和9年(1934)5月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(花柘榴) | 富田溪仙 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(蔬菜) | 安田半圃 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 鳥類写真版 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第10巻6号(昭和9年(1934)6月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(巣立ち) | 西村五雲 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(蟲) | 金島桂華 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第10巻7号(昭和9年(1934)7月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(花桐) | 荒木十畝 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(双鯉) | 徳岡神泉 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 湯泉客舎夜話 | 竹内栖鳳 |
| 竹堂、楳嶺、栖鳳、玉堂 | 西村五雲・加藤英舟 |
| 斯くして画家に | 土田麦僊 |
| 半古先生に入門した頃 | 小林古径 |
| 越後人小林古径 | 神崎憲一 |
| それからそれ | 宇野浩二 |
| 素人の絵 | 畑耕一 |
| 画人風土記 | 添田達嶺 |
| 西山温泉 | 村雲大樸子 |
| 日本画の批評に就て | 大森富平 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第10巻8号(昭和9年(1934)8月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(享保時代の盆踊) | 上村松園 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(雨後清流) | 田中咄哉州 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 古画、蒔絵写真版 | – |
| 漫談抄 | 安田靫彦 |
| 湖南博士と入木道 | 井土霊山 |
| 紀州人、川端龍子 | 神崎憲一 |
| 漆画の新興に就て | 吉野富雄 |
| 草堂寺の応挙と芦雪 | 佐藤春夫 |
| 筆山主人の蘭画に就て | 比嘉朝健 |
| 金子豊水と斎藤香玉 | 竹内梅松 |
| 下岡蓮杖翁(画人風土記) | 添田達嶺 |
| 遊星子雑感 | 竹原嘲風 |
| 博物館其他の感想 | 田中宇一郞 |
| 舞踊『年中行事絵』 | 豊田豊 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第10巻9号(昭和9年(1934)9月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(秋池) | 橋本関雪 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(吹笛) | 松本一洋 |
| 口絵原色版 | – |
| 雪舟筆写真版 | – |
| 上高地其他の地方の写生画写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 古画其他写真版 | – |
| 雪舟の芸術 | 正木直彦 |
| 画聖雪舟に就て | 溝口禎次郞 |
| 雪舟花鳥画の問題 | 田中一松 |
| 雪舟の写実味 | 川合玉堂 |
| 雪舟の仏画 | 島田墨仙 |
| 雪舟雑感 | 野田九浦 |
| 雪舟の庭園 | 福田浩湖 |
| 蛇酒を飲んだ雪舟 | 国枝史郞 |
| 奥武蔵吟遊 | 斎田素州 |
| 鵙の早贄 | 籾山徳太郞 |
| 俳句 | 諸家 |
| 雲石二州の画家 | 桑原羊次郞 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第10巻10号(昭和9年(1934)10月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(葡萄) | 川端龍子 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(紅蜀葵) | 石川寒巌 |
| 口絵原色版 | – |
| 満州国献上画写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| スケッチ写真版 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第10巻11号(昭和9年(1934)11月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(日向ぼこ) | – |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(果実) | 落合朗風 |
| 口絵原色版 | – |
| 帝展出品に因む素描 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| スケッチ写真版 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第10巻12号(昭和9年(1934)12月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙(冬暄) | 堂本印象 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(浅春) | 木本大果 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 竹田筆写真版 | – |
| 円山四条派写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 古画其他写真版 | – |
| 温習会舞台背景 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第11巻(昭和10年(1935)1月~12月)
第11巻1号(昭和10年(1935)1月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(機声) | 川合玉堂 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(ひわ) | 金島桂華 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 百穂筆写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 古画其他写真版 | – |
| 鶴の生態写真版 | – |
| スケッチ網目凸版 | – |
| 鶴画談片 | 相見香雨 |
| 鶴の話 | 内田清之助 |
| 素人の絵 | 斎藤隆三 |
| 雪の東照宮(短歌) | 中河幹子 |
| 作画術の研究 | 塩田力蔵 |
| 京のその頃 | 上村松園 |
| 趁春記(絵と文) | 望月春江 |
| 百穂氏の芸術 | 添田達嶺 |
| 百穂氏の生涯 | 富樫小兎 |
| 舞台装置のこと二三 | 長谷川伸 |
| 風の如くに | 中河与一 |
| 姓名判断 | 畑耕一 |
| 神宮絵画館観謹記 | 豊田豊 |
| 菅原白龍翁 | 添田達嶺 |
| 画僧棟隠の一遺作 | 平田六郞 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第11巻2号(昭和10年(1935)2月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(浅春) | 結城素明 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(紅白梅) | 宇田荻邨 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 古画其他写真版 | – |
| スケッチ網目凸版 | – |
| 日本画洋画の弁 | 石井柏亭 |
| 日本画の新しい方向 | 竹内勝太郞 |
| 宗達から受くるもの | バーナード・リーチ |
| 雪 | 飛田周山 |
| 画讃について | 尾上柴舟 |
| 刀剣 | 小杉放庵 |
| 美術人と俳句 | 田沢田軒 |
| 俳句 | 諸家 |
| 朝鮮古美術史跡巡礼 | 下店静市 |
| 画人宮本武蔵 | 添田達嶺 |
| 批評する心 | 神崎憲一 |
| 展覧会批評 | 斎田素州 |
| 紫峰花鳥画集 | 神崎憲一 |
| 高取稚成氏逝く | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第11巻3号(昭和10年(1935)3月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(江頭春霞) | 川村曼舟 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(蔬菜) | 水上泰生 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 庭園写真版 | – |
| 極東第一の画 | 福井利吉郞 |
| 庭園写真解説 | 龍居松之助 |
| 日本庭園概説 | 高橋箒庵 |
| 造園と絵画 | 正木直彦 |
| 日本の庭 | 龍居松之助 |
| 林泉雑記 | 小山大月 |
| 支那の庭園 | 村松梢風 |
| 茶道放談 | 田中親美 |
| 床の間と日本画 | 西川一草亭 |
| 床の間 | 野田九浦 |
| 島田雪谷と野口小蘋 | 添田達嶺 |
| 朝鮮古美術史跡巡礼 | 下店静市 |
| 神宮壁画を終りて | 北野恒富 |
| 神武大帝尊像拝写記 | 岡山聖虚 |
| 永福寺雑記 | 中川一政 |
| 清方と荘八 | 広瀬熹六 |
| 芋銭氏の芸術と嵩谷 | 田中宇一郞 |
| 展覧会批評 | – |
| 帝展改革問題議会質問速記録 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第11巻4号(昭和10年(1935)4月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵 | 松林桂月 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵 | 池上秀畝 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 院試作・春の青龍展春虹会・小室翠雲個展三人評 | 添田達嶺・神崎憲一・斎田素州 |
| 放心の表情 | 谷川徹三 |
| 美に就ての雑感 | 武者小路実篤 |
| 日本美術雑感 | 千家元麿 |
| 図案と日本画 | 杉浦非水 |
| 赤津にて | 富本憲吉 |
| 芭蕉と義士の俳句 | 田沢田軒 |
| 画壇閑話 | 加茂川酔歩 |
| 印象氏の信貴山襖絵 | 神崎憲一 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 展覧会 | – |
| 雑彙 | – |
| 個人消息 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第11巻5号(昭和10年(1935)5月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵 | 山口蓬春 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵 | 徳岡神泉 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 古名画写真版 | – |
| 故速水御舟遺作集 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 古画の鑑賞に就て | 溝口禎次郞 |
| 華山先生と鄭所南 | 松林桂月 |
| 大阪大茶会記 | 外狩素心庵 |
| 速水御舟氏追悼録 | – |
| 速水御舟君の足跡 | 安田靫彦 |
| 畏友速水御舟君 | 小林古径 |
| 速水の横顔 | 吉田幸三郞 |
| 悲しき追憶記 | 速水彌子 |
| 京都時代の速水君 | 内貴清兵衞 |
| その頃の生活 | 小山大月 |
| 目黒時代の思ひ出 | 長谷川昇 |
| 少年の日の速水君 | 田中咄哉州 |
| 作品を通じた速水君 | 菊池契月 |
| 速水氏の近作二三 | 西村五雲 |
| 江戸っ児御舟 | 高沢初風 |
| 不取敢の記 | 神崎憲一 |
| 速水御舟画伯略年譜 | – |
| 昔人の桜の歌句 | 富田溪仙 |
| 台湾から | 勝田国哲 |
| 五号館の昔を語る | 添田達嶺 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第11巻6号(昭和10年(1935)6月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵 | 小室翠雲 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵 | 田中咄哉州 |
| 口絵原色版 | – |
| 鉄斎遺作写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 帝展よ何処へ行く | 添田達嶺 |
| 堺時代の鉄斎翁 | 正木直彦 |
| 鉄斎翁に就ての漫草 | 望月信成 |
| 画壇三秀 | 吉井勇 |
| 四十年前の作家回顧 | 関如来 |
| 不易流行 | 西山翠嶂 |
| 南洋を描く | 川端龍子 |
| 南画展を見て | 武者小路実篤 |
| 南画院展評 | 添田達嶺 |
| 朝鮮古美術史跡巡礼 | 下店静市 |
| 不動明王 | 広瀬熹六 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 展覧会 | – |
| 雑彙 | – |
| 個人消息 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第11巻7号(昭和10年(1935)7月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵 | 小杉放庵 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵 | 永田春水 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 書道と画道 | 工藤壮平 |
| 書画道一致論 | 今井爽邦 |
| 西洋画と日本画 | 川島理一郞 |
| 絵画協会の最盛期 | 関如来 |
| 九州人荒木十畝 | 神崎憲一 |
| 元禄頃の小袖文様 | 吉田堯文 |
| 和光院の不動明王 | 木村武山 |
| 歴史画の復興 | 豊田豊 |
| 展覧会批評 | – |
| 帝国美術院改組顛末日記 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第11巻8号(昭和10年(1935)8月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵 | 川端龍子 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵 | 松本姿水 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 六甲山 | 村上華岳 |
| 能地 | 田中咄哉州 |
| 個展時代 | 神崎憲一 |
| 個展論 | 鏑木清方 |
| 個展自弁 | 川端龍子 |
| 好き勝手な個展 | 土田麦僊 |
| 個展は難しい | 村上華岳 |
| 自らを歌ふ(短歌) | 梶原緋佐子 |
| 個展雑感 | 岡田三郞助 |
| 一人展私観 | 津田青楓 |
| 個展漫筆 | 藤井浩祐 |
| 個展の収獲 | 福田平八郞 |
| 個展を顧みて | 伊東深水 |
| 絵画協会の最盛期 | 関如来 |
| 寬快、寬畝、十畝 | 添田達嶺 |
| 備後の帝釋峡へ | 小早川秋聲 |
| 展覧会批評 | – |
| 清方氏の舞台装置 | 豊田豊 |
| 竹内勝太郞の死 | 榊原紫峰 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・川端龍子・土田麦僊・福田平八郞・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・梶原緋佐子・安田半圃 |
第11巻9号(昭和10年(1935)9月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵 | 菊池契月 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵 | 望月春江 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 僧画写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 坊さんの絵に就て | 正木直彦 |
| 白隠師弟の絵事 | 森大狂 |
| 良寬の書について | 相馬御風 |
| 良寬和尚を尋ねて | 横尾翠田 |
| 画僧風外 | 添田達嶺 |
| 香積寺風外禅師 | 高橋竹迷 |
| 仙厓の絵に就て | 安達荒村 |
| 龍泰寺仏乗禅師 | 高橋竹迷 |
| 僧画の真骨頂 | 神崎憲一 |
| 日本画壇回顧四十年 | 関如来 |
| 伝統礼讃 | 藤田嗣治 |
| わすれぬもの | 長谷川時雨 |
| 橋本左内先生の肖像 | 島田墨仙 |
| さんいんの海岸 | 池田遙邨 |
| 展覧会批評 | – |
| 長唄の一蝶と歌麿 | 高沢初風 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第11巻10号(昭和10年(1935)10月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵 | 福田平八郞 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵 | 池田遙邨 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 速水御舟遺作写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 絵画と建築 | 佐藤功一 |
| 五味子と墨の話 | 沖野岩三郞 |
| 藤原時代に美を求めて | 吉村忠夫 |
| 金地彩色絵に就て | 山下新太郞 |
| 壁画模写回想 | 荒井寬方 |
| 身辺雑感 | 斎藤素巌 |
| 新秋感傷 | 松本姿水 |
| 猿投神社の鎧 | 前田青邨 |
| 橋本雅邦と川端玉章 | 関如来 |
| 寬快、寬畝、十畝 | 添田達嶺 |
| 利根出水所見(俳句) | 小川芋銭 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第11巻11号(昭和10年(1935)11月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵 | 伊東深水 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵 | 永田春水 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 現代の日本画 | 福井利吉郞 |
| 橋本雅邦と川端玉章 | 関如来 |
| 日本画と西洋画 | 安井曾太郞 |
| 佗び寂びの絵 | 里見勝蔵 |
| 山麓月夜(短歌) | 杉浦翠子 |
| 偶感二則 | 石井柏亭 |
| 平福百穂先生を憶ふ(短歌) | 中河幹子 |
| 写生 | 中村丘陵 |
| 私の日課 | 北村西望 |
| 好きといふのみ | 土師清二 |
| 安々園楽々荘閑話 | 邨田丹陵 |
| 帰郷小感 | 勝田蕉琴 |
| 海辺小景 | 永田春水 |
| 富士登山二十句(俳句) | 野田九浦 |
| 神代の古寺 | 田中宇一郞 |
| 播州人松岡映丘 | 神崎憲一 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第11巻12号(昭和10年(1935)12月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵 | 荒木十畝 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵 | 勝田蕉琴 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 瀬戸内海探勝図写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 故きを温ねて | 溝口禎次郞 |
| 台湾風物ところ[ドコロ] | 荒木十畝 |
| 弓と絵 | 堅山南風 |
| 画境私語 | 太田聴雨 |
| 挿絵に就て | 邦枝完二 |
| 飼鳥閑談 | 水上泰生 |
| 仏像・絵画の発見 | 木村武山 |
| 映画「かぐや姫」のこと | 服部有恒 |
| 肥後に於ける雲谷派矢野吉重と其の一門 | 添田達嶺 |
| 秋田派南蛮絵に就て | 竹内梅松 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第12巻(昭和11年(1936)1月~12月)
第12巻1号(昭和11年(1936)1月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(初霞) | 川合玉堂 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵 | 池上秀畝 |
| 口絵原色版 | 小林古径・伊東深水 |
| 口絵写真版 | – |
| 水風清(高島屋新作画展) | 竹内栖鳳 |
| 返照(東京会新作画展) | 川合玉堂 |
| 皇后冊立(明治神宮壁画) | 菅楯彦 |
| 翺翔開雲(献上屏風) | 堂本印象 |
| 勤王画人特集写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 古画写真版 | – |
| 湯泉第一楼夜話 | 竹内栖鳳 |
| 身辺閒談 | 小川芋銭 |
| 勤王画人略伝 | 添田達嶺 |
| 草雲先生の芸術境 | 小室翠雲 |
| 勤王の画家菊池容斎 | 結城素明 |
| 崋山先生の画業 | 松林桂月 |
| 藤田小四郞の画蹟 | 斎藤隆三 |
| 頼山陽の画筆一抹 | 木崎好尚 |
| 杏所と東湖 | 池上秀畝 |
| 武田耕雲斎のこと | 高橋皞 |
| 老龍庵星巌先生 | 飯塚鵜涯 |
| 一蕙斎浮田可為先生 | 森村宜稲 |
| 藤本鉄石の一挿話 | 古川北華 |
| 村山半牧のこと | 横尾翠田 |
| 文麟・鉄斎・寬斎 | 神崎憲一 |
| 杏所、耕雲斎、小四郞 | 竹内原風 |
| 初春(短歌) | 柳原燁子 |
| 始興・何帛其他 | 添田達嶺 |
| 舞妓のことなど | 中澤弘光 |
| 酒と凧 | 牧野虎雄 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第12巻2号(昭和11年(1936)2月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(家兎絹本尺八横) | 竹内栖鳳 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(臘梅小禽) | 永田春水 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 霜霽(三越日本画展) | 結城素明 |
| 鳩(三越日本画展) | 松林桂月 |
| 鴛鴦髷(三越日本画展) | 上村松園 |
| 観音(松島画舫新作画展) | 村上華岳 |
| 宇治晴雲(松島画舫新作画展) | 小野竹喬 |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 古画写真版 | – |
| 雪国旅情 | 川合玉堂 |
| 銀閣寺の庭園 | 五十嵐力 |
| 雪を描く | 辻永 |
| 身辺雑感 | 小村雪岱 |
| 熱田神宮遷座祭(和歌) | 森村宜稲 |
| 橋本雅邦 | 関如来 |
| 是真の魚類図 | 西沢笛畝 |
| 光琳筆扇面散し屏風 | 大森富平 |
| 罪の画家懐月堂安度 | 添田達嶺 |
| 新歴史画の提唱 | 河野桐谷 |
| 不断帖 | 中河与一 |
| 眼 | 金原省吾 |
| 散木会のはなし | 畑耕一 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第12巻3号(昭和11年(1936)3月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(春、絹本二尺横物) | 上村松園 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(雛) | 西沢笛畝 |
| 口絵原色版 | – |
| 古今閨秀画人特集写真版 | – |
| 汀(六潮会第五回展) | 山口蓬春 |
| 虎杖(個展) | 小杉放庵 |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 松園女史讃頌 | 神崎憲一 |
| 女雪信の話 | 添田達嶺 |
| 大雅堂夫人玉瀾女史 | 人見少華 |
| 文晁夫人幹々女史 | 佐竹永陵 |
| 江馬細香と梁川紅蘭 | 添田達嶺 |
| 立原春沙女史 | 飛田周山 |
| 斎藤香玉のことども | 竹内原風 |
| 奥原晴湖について | 藤懸静也 |
| 私の母野口小蘋 | 野口小蕙 |
| 伯母跡見花蹊のこと | 跡見泰 |
| 河崎蘭香と栗原玉葉 | 野田九浦 |
| 愛の画家池田蕉園 | 荒井寬方 |
| 閨秀作家の道 | 神崎憲一 |
| 門人を語る | – |
| 現代閨秀作家概観 | 神崎憲一 |
| 現代閨秀作家概観 | 大森富平 |
| 現代閨秀作家概観 | 豊田豊 |
| 古今閨秀画人略伝 | 松の里人 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第12巻4号(昭和11年(1936)4月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(早春流、絹尺八横) | 山口蓬春 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(山吹小禽) | 堅山南風 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 帝展全出品写真版 | – |
| 古画写真版 | – |
| 入江為守子筆「夏夕」「曲水」 | – |
| 新帝展の一大収穫 | 溝口禎次郞 |
| 帝展所感 | 長谷川如是閑 |
| 帝展総観 | 紀淑雄 |
| 新帝展「門外観」 | 宇野浩二 |
| 改組と帝展型 | 川路柳虹 |
| 新帝展に対する肯定的見解と否定的見解 | 横川毅一郞 |
| 感想と短評 | 黒田鵬心 |
| 帝展入選画の中から | 金井紫雲 |
| 帝展の欲しい作品二つ | 本山豊実 |
| 帝展の三作品 | 関長次郞 |
| 橋本雅邦 | 関如来 |
| 日本画と西洋画 | 硲伊之助 |
| 東洋画の材料に就て | 安宅安五郞 |
| 日本画の描線に就て | 広瀬憙六 |
| 美の追求 | 武者小路実篤 |
| 鯉の思ひ出 | 五十嵐力 |
| 踊りを見ながら感じたこと | 谷川徹三 |
| 紀楳亭の画蹟に就て | 望月信成 |
| 琉球の画家呉著温 | 比嘉朝健 |
| 逝ける入江為守子 | 添田達嶺 |
| 石川寒巌氏逝く | 斎田素州 |
| 大阪美術展批評 | 大森富平 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第12巻5号(昭和11年(1936)5月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(新月絹尺八横) | 橋本関雪 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(鯉紙二尺横) | 橋本静水 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 吉野春風(春虹会第二回展) | 富田溪仙 |
| 猫(春虹会第二回展) | 金島桂華 |
| 春宵(春虹会第二回展) | 上村松園 |
| 青白梅雀(第三回日本画個展) | 津田青楓 |
| 酒顚童子絵巻(ノ内五図) | 狩野孝信 |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 古実家の立場より見た歴史画及歴史画家 | 関保之助 |
| 武者絵雑感 | 松岡映丘 |
| 鎧の美に就いて | 前田青邨 |
| 武者絵の名作 | 服部有恒 |
| 鎧直垂のこと | 伊東紅雲 |
| 武者絵と小掘先生 | 小山栄達 |
| 酒顚童子絵巻考 | 秋山光夫 |
| 古今の画龍 | 市村瓉次郞 |
| かつしか栄女 | 山口林治 |
| 十市石谷に就て | 添田達嶺 |
| 巨然筆溪山蘭若図巻 | 原田尾山 |
| 主題応答 | 川端龍子 |
| 陶器に寄する言葉 | 田辺至 |
| 展覧会批評 | – |
| 紀先生の思ひ出 | 仲田勝之助 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第12巻6号(昭和11年(1936)6月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(紫陽花絹尺八横) | 富田溪仙 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(漁閑紙尺五横) | 酒井三良 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 午涼(個展) | 小室翠雲 |
| 丹頂鶴(踏青会第二回展) | 榊原紫峰 |
| 緑雨(踏青会第二回展) | 小川芋銭 |
| 海風(踏青会第二回展) | 大智勝観 |
| 餌(九皐会第二回展) | 奥村土牛 |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 展覧会の過去及将来 | 正木直彦 |
| 正道を行く芸術 | 野田九浦 |
| 潮岬と室戸崎 | 藤島武二 |
| 画家と筆 | 島田墨仙 |
| 身辺雑感 | 香取秀真 |
| 牡丹を写す | 石崎光瑤 |
| 地方色的なものゝ再吟味 | 加藤信也 |
| 大口代議士の質問とそれに対する感想 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第12巻7号(昭和11年(1936)7月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(婦女 絹尺五横) | 中村大三郎 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(桔梗 紙二尺横) | 木本大果 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 故土田麦僊遺作集 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 麦僊君の苦学時代 | 石崎光瑤 |
| 土田君を憶ふ | 田中喜作 |
| 噫土田君 | 西山翠嶂 |
| 土田君の死 | 榊原紫峰 |
| 平明の天才土田君 | 村上華岳 |
| 麦僊兄を憶ふ | 小野竹喬 |
| 土田麦僊君を憶ふ | 大原孫三郞 |
| 巨人地に墜つ | 西村五雲 |
| しのぶぐさ | 鏑木清方 |
| 二つの面 | 菊池契月 |
| 麦僊の急逝を惜む | 梅原龍三郞 |
| 土田さんの芸術 | 上村松園 |
| その人と作品 | 神崎憲一 |
| 麦僊氏を偲ぶ | 添田達嶺 |
| 終焉記 | 土田千代子 |
| 土田麦僊氏略年譜 | – |
| 梅雨吟行(句画) | 川合玉堂 |
| 橋本雅邦 | 関如来 |
| 盲人の世界 | 川島理一郞 |
| 花鳥画十年 | 山口蓬春 |
| 下村さんの若い頃 | 木村武山 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第12巻8号(昭和11年(1936)8月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(百合 絹二尺横) | 中村岳陵 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(葡萄 絹尺五横) | 三輪晁勢 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 故富田溪仙遺作集 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 理想主義者富田君 | 横山大観 |
| 富田も死んだ | 内貴清兵衛 |
| 富田溪仙氏のこと | 吉江喬松 |
| 噫富田君 | 西村五雲 |
| 富田さんの思ひ出 | 福田平八郞 |
| クロオデル・溪仙の交遊 | 山内義雄 |
| 観世音(詩) | 富田溪仙 |
| 燕巣楼今昔譚 | 加茂川酔歩 |
| 卅余年前の片影 | 飛松甚吾 |
| ありし日の溪仙画伯 | 辻本和一 |
| 一盲撫象記 | 神崎憲一 |
| 苦学時代の富田先生 | 佐藤梅軒 |
| 溪仙先生追憶 | 河原田平助 |
| 魂を牽引する力 | 増井栄 |
| 家系や少年時代 | 藤子刀自 |
| 富田溪仙氏略年表 | – |
| 「曲亭馬琴」の思ひ出 | 鏑木清方 |
| 処女作「のどか」の事 | 伊東深水 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第12巻9号(昭和11年(1936)9月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(牽牛花 絹尺八横) | 伊東深水 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵 | 松本姿水 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 北海道写生写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 水墨画のこと | 正木直彦 |
| 水墨画に就て | 川合玉堂 |
| 破墨山水 | 溝口禎次郞 |
| 北宗墨画の一源流 | 相見香雨 |
| 墨のはなし | 小杉放庵 |
| 水墨山水画私観 | 飛田周山 |
| 修業道としての水墨画 | 大智勝観 |
| 私の水墨画に就て | 近藤浩一路 |
| 身辺雑感 | 奥村土牛 |
| 箱根にて(俳句) | 川合玉堂 |
| 漆絵のはなし | 山村耕花 |
| その後の南蛮もの | 長野草風 |
| 松霞安田翁の深秀園 | 市嶋春城 |
| 美術記者の頃 | 松原寬 |
| 芝居絵雑感 | 河竹繁俊 |
| 花鳥画に就て | 吉田秋光 |
| 装飾画といふこと | 高木保之助 |
| 維新志士遺墨展 | 添田達嶺 |
| 吾妻溪谷を行く | 田中宇一郞 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第12巻10号(昭和11年(1936)10月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(紅粧美絹二尺横) | 川端龍子 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(秋趣 紙尺四横) | 落合朗風 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 故富田溪仙遺作補遺 | – |
| 風土と美術 | 荒木十畝 |
| 非常時の野展概観 | 神崎憲一 |
| 各新聞の院展・青龍展・明朗展評 | – |
| ボストンに於ける天心先生の思ひ出 | 六角紫水 |
| 東京美校紛擾事件 | 関如来 |
| 日本南画院解散後に | 矢野橋村 |
| 新説乞食月僊 | 杉浦冷石 |
| 印象氏の三宝院襖絵 | 神崎憲一 |
| 青樹社第三回展 | 杉浦冷石 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第12巻11号(昭和11年(1936)11月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(秋晴 絹尺八横) | 荒木十畝 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(朝 紙尺五横) | 田中咄哉州 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 展覧会雑感 | 高田早苗 |
| 加筆 | 林癸未夫 |
| 身辺雑感 | 和田英作 |
| 新文展概観 | 神崎憲一 |
| 各新聞の新文展招待展評 | – |
| 浦の秋(句と画) | 川合玉堂 |
| 新文展総観図 | 豊田豊 |
| 各新聞の新文展鑑査展評 | – |
| 風俗偶感 | 島田墨仙 |
| 風俗画について | 伊東深水 |
| 探幽の墓所を繞って | 狩野探道 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第12巻12号(昭和11年(1936)12月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(菊池次郞 絹二尺横) | 松岡映丘 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(山茶花 紙尺八横) | 永田春水 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 清津峡谷黒岩の險 | 堅山南風 |
| 二居新道より見たる溪谷の奥 | 堅山南風 |
| 書と画 | 中村不折 |
| 硬質作画術 | 塩田力蔵 |
| 中京三傑会略評 | 高橋箒庵 |
| 隆能源氏の顔合せ | 杉浦冷石 |
| 白河楽翁公 | 添田逹嶺 |
| 初転法輪寺の壁画 | 野生司香雪 |
| 琉球の肖像画と其進展 | 比嘉朝健 |
| 清津峡谷を探ねて | 堅山南風 |
| 舞踊画に就て | 山川秀峰 |
| 東京美校紛擾事件 | 関如来 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第13巻(昭和12年(1937)1月~12月)
第13巻1号(昭和12年(1937)1月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(田家早梅白金紙尺八) | 西山翠嶂 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(松に小禽紙尺五横) | 堅山南風 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 古今余技画特集写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 余技画の妙趣 | 正木直彦 |
| 松平春嶽公と私の父 | 島田墨仙 |
| 山内容堂侯の絵 | 池上秀畝 |
| 大院君の絵の話 | 添田達嶺 |
| 大石良雄の絵事 | 安達荒村 |
| 画人江川太郞左衛門 | 添田達嶺 |
| 先代団十郞の日本画 | 市川三升 |
| 美術・工芸家の余技画 | 破竹翁如来 |
| 佐久間象山と秋月古香 | 一記者 |
| 余技の日本画 | 川崎克 |
| 日本画観 | 朝倉文夫 |
| 日本画の楽しみ | 北村西望 |
| 私の日本画 | 建畠大夢 |
| 日本画を描く | 藤井浩祐 |
| 日本画私観 | 藤田嗣治 |
| 日本画のこと | 富本憲吉 |
| 宮本武蔵の絵に就いて | 添田達嶺 |
| 新春雑感 | 溝口禎次郞 |
| 日本民族性と美術 | 西村真次 |
| 述懐(詩と画) | 児玉希望 |
| 芸術に現はれたる牛 | 金井紫雲 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第13巻2号(昭和12年(1937)2月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(山ふところ絹二尺横) | 川合玉堂 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(冬閑紙尺二横) | 酒井三良 |
| 裏表紙絵(蒲公英紙尺五横) | 木本大果 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 俳画人涼袋特集写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 秩父宮同妃両殿下の御下問に答へ奉りて | 佐々木嘉太郞 |
| 建部涼袋のこと | 伊藤松宇 |
| 寒葉斎と其遺墨に就て | 西村南岳 |
| 南蘋派の花鳥画に就て | 添田達嶺 |
| ブルーノ・タウト氏の日本画観 | 岡田俊一 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 尾竹竹坡君と僕 | 永井久晴 |
| 展覧会批評 | – |
| 財産税の芸術に及ぼす影響 | 正木直彦 |
| 美術協会の二元老逝く | 添田達嶺 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第13巻3号(昭和12年(1937)3月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(王献之絹二尺横) | 島田墨仙 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(加茂の尭絹尺三横) | 池田遙邨 |
| 裏表紙絵(樫鳥) | 徳岡神泉 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 熱海梅園にて | 小室翠雲 |
| たなご釣(絵と句) | 伊東深水 |
| 獅子頭、増長天の鬼 | 奥村土牛 |
| 琉球の石彫刻九種 | – |
| 加茂人形四種 | – |
| 御所人形裸童四態 | – |
| 絵画と文学 | 本間久雄 |
| 最近の制作と日本画 | 高間惣七 |
| 画人と教養 | 添田達嶺 |
| 琉球の石彫刻に就て | 比嘉朝健 |
| 破笠と団十郞 | 杉浦冷石 |
| 寺崎広業先生を想ふ | 正木直彦 |
| 余技三味線 | 斎藤素巌 |
| 普茶礼讃 | 鈴木吉祐 |
| 熱海詠抄(歌) | 田口掬汀 |
| 人形蒐集二十年 | 西沢笛畝 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 林檎と雪 | 豊田豊 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第13巻4号(昭和12年(1937)4月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(ほととぎす絹二尺横) | 鏑木清方 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(杜鵑紙尺五横) | 池上秀畝 |
| 裏表紙絵(下萌え紙尺六横) | 吉田秋光 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 狩野探幽特集写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 鍛冶橋家初祖探幽に就て | 狩野探道 |
| 探幽の書と弘法大師座右銘 | 田中親美 |
| 探幽雑談 | 相見香雨 |
| 都返りの茶人と丸龍屏風 | 野田九浦 |
| 探幽の人間的偉さ | 添田達嶺 |
| 江月和尚筆探幽斎号記 | 関如来 |
| 探幽縮図に就て | 添田達嶺 |
| 熱河行を前に | 川端龍子 |
| 野に住みて | 堅山南風 |
| 余技漫語 | 柚木久太 |
| 謝赫の六法の独逸譯 | 青柳正広 |
| 東京美校紛擾事件 | 関如来 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第13巻5号(昭和12年(1937)5月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(初夏絹二尺横) | 田中咄哉州 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(杜若紙尺八横) | 永田春水 |
| 裏表紙絵(百合紙尺五横) | 松本姿水 |
| 口絵原色版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 美術家と文化勲章 | 黒田鵬心 |
| 忍冬文様の考察 | 渡辺素舟 |
| 画房閑話 | 山村耕花 |
| 古典への探究 | 吉田秋光 |
| 滑稽な美術愛好者 | 高沢初風 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 合戦屏風の興味 | 広瀬憙六 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第13巻6号(昭和12年(1937)6月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(けし絹尺八横) | 西村五雲 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(白雲深処紙尺五横) | 小野竹喬 |
| 裏表紙絵(島原所見紙尺五横) | 池田遙邨 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 帝室博物館壁画写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 作風新古 | 金原省吾 |
| 芸術に現れた太陽 | 金井紫雲 |
| 藤原時代の風俗画 | 吉村忠夫 |
| 日本画を描くの弁 | 中川紀元 |
| 洋蘭を描く | 川島理一郞 |
| 鳥と昆蟲の茶話 | 畑耕一 |
| 東美校紛擾事件 | 関如来 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 栗山範修氏の事ども | – |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第13巻7号(昭和12年(1937)7月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(北条時宗 絹二尺横) | 菊池契月 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(千鳥 紙尺八横) | 山本倉丘 |
| 裏表紙絵(野兎 紙尺五横) | 池上秀畝 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 菊池容斎と行誡上人 | 結城素明 |
| 独湛禅師の画蹟 | 西村南岳 |
| 無碍の心境 | 永井久晴 |
| 昨日今日(句信) | 金島桂華 |
| 落合朗風君の想出 | 金井紫雲 |
| 奇骨落合朗風君 | 田中咄哉州 |
| 朗風さんを憶ふ | 川口春波 |
| 主人朗風を偲ぶ | 落合信子 |
| 朗風幼年時代 | 杉山テフ |
| 朗風少年時代の思出 | 落合忠三郞 |
| 落合朗風制作略年表 | – |
| 美人画その他 | 邦枝完二 |
| 時代意識と漢詩 | 古川北華 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第13巻8号(昭和12年(1937)8月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(晩涼飲馬 絹尺八横) | 橋本関雪 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(茄子 紙尺八横) | 永田春水 |
| 裏表紙絵(山辺赤人 絹尺五横) | 板倉星光 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 古北口長城線(スケッチ) | 川端龍子 |
| 承徳喇嘛廟(スケッチ) | 川端龍子 |
| 楠公訣別図(額面) | 荻生天泉 |
| 写生に就て | 西村五雲 |
| 写真と絵画 | 山口蓬春 |
| 風景と樹木 | 矢沢弦月 |
| 花の写生 | 辻永 |
| 熱河行 | 川端龍子 |
| 朝鮮と八瀬大原 | 西沢笛畝 |
| 家を建てる | 榊原紫峰 |
| 文晁と本教及び麓谷 | 添田達嶺 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第13巻9号(昭和12年(1937)9月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵(インコ 絹尺八横) | 山口蓬春 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(湖辺 紙二尺横) | 矢野鉄山 |
| 裏表紙絵(牛 紙尺五横) | 小松均 |
| 口絵原色版 | – |
| 中堅作家特集写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 内蒙の日の出 | 藤島武二 |
| 夏花雑感 | 荒木十畝 |
| 日本美術院の創立 | 関如来 |
| 東西の新人 | 川路柳虹 |
| 新人論 | 下店静市 |
| 慢性有名病毒下し | 筑紫春三郞 |
| 若人点描 | 辻本和一 |
| 北陸ところ[ドコロ] | 金島桂華 |
| 風景と花鳥 | 田中咄哉州 |
| 身辺雑感 | 奥村土牛 |
| 郷土芸術の事など | 酒井三良 |
| 舞踊画の生まれる迄 | 山川秀峰 |
| 花鳥画その他 | 森白甫 |
| 若葉の東海道 | 池田遙邨 |
| 伊勢路の春 | 勝田哲 |
| 雑感 | 吉岡堅二 |
| 新日本画の動向 | 福田豊四郞 |
| わが行く途 | 上村松篁 |
| 人物画を目ざして | 三輪晁勢 |
| この頃の感想 | 三谷十糸子 |
| 山を歩く | 村島酉一 |
| 新らしい絵の立場 | 杉山寧 |
| 雨を待った夏の想出 | 田之口青晃 |
| 師匠の蔭に | 加納三楽 |
| 私の旅 | 加藤栄三 |
| 旅の修養 | 木本大果 |
| 国芳描く(舞踊台木) | 高沢初風 |
| 絵画の永遠性 | 添田達嶺 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 西井敬岳君を憶ふ | 玉舎春輝 |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第13巻10号(昭和12年(1937)10月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(月明 絹二尺横) | 横山大観 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(憩ひ 紙尺八横) | 勝田哲 |
| 裏表紙絵(飛鴨 紙尺八横) | 堅山南風 |
| 口絵原色版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 日高アイヌの家外 | 山村耕花 |
| 日高アイヌ室内 | 山村耕花 |
| 湖上雨後 | 田中咄哉州 |
| 北支那の石仏 | 荒井寬方 |
| アイヌの漆器 | 山村耕花 |
| 山荘漫筆 | 島田墨仙 |
| 釣を楽しむ | 伊東深水 |
| 南風の「朔風」と土牛の「仔馬」 | 神崎憲一 |
| 各新聞の院展・青龍展・明朗展評 | – |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第13巻11号(昭和12年(1937)11月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(豊穣 紙尺八横) | 堂本印象 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(豊秋 紙二尺横) | 横尾翠田 |
| 裏表紙絵(晩秋 絹尺五横) | 三輪晁勢 |
| 口絵原色版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 日本画に於る戦争画 | 松岡映丘 |
| 支那断片 | 小杉放庵 |
| 戦争と絵画 | 広瀬憙六 |
| 文展の日本画に寄す | 川崎克 |
| 各新聞の文展評 | – |
| 好きなこと二三 | 川合玉堂 |
| 支那の古工芸 | 香取秀真 |
| 飛騨の竹籠其の他 | 長野草風 |
| 日本美術院第一回展 | 関如来 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第13巻12号(昭和12年(1937)12月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(深秋 絹尺八横) | 八木岡春山 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(雪山遊鹿) | 飛田周山 |
| 裏表紙絵(鳩) | 岩田正巳 |
| 口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 越後燕背後惣瀑之景 | 堅山南風 |
| 栗子隧道十二景ノ内苅安洞内 | 菅原白龍 |
| 瀧之沢石橋 | 菅原白龍 |
| 栗子隧道東面 | 菅原白龍 |
| 関場籠巌 | 菅原白龍 |
| 跋文 | 菅原白龍 |
| 牛 | 長井雲坪 |
| 虎 | 長井雲坪 |
| ふれ太鼓 | 淡島椿岳 |
| 雪中花鳥図 | 章聲 |
| 雪中花鳥図模写 | 殷元良 |
| 外壕の鳥(真雁と菱喰、カルガモの群、ユリカモメ、鵜、カイツブリ) | – |
| 古鐔二図(刀匠物、甲冑師物) | – |
| 事変と美術雑感 | 内ヶ崎作三郞 |
| 支那文化より観たる時事雑感 | 市村瓚次郞 |
| 本音を聞く | 大智勝観 |
| 若い人達の仕事 | 広島晃甫 |
| 画房断感 | 高木保之助 |
| 外濠の鳥 | 内田清之助 |
| 古鍔の鑑賞に就て | 桑原羊次郞 |
| 栗子隧道献上画冊 | 添田達嶺 |
| 章聲筆雪中花鳥画 | 比嘉朝健 |
| 雲坪の動物画 | 丸山良策 |
| 淡島椿岳のことども | 竹内梅松 |
| 日本美術院第一回展 | 関如来 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | ‐ |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第14巻(昭和13年(1938)1月~12月)
第14巻1号(昭和13年(1938)1月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(渡頭の春紙尺九横) | 川合玉堂 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(虎絹尺八横) | 荒井寬方 |
| 裏表紙絵(航子絹尺八横) | 森白甫 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 梅花書屋 | 広瀬台山 |
| 風雨競渡 | 広瀬台山 |
| 陽明洞 | 広瀬台山 |
| 熱海写生巻ノ内 | 広瀬台山 |
| 琴響画冊 | 広瀬台山 |
| 梅亭遠望 | 広瀬台山 |
| 雨中猛虎図 | 風外禅師 |
| 香積寺 | – |
| 古鐔九図 | – |
| ものゝあはれ断片 | 松岡映丘 |
| 古典と自分 | 川端龍子 |
| 古典と現代 | 中村岳陵 |
| 水虎画人芋銭 | 神崎憲一 |
| 作麼生魯山人 | 神崎憲一 |
| 河童の話その他 | 小川芋銭 |
| 朝鮮遊記 | 山村耕花 |
| 東洋の虎 | 渡辺素舟 |
| 香積禅寺虎物語 | 杉浦冷石 |
| 古鐔の鑑賞に就て | 桑原羊次郞 |
| 広瀬台山 | 広瀬哲士 |
| 広瀬台山の遺墨に就て | 西村南岳 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 北支戦線より(絵と文) | 小早川秋聲 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第14巻2号(昭和13年(1938)2月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(草萌え絹尺五横) | 竹内栖鳳 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(冬山絹尺八横) | 福田豊四郞 |
| 裏表紙絵(竹馬絹尺八横) | 伊東紅雲 |
| 口絵原色版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 十六羅漢図(十六幅ノ内) | 観三法師 |
| 書 | 観三法師 |
| 山水図 | 観三法師 |
| 書 | 観三法師 |
| 水鏡観音図 | 観三法師 |
| 古武装一夕話 | 菊池契月 |
| はやりかぜ | 鏑木清方 |
| 風景を語る | 飛田周山 |
| 工房閑談 | 藤井浩祐 |
| 支那へ支那へ | 藤田嗣治 |
| 大阪より | 青木大乗 |
| 江南の戦線より(絵と文) | 田中案山子 |
| 椿花 | 吉田堯文 |
| 展観よ何処へ行く | 南野菜苦子 |
| 最近の鑑賞界を観る | 豊田豊 |
| 観三法師の墨戯 | 桑原双蛙 |
| 日本書会四十年回顧 | 添田達嶺 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 希望氏作浪曲大楠公 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第14巻3号(昭和13年(1938)3月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(春絹二尺横) | 田中咄哉州 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(椿小禽絹尺八横) | 森守明 |
| 裏表紙絵(鶉、絹尺八横部分) | 山本倉丘 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 山帰来小禽 | 俵屋宗達 |
| 野老飼馬 | 与謝蕪村 |
| 古鐔十二図 | – |
| 武将と美術 | 正木直彦 |
| 戦争と日本画 | 黒田鵬心 |
| 犢を飼った話その他 | 西村五雲 |
| 動物画雑感 | 金井紫雲 |
| 雪中珍客 | 相馬御風 |
| 水墨の永井久晴氏 | 広瀬憙六 |
| 入江波光論 | 横川毅一郞 |
| 古鐔の鑑賞に就て | 桑原羊次郞 |
| 関如来君の思ひ出 | 塩田力蔵 |
| 関如来氏を偲ぶ | 添田達嶺 |
| 関さんが到頭 | 神崎憲一 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展観よ何処へ行く | 南野菜苦子 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第14巻4号(昭和13年(1938)4月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(芽春絹尺八横) | 郷倉千靱 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(梨花絹尺八横) | 松本姿水 |
| 裏表紙絵(踊り部分絹尺五横) | 北野恒富 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 故松岡映丘遺作集 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 故松岡映丘追悼 | – |
| 小野竹喬論 | 横川毅一郞 |
| 展観よ何処へ行く | 南野菜苦子 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 大場鎮にて(絵と文) | 小松均 |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第14巻5号(昭和13年(1938)5月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(遅日絹二尺横) | 堅山南風 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(驟雨紙尺五横) | 水田竹圃 |
| 裏表紙絵(蝦籠絹二尺横) | 橋本静水 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 蒙古行を前に | 川端龍子 |
| 北支行の言葉 | 川島理一郞 |
| 花卉雑稿 | 辻永 |
| 浪を描く | 堅山南風 |
| 制作雑感 | 田中咄哉州 |
| 現画壇の人々と書 | 外狩素心庵 |
| 美術家旧宅の想ひ出 | 添田逹嶺 |
| 小杉放庵論 | 横川毅一郞 |
| 川崎克氏の陶芸画技 | 神崎憲一 |
| 大阪京都陽春画壇譜 | 豊田豊 |
| 関西行 | 広瀬憙六 |
| 展観よ何処へ行く | 南野菜苦子 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第14巻6号(昭和13年(1938)6月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(八仙花絹尺八横) | 山口蓬春 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(青楓若鮎絹尺八横) | 高木保之助 |
| 裏表紙絵(御所人彩絹尺五横) | 西沢笛畝 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 訪録挿絵ノ内四図 | 渡辺崋山 |
| 日本画に就ての断片 | 武者小路実篤 |
| 削去 | 金原省吾 |
| 動画促成の問題 | 塩田力蔵 |
| 宝相華文様の考察 | 渡辺素舟 |
| 酒と野球 | 牧野虎雄 |
| 堂本印象論 | 横川毅一郞 |
| 崋山尽忠報恩の意気 | 杉浦冷石 |
| 清籟書屋余適 | 古川北華 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展観よ何処へ行く | 南野菜苦子 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第14巻7号(昭和13年(1938)7月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(碧山鵠絹尺八横) | 石崎光瑤 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(紫陽花紙尺八横) | 小林観爾 |
| 裏表紙絵(松黄鶺鴒、部分) | 福田翠光 |
| 口絵原色版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 上海戦線スケッチ | 藤島武二 |
| 西湖所見 | 藤島武二 |
| 雲崗石仏寺 | 川端龍子 |
| 琴棋書画之図 | 狩野昌運 |
| 中支戦線雑感 | 藤島武二 |
| 蒙彊雑記 | 川端龍子 |
| 高千穂峰 | 青木大乗 |
| 京都美術俱楽部創立三十周年祝賀茶会記 | 川崎克 |
| 狩野昌運と其遺作 | 添田逹嶺 |
| 田原幽褻以後の崋山 | 杉浦冷石 |
| 清籟書屋余適 | 古川北華 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展観よ何処へ行く | 南野菜苦子 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 小曲女十二姿 | 伊東深水 |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・榊原紫峰・田中咄哉州・安田半圃 |
第14巻8号(昭和13年(1938)8月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(残月絹二尺横) | 小野竹喬 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(ほたる絹尺八横) | 中村貞以 |
| 裏表紙絵(瓜、紙尺八横部分) | 川崎小虎 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 国宝那智瀧図 | 巨勢金岡 |
| 瀧山水図 | 芸阿彌 |
| 春日権現験記絵巻中ノ小袿姿御物(模写) | – |
| 平家納経見返し中ノ物具姿国宝(模写) | – |
| 時局と花鳥画 | 荒木十畝 |
| 能登の旅(絵と句) | 川合玉堂 |
| 初夏の蔦温泉 | 内田清之助 |
| 北京雑記 | 川島理一郞 |
| 水を描く | 中村岳陵 |
| 画室の感想 | 伊東深水 |
| 古名画の女装に就て | 河鰭実英 |
| 東洋芸術と瀑布 | 金井紫雲 |
| 清籟書屋余適 | 古川北華 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・福田平八郞・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第14巻9号(昭和13年(1938)9月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(清夏絹尺八横) | 山本倉丘 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(遊鯉紙尺八横) | 木本大果 |
| 裏表紙絵(茄子) | 土田麦僊 |
| 口絵原色版 | – |
| 肖像画特集写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 肖像画特集 | – |
| 玉堂邸を詠む | 高橋桂二 |
| 素人の絵画観 | 青柳瑞穂 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 渡辺公観君を悼む | 広田百豊 |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・福田平八郞・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第14巻10号(昭和13年(1938)10月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(秋興紙尺七横) | 西山翠嶂 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(湯の宿紙尺六横) | 田中咄哉州 |
| 裏表紙絵(秋果紙尺五横) | 津田青楓 |
| 口絵原色版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 日本美術院第廿五回展評 | – |
| 青龍社第十回記念展評 | – |
| 明朗美術第五回記念展評 | – |
| 時局下の美術雑感 | 結城素明 |
| 龍 | 長野草風 |
| 制作雑記 | 奧村土牛 |
| 深水邸を訪ふ | 高橋桂二 |
| 近頃の感想 | 藤井浩祐 |
| 美術と戦争 | 中川紀元 |
| 新凉小話 | 畑耕一 |
| 独山老師の片鱗 | 木村棲雲 |
| 金島桂華論 | 横川毅一郞 |
| 赤目渓谷(絵と句) | 小野竹喬 |
| 各新聞の院展・青龍展・明朗展評 | – |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 成吉思汗(舞踊台本) | 高沢初風 |
| 西村五雲氏急逝 | 神崎憲一 |
| 森村宜稲氏逝く | 添田逹嶺 |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・福田平八郞・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第14巻11号(昭和13年(1938)11月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(宇津の山絹二尺横) | 松本一洋 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(紅葉双禽絹尺八横) | 山本倉丘 |
| 裏表紙絵(公時絹二尺横部分) | 岩田正巳 |
| 口絵原色版 | – |
| 高原の秋(絹尺八横) | 児玉希望 |
| 口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 第二回文展評 | – |
| 玉堂の作品其他 | 本間久雄 |
| Lion・唐獅子・狛犬考 | 渡辺素舟 |
| 小杉放庵邸を訪ねて | 高橋桂二 |
| 陶器漫語 | 山村耕花 |
| 支那へ行く気持 | 伊東深水 |
| 文展の人形批判と希望 | 西沢笛畝 |
| 画室余語 | 田中咄哉州 |
| 制作雑記 | 高木保之助 |
| 文展前後 | 森白甫 |
| 各新聞の文展評 | – |
| 素人の観た展覧会 | 正宗白鳥 |
| 清籟書屋余適 | 古川北華 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・福田平八郞・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第14巻12号(昭和13年(1938)12月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(冬暖紙二尺横) | 山口華楊 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(山茶花絹尺八横) | 勝田蕉琴 |
| 裏表紙絵(千鳥絹尺二竪部分) | 高木保之助 |
| 口絵原色版 | – |
| 西村五雲遺作集 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 高野山大塔内壁装飾画八図 | 堂本印象 |
| 西村五雲追悼 | – |
| 小室翠雲邸を訪ふ | 高橋桂二 |
| 本年の回顧 | 川端龍子 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 清籟書屋余適 | 古川北華 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・福田平八郞・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第15巻(昭和14年(1939)1月~12月)
第15巻1号(昭和14年(1939)1月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(朝寒絹尺八横) | 川合玉堂 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(朝陽映島絹尺八横) | 矢沢弦月 |
| 裏表紙絵(柚子絹尺五横) | 山村耕花 |
| 口絵原色版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 臥虎 | 西村五雲 |
| 北畠顕家卿像 | 池上秀畝 |
| 松ニ芙蓉ノ図 | 狩野光信 |
| 秋草群鷺図 智積院蔵 | – |
| 明治天皇と美術 | 渡辺幾治郞 |
| 古画の精神 | 溝口禎次郞 |
| 松林桂月邸訪問記 | 高橋桂二 |
| 本統の絵 | 安達謙蔵 |
| 心構へ | 星島二郞 |
| 画家と展覧会 | 新居格 |
| 紫禁城 | 正木直彦 |
| 北京で観た支那画 | 川崎克 |
| 光信を称へる | 沢田牛麿 |
| 小宅二軒家(絵と文) | 三橋武顕 |
| 五雲と云ふ人 | 神崎憲一 |
| 木島桜谷氏を憶ふ | 神崎憲一 |
| 逝ける高田早苗博士 | 添田達嶺 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・福田平八郞・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第15巻2号(昭和14年(1939)2月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(椿絹尺八横) | 山口蓬春 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(春庭紙尺九横) | 根上富治 |
| 裏表紙絵(花籠絹尺二竪) | 津田青楓 |
| 口絵原色版 | – |
| 小川芋銭遺作集 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 三番叟 | 西村五雲 |
| 絵事夜話 | 竹内栖鳳 |
| 雑感 | 藤島武二 |
| 質画 | 荒木十畝 |
| 機上礼讃 | 北村西望 |
| 陶器偶感 | 沢田宗山 |
| フジヤマ(絵と文) | 田中咄哉州 |
| 芋銭翁の手紙 | 斎藤隆三 |
| 珊瑚会時代の小川芋銭さん | 川端龍子 |
| 平民新聞時代の小川芋銭先生 | 添田達嶺 |
| 芋銭先生断面 | 外狩素心人 |
| 追憶 | 酒井三良 |
| 芋銭先生から直接聞いたことの二三 | 池田龍一 |
| 芋銭先生の御手紙 | 沢田竹治郞 |
| 丹波に於ける芋銭翁 | 西山泊雲 |
| 色々の思ひ出 | 未亡人 |
| 父の肖像 | 小川倩葭 |
| 祖父の思ひ出 | 弓削素一 |
| 小川芋銭制作略年表 | – |
| 益田孝翁のこと | 田中親美 |
| 五雲と云ふ人 | 神崎憲一 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 揺れる京都画壇 | 豊田豊 |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・福田平八郞・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第15巻3号(昭和14年(1939)3月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(薫芳図 絹尺八横) | 川端龍子 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(松ニ連雀絹尺八横) | 水上泰生 |
| 裏表紙絵(立雛絹尺八横) | 西沢笛畝 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 厚和所見 | 吉岡堅二 |
| 駱駝 | 福田豊四郞 |
| 日本画の過去と将来 | 長谷川如是閑 |
| 日本画に於ける「自然」 | 本庄可宗 |
| 分類からの抑制 | 塩田力蔵 |
| 寸感 | 佐藤俊子 |
| 肖像画の苦心 | 島田墨仙 |
| 近頃の感想 | 中村岳陵 |
| 画室雑記 | 八木岡春山 |
| えにし | 望月春江 |
| 従軍報告対談会 | 吉岡堅二・福田豊四郞・三輪鄰 |
| 五雲と云ふ人 | 神崎憲一 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 川崎克氏の議会美術問答 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・福田平八郞・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第15巻4号(昭和14年(1939)4月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(薫風絹二尺横) | 小室翠雲 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(ふぢ花紙尺五横) | 池上秀畝 |
| 裏表紙絵(藤屋伊左衛門絹尺八横) | 山川秀峰 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 霊山の北畠顕家卿 | 荻生天泉 |
| 雲海の日の出 | 川島理一郞 |
| 観音山より広東大観 | 川島理一郞 |
| 横井金谷筆四図 | – |
| 古画鑑賞花鳥画に就て | 田中一松 |
| 日本精神と日本画 | 添田達嶺 |
| 線と象徴 | 金原省吾 |
| 日本美術に現れた桜 | 田中一松 |
| 娘の日本画 | 朝倉文夫 |
| 人の問に答ふ | 児玉希望 |
| 広東から帰って | 川島理一郞 |
| 伊豆雑記 | 田中咄哉州 |
| 奥村土牛論 | 広瀬憙六 |
| 近藤浩一路とゴルフ | 邦枝完二 |
| 斧行者法印金谷 | 杉浦冷石 |
| 為恭のことゞも | 竹内梅松 |
| 永平寺宝蔵の書画 | 高橋竹迷 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 長唄現代画聖三部作 | 高沢初風 |
| 伊東紅雲氏逝く | 添田達嶺 |
| 加藤英舟氏の訃 | 神崎憲一 |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・福田平八郞・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第15巻5号(昭和14年(1939)5月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(牡丹 絹二尺横) | 田中咄哉州 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(巣立ち 紙二二横) | 永田春水 |
| 裏表紙絵(和気清麿 絹尺三竪部分) | 小山栄逹 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 飯塚琅玕斎氏製作の花籃五種 | – |
| 蓮花の写生に就て古画鑑賞 | 田中一松 |
| 日本精神と日本画 | 添田逹嶺 |
| 絵画の時代性 | 川路柳虹 |
| 健康なる文化の創造へ | 石井柏亭 |
| 中支行を前に | 川端龍子 |
| 生のまゝに | 小倉遊亀 |
| 画室の中から | 山川秀峰 |
| 竹とその芸術 | 飯塚琅玕斎 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 趣味の人伊東紅雲 | 金井紫雲 |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・福田平八郞・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第15巻6号(昭和14年(1939)6月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(松韻 絹二尺横) | 松林桂月 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(百合花 絹尺八横) | 楳崎朱雀 |
| 裏表紙絵(飛燕 牛折部分) | 八木岡春山 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 肇国創業絵巻 | – |
| 牡丹図 高桐院蔵 | – |
| 牡丹図 知恩院蔵 | – |
| 元賀筆 花籠図 守尾孝蔵氏蔵 | – |
| 毛益筆 葵花麝香猫図 原三溪氏蔵 | – |
| 毛益筆 萱草狗子図 原三溪氏蔵 | – |
| 毛益筆 葵花麝香猫図 団琢磨氏蔵 | – |
| 毛益筆 鳳仙花狗子図 益田太郞氏蔵 | – |
| 山楽筆 牡丹襖絵部分大覚寺蔵 | – |
| 右京進筆 牡丹図 柏倉九左衛門氏蔵 | – |
| 周林筆 蜀葵図 帝室博物館蔵 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 牡丹と葵花古画鑑賞 | 田中一松 |
| 日本芸術に於ける指導精神 | 藤懸静也 |
| 和歌と蒔絵の関係に就いて | 吉野富雄 |
| 水郷写生行 | 斎田素州 |
| 白牡丹を写生して丈山を憶ふ | 小室翠雲 |
| 山を描く | 安井会太郞 |
| 土佐、狩野派の軋轢 | 添田逹嶺 |
| 幽霊画を漁る話 | 畑耕一 |
| 鉄線かづら | 長谷川時雨 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・福田平八郞・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第15巻7号(昭和14年(1939)7月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(瑠璃鶲 絹尺八横) | 金島桂華 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵涼み(絹尺八横) | 勝田哲 |
| 裏表紙絵原色(妓生 紙小品) | 山川秀峰 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 青瓜図 根津嘉一郞氏蔵 | – |
| 群鼠食瓜図 黒田長成侯蔵 | – |
| 玻璃器大豆図 黒田長成侯蔵 | – |
| 筍瓜図 高野山宝珠院蔵 | – |
| 瓜栗鼠図 徳川宗敬伯蔵 | – |
| 青瓜図 近衛文麿公蔵 | – |
| 瓜図 ボストン美術館蔵 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 蔬果画に就て古画鑑賞 | 田中一松 |
| 画壇への希望 | 岡部長景 |
| 画人と歌 | 相馬御風 |
| 緑窓漫語 | 堅山南風 |
| この頃のこと | 徳岡神泉 |
| 絵と心 | 榊原紫峰 |
| 力の芸術 | 伊東深水 |
| 近時随想 | 吉田秋光 |
| 日本画の技法其他 | 杉浦非水 |
| 彫金家の墨戯 | 桑原双蛙 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 夜江先生の作品表装 | 萩原庸禎 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 猪飼嘯谷氏逝く | 神崎憲一 |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・福田平八郞・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第15巻8号(昭和14年(1939)8月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(魚虎 紙尺七横) | 小杉放庵 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(月影 絹尺八横) | 荻生天泉 |
| 裏表紙絵(鮎 絹尺八横) | 横尾翠田 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 蓮蟹図 馬越家蔵 | – |
| 藻魚図 藤堂家旧蔵 | – |
| 伝范安仁筆 穿荇魚蟹図 村山長挙氏蔵 | – |
| 伝苑安仁筆 藻魚図 馬越恭一氏蔵 | – |
| 伝賴菴筆 藻魚図 武藤金太氏蔵 | – |
| 蟹図 清水家蔵 | – |
| 鯉魚図 溝口宗文氏蔵 | – |
| 藻魚図 原三溪氏蔵 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 魚蟹図に就て古画鑑賞 | 田中一松 |
| 茶道より見たる現代画 | 吉田尭文 |
| 中支行あれこれ | 川端龍子 |
| 水三題 | 菊池契月 |
| 京の夏景色 | 上村松園 |
| 蛇籠の記 | 長野草風 |
| 彫金家の墨戯 | 桑原双蛙 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・福田平八郞・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第15巻9号(昭和14年(1939)9月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(城棲月京 絹尺八横) | 竹内栖鳳 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(游狸 絹二尺横) | 田之口青晃 |
| 裏表紙絵(みのる秋 紙円窓) | 酒井三良 |
| 口絵原色版 | – |
| 宮本武蔵特集写真版 | – |
| 随筆写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 宮本武蔵特集 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・福田平八郞・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第15巻10号(昭和14年(1939)10月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(小春日 絹二尺横) | 山村耕花 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(河口 紙二四横) | 前田荻邨 |
| 裏表紙絵(不動尊 絹尺五部分) | 木村武山 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 日本美術院第廿六回展 | – |
| 青龍社第十一回展 | – |
| 明朗美術連盟第六回展 | – |
| 大輪書院第二回展 | – |
| 森守明氏個展 | – |
| 宮崎井南居新作書展 | – |
| 梅軒書廊祇園会展 | – |
| 土井撰美堂祇園会展 | – |
| 白閃社第三回展 | – |
| 福陽美術第十回展 | – |
| 青甲社小品展 | – |
| 丹丘会作品展 | – |
| 樹人社第二回展 | – |
| 歴程美術協会第二回展 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・福田平八郞・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第15巻11号(昭和14年(1939)11月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(蘆叢 絹尺八横) | 児玉希望 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(豊秋 絹尺八横秋) | 山本倉丘 |
| 裏表紙絵(鶏 絹尺八横部分) | 菊沢武江 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 第三回文展 | – |
| 岸浪百艸居氏第二回個展 | – |
| 北斗会第一回展 | – |
| 朗峯書塾第九回展 | – |
| 葱青社第一回展 | – |
| 都筑真琴氏第二回個展 | – |
| 平林清輝氏仏画展 | – |
| 衣笠木荘氏個展 | – |
| 尾関栗庵氏文人画展 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・福田平八郞・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第15巻12号(昭和14年(1939)12月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(千両 絹尺八横) | 中村岳陵 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(湖畔紙二二横) | 筆谷等観 |
| 裏表紙絵(上海画信) | 伊東深水・酒井三良 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| カット | 小室翠雲・池上秀畝・福田平八郞・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第16巻(昭和15年(1940)1月~12月)
第16巻1号(昭和15年(1940)1月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(雪暁絹尺八横) | 川合玉堂 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(鶺鴒紙小品) | 田中咄哉州 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 支那旅行絵と文 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 皇紀二千六百年を迎へて | 正木直彦 |
| 「龍」その他 | 川端龍子 |
| 東洋の龍 | 渡辺素舟 |
| 青邨氏の舞台美術 | 高沢初風 |
| 幽玄に就いて | 金原省吾 |
| 蒔絵瑣談 | 竹内梅松 |
| 冬の大同行 | 川島理一郞 |
| 大陸行(俳句) | 酒井三良 |
| 蘇州の秋 | 上村松篁 |
| 戦後の支那の人達 | 三輪晁勢 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・田中咄哉州・安田半圃 |
第16巻2号(昭和15年(1940)2月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(早春絹二尺横) | 川端龍子 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(木瓜小禽絹二尺横) | 西村卓三 |
| 口絵原色版 | – |
| 村上華岳遺作集 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 村上華岳追悼 | – |
| 村上華岳画仙を憶ふ | 西田天香 |
| 片影の一二 | 入江波光 |
| 交友四十年 | 榊原紫峰 |
| 村上君を偲ぶ | 小野竹喬 |
| 華岳氏の人と芸術との宿命的な繋りに就て | 神崎憲一 |
| 華岳の家系その他 | 佳子未亡人 |
| 村上華岳語録(遺稿) | – |
| 玉堂氏の言葉 | 三輪鄰 |
| 剛毅樸訥の風尚を望む | 塩田力蔵 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 邨田丹陵氏逝く | 添田達嶺 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第16巻3号(昭和15年(1940)3月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(いちご 絹二尺横) | 山口蓬春 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(紅梅 絹二尺横) | 岩田正巳 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 芋銭遺作展写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 日本画と日本人の生活様式 | 鼓常良 |
| 日本画と現代知覚 | 川路柳虹 |
| 鶏を描く | 田中咄哉州 |
| 個展の前に | 郷倉千靱 |
| 画室偶感 | 横尾翠田 |
| 番茶坐談 | 畑耕一 |
| 伊東深水 山川秀峰対談会 | – |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 竹田山中人饒舌講義 | 杉原夷山 |
| 正木直彦先生薨去 | 添田達嶺 |
| 田中頼璋氏逝く | 添田達嶺 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第16巻4号(昭和15年(1940)4月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(菖蒲 絹二尺横) | 畠山錦成 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(春林 絹八尺横) | 小野竹喬 |
| 口絵原色版 | – |
| 南支那行絵と文 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 心と形 | 田中親美 |
| 形似と生動 | 森口多里 |
| 奉祝展その他 | 藤島武二 |
| 北満行を前に | 川端龍子 |
| 絵と私 | 井上正夫 |
| 浅春雑話 | 三好達治 |
| 正木直彦先生を悼む | 川合玉堂 |
| 正木校長の憶ひ出 | 朝倉文夫 |
| 正木先生の想ひ出 | 津田信夫 |
| 正木先生と日本美術の海外進出 | 黒田鵬心 |
| 正木先生と岡倉先生 | 塩田力蔵 |
| 明治大正美術史と正木直彦先生 | 添田達嶺 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第16巻5号(昭和15年(1940)5月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(梨花小禽 絹尺八横) | 杉山寧 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵絹(勝鬨 尺八横) | 長野草風 |
| 口絵原色版 | – |
| 大観個展全出品 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 大観画伯の奉祝記念展に際して | 松浦鎮次郞 |
| 大観と云ふ人 | 細川護立 |
| 大観画伯のこと | 岡部長景 |
| 大観君の気魄 | 市村瓚次郞 |
| 大観君の芸術 | 溝口宗文 |
| 大観の近業 | 脇本楽之軒 |
| 先覚者的主張の国士的実践 | 神崎憲一 |
| 惜春賦(俳句) | 川合玉堂 |
| 大観先生を繞る思出 | 堅山南風 |
| 正木直彦翁追憶 | 桑原双蛙 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第16巻6号(昭和15年(1940)6月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(泰山木 紙二五横) | 児玉希望 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(五位鷺 紙二二横) | 根上富治 |
| 口絵原色版 | – |
| 五雲遺作展出品 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 大陸の自然と日本の自然 | 大智勝観 |
| 身辺雑記 | 山口蓬春 |
| 水墨余滴 | 近藤浩一路 |
| 画室随想 | 山本倉丘 |
| 潮来にて(俳句) | 小野竹喬 |
| 五雲画伯の仕事 | 川路柳虹 |
| 五雲遺作展所感 | 金井紫雲 |
| 五雲芸術のいのち | 豊田豊 |
| 先生の遺作展に際して | 山口華楊 |
| 遺作展風景 | – |
| 神武天皇の御尊像と竹内久一翁 | 添田逹嶺 |
| 新聞美術記者今昔噺 | 田沢田軒 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第16巻7号(昭和15年(1940)7月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(朝 絹二尺横) | 徳岡神泉 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(蔬菜 絹二尺横) | 白倉二峰 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 四天王寺壁画の制作 | 堂本印象 |
| 中ノ沢温泉(絵と文) | 堅山南風 |
| 北満の旅と新京美術院 | 川端龍子 |
| 北支点描(俳句) | 川端龍子 |
| 制作随想 | 八木岡春山 |
| 「何」を描く | 式場隆三郞 |
| 法衣に包んだ鑿 | 相馬御風 |
| 尾形乾山の人と芸術 | 添田逹嶺 |
| 現代日本画に於ける新しきものと古きもの | 神崎憲一 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 青邨清方舞台装置 | 高沢初風 |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第16巻8号(昭和15年(1940)8月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(含墨魚 紙尺八横) | 金島桂華 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(飛泉 絹尺八横) | 中野草雲 |
| 口絵原色版 | – |
| 映丘遺作展出品 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 美術界近時雑感 | 荒木十畝 |
| 日本画に於ける個性の問題 | 岡崎義恵 |
| 身辺雑記 | 中村岳陵 |
| 海荘清韻(漢詩) | 小室翠雲 |
| 映丘遺作展を観て | 川合玉堂 |
| 遺業追懐 | 鏑木清方 |
| 松岡映丘氏の芸術 | 添田逹嶺 |
| 遺作展による映丘の再生 | 豊田豊 |
| 恩師遺作展の記 | 吉村忠夫 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第16巻9号(昭和15年(1940)9月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(くさむら 絹二尺横) | 吉岡堅二 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(桔梗 絹尺八横) | 森戸国次 |
| 口絵原色版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 時局と美術 | 川崎克 |
| 日本文化の独創性 | 保田与重郞 |
| 軽井沢療養(句と歌) | 島田墨仙 |
| 俵屋宗逹の墓(絵と文) | 田中咄哉州 |
| 天人考 | 渡辺素舟 |
| 柴田是真翁の事ども | 添田逹嶺 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 笛畝氏の舞台装置 | – |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第16巻10号(昭和15年(1940)10月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(栗鼠 絹二尺横) | 加藤栄三 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(葡萄栗鼠 紙二一横) | 板倉星光 |
| 口絵原色版 | – |
| 古画写真版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 日本美術院第廿七回展 | – |
| 青龍社第十二回展 | – |
| 大輪画院第二回展 | – |
| 明朗美術第七回展 | – |
| 関尚美堂新作画展 | – |
| 辰巳吉次氏主催新作画展 | – |
| 佐藤梅軒東西大家新作画展 | – |
| 土井撰美堂祗園会展 | – |
| 蒼穹会第二回展 | – |
| 扶桑会第三回展 | – |
| 波光・竹喬・紫峰三氏新作展 | – |
| 堅山南風氏新作展 | – |
| 浜倉清光氏第一回個展 | – |
| 古城江観氏スケッチ展 | – |
| 最島社小品展 | – |
| 満洲国美術第三回展 | – |
| 矢野鉄山塾展 | – |
| 新虹会第三回展 | – |
| 聖徳太子御像に就て | 田中一松 |
| 美術を愛する心と国民の品格 | – |
| 美術愛の日独交流 | 丸尾彰三郞 |
| 在野展総評 | 鈴木進 |
| 日本美術院廿七回展 | 神崎憲一 |
| 青龍社第十二回展 | 神崎憲一 |
| 明朗美術第十回展 | 豊田豊 |
| 大輪画院第三回展 | 豊田豊 |
| 体質と年齡 | 伊東深水 |
| 夢・軍鶏の子 | 児玉希望 |
| 床の間 | 青木大乗 |
| 松園女史のこと | 谷口富美枝 |
| 渡辺崋山百年記念展 | 添田逹嶺 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第16巻11号(昭和15年(1940)11月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(草相撲 紙尺九横) | 竹内栖鳳 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(するめ 扇面) | 竹内栖鳳 |
| 竹内栖鳳原色作品集 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 一生一硯 | 竹内栖鳳 |
| 喜寿の栖鳳画伯 | 松本亦太郞 |
| 栖鳳先生のこと | 大谷句仏 |
| 栖鳳翁喜寿賦呈(漢詩) | 外狩素心庵 |
| 栖鳳の瑞 | 田中倉琅子 |
| 喜寿にしてこの鍈気 | 北大路魯卿 |
| 珍什の二作品に就て | 柴田源七 |
| 人間栖鳳 | 村松梢風 |
| 栖鳳師四姿(俳句) | 大谷句仏 |
| 塾に於ける先生 | 西山翠嶂 |
| 栖鳳七十七話 | 神崎憲一 |
| 教へられる数々 | 松本幸四郞 |
| 写生の熱製作の気合 | 柴田定吉 |
| 柱の蝉その他 | 伏原利造 |
| 献寿(長唄) | 加茂川酔歩 |
| 栖鳳先生あれこれ | 中西嘉助 |
| 画壇の三長老を語る | 添田達嶺 |
| 霊巌山(絵と文) | 安田半圃 |
| 身辺雑感 | 矢野橋村 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第16巻12号(昭和15年(1940)12月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(彩雨) | 川合玉堂 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(三番叟) | 橋本永邦 |
| 口絵原色版 | – |
| 日本画の表現 | 金原省吾 |
| 建仁寺の襖絵に就て | 橋本関雪 |
| 奉祝展雑感 | 清水澄 |
| 時局と奉祝展 | 岡部長景 |
| 奉祝展に寄す | 川崎克 |
| 「彩雨」と「一葉」 | 本間久雄 |
| 奉祝展を観る | 喜多壮一郞 |
| 奉祝展日本画総評 | 鈴木進 |
| 奉祝展第一部所感 | 神崎憲一 |
| 北京再遊 | 梅原龍三郞 |
| 鹿を語る | 内田清之助 |
| 制作余語 | 田中咄哉州 |
| 洋服の弁 | 山川秀峰 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第17巻(昭和16年(1941)1月~12月)
第17巻1号(昭和16年(1941)1月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(雲且 絹二尺横) | 郷倉千靱 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(漁村曙 紙尺八横) | 池上秀畝 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 渡辺崋山作品集 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 本文挿入写真版 | – |
| 湯原閑談 | 竹内栖鳳 |
| 第廿七世紀の年頭に | 川端龍子 |
| 芸術に現はれた蛇 | 金井紫雲 |
| 崋山先生の人物画と肖像画とを辿る | 外狩素心庵 |
| 晩年の華山先生 | 大口喜六 |
| 全楽堂遣墨浅説 | 相見香雨 |
| 渡辺崋山と蛮社の獄 | 森銑三 |
| 崋山覚書 | 菅沼貞三 |
| 崋山先生の傑作 | 鈴木進 |
| 崋山の俳画観 | 杉浦冷石 |
| 崋山百年展出陳目録 | – |
| 展覧会批評 | – |
| 美術新体制の提案 | 横山大観 |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第17巻2号(昭和16年(1941)2月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(桃花水□ 絹二尺横) | 松林桂月 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(雪竹宿禽 絹尺八横) | 白倉嘉入 |
| 口絵原色版 | – |
| 正倉院御物特集 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 本文挿入写真版 | – |
| 正倉院御物に就て | 溝口禎次郞 |
| 天平の絵ごころ | 秋山光夫 |
| 鳥毛立女屏風(遣稿) | 大村西崖 |
| 正倉院御物と現代 | 深水正策 |
| 正倉院御物拝観余滴 | 遠山孝 |
| 正倉院拝観の記 | 鈴木進 |
| 正倉院御物螺鈿木画 | 木内省古 |
| 木内家三代の芸術 | 添田達嶺 |
| 雑感 | 藤島武二 |
| 鱗光園 | 伊東深水 |
| 東洋画の骨法用筆 | 添田達嶺 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第17巻3号(昭和16年(1941)3月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(春寒 絹二尺横) | 山口華楊 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(浅春 絹二尺横) | 勝田蕉琴 |
| 口絵原色版 | – |
| 法隆寺壁画特集 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 楠の若枝 | 荻生天泉 |
| 日柳燕石像 | 板倉星光 |
| 本文挿入写真版 | – |
| 法隆寺壁画の主題に就て | 福井利吉郞 |
| 法隆寺金堂壁画の様式的年代 | 金原省吾 |
| 鴉一羽(絵と句) | 川合玉堂 |
| 雪の花(絵と文) | 田中咄哉州 |
| 私の古画スケッチ | 広瀬熹六 |
| 法隆寺金堂壁画解説 | 田中一松 |
| 法隆寺壁画の保存 | 添田達嶺 |
| 壁画模写に当りて | 中村岳陵 |
| 法隆寺壁画閑話 | 荒井寬方 |
| 模写の大任を拝して | 橋本明治 |
| 壁画模写の感銘 | 吉岡堅二 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第17巻4号(昭和16年(1941)4月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(双鳩 紙二二横) | 前田青邨 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(惜春 絹尺八横) | 中村大三郞 |
| 富岡鉄斎筆十二賢哲像特集 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 本文挿入写真版小学校教科書挿絵三図 | – |
| 絵画の倫理性 | 金原省吾 |
| 鉄斎筆賢哲像の示唆 | 外狩素心庵 |
| 鉄斎先生の人と芸術 | 正宗得三郞 |
| 鉄斎翁近世賢哲像とその思想的関連 | 横川毅一郞 |
| 近世賢哲像雑感 | 浅野晃 |
| 売茶翁のことゞも | 森銑三 |
| 十二賢哲像と国民学校教科書の挿絵 | 深水正策 |
| 読書生としての自負 | 神崎憲一 |
| 南画と鉄斎の芸術 | 添田達嶺 |
| 清方ゑがく(清元) | 高沢初風 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第17巻5号(昭和16年(1941)5月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(清凉 絹二尺横) | 小室翠雲 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(笹小禽 絹尺八横) | 奧田元宋 |
| 口絵原色版・口絵写真版 | – |
| 田崎草雲特集 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 草雲先生の遺徳 | 小室翠雲 |
| 草雲先生の芸術 | 添田達嶺 |
| 人間草雲 | 河野桐谷 |
| 田崎草雲略年譜 | – |
| 草雲遺墨展出陳目録 | – |
| 肖像画 | 鏑木清方 |
| タイ国の印象 | 川島理一郞 |
| 柴田是真旧蔵十六羅漢の行方 | 桑原双蛙 |
| 日本画について | 青柳瑞穂 |
| 文事奇考三つ | 畑耕一 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第17巻6号(昭和16年(1941)6月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(芍藥 絹尺八横) | 山口蓬春 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(八仙花 絹尺八横) | 三輪晁勢 |
| 口絵原色版 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 布袋図 | 宮本二天 |
| 山水図巻(部分) | 矢野三郞兵衛 |
| 馬形考 | 渡辺素舟 |
| 朝鮮金剛山中(絵と句) | 田中咄哉州 |
| 宮本二天の画蹟と其師矢野三郞兵衛 | 甲木道雄 |
| 花と山水 | 呉茂一 |
| 随想、炭切り | 吉田尭文 |
| 初夏襍想 | 福田豊四郞 |
| 回顧二十五年 | 関長次郞 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| 松園女史の会員補任 | – |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |
第17巻7号(昭和16年(1941)7月)
| タイトル | 著者 |
| 表紙絵原色(巣鳥 絹二尺横) | 田中咄哉州 |
| 題字 | 横山大観 |
| 扉絵(茄子小禽 紙尺八横) | 森守明 |
| 口絵原色版 | – |
| 古画屏風特集 | – |
| 彩管報国三展 | – |
| 展覧会出品写真版 | – |
| 現代画界に於ける古画の検討 | 藤懸静也 |
| 古典研究の意義 | 木村素衛 |
| 屏風絵の史的鑑賞 | 秋山光夫 |
| 二連作を見直して | 川端龍子 |
| 「画心応召」と其画業 | 広瀬憙六 |
| 時局と美術 | 上田俊次 |
| 「龍子応召画」「海軍献納画」「共同製作」 | 神崎憲一 |
| 牡丹雑記 | 石崎光瑤 |
| 画境 | 中川紀元 |
| 展覧会批評 | – |
| 画壇鳥瞰 | – |
| カット | 小室翠雲・榊原紫峰・田中咄哉州 |