日本画家・鏑木清方は“口絵の黄金時代”を代表する画家として武内桂舟、水野年方とともに富岡永洗の名を挙げた。特に永洗については「あの時分に、もし口絵の人気投票があったとしたら、その高点を得るものは、恐らく富岡永洗であったろう。」と書いている。今回は富岡永洗について、都新聞の追悼記事と弟子・桐谷洗麟の著述を中心に紹介する。
スポンサードリンク
目次
生い立ち
富岡永洗は元治元年(1864)3月に長野県埴科郡松代町御安に松代藩士・富岡判六の三兄弟の次男として生まれる(長兄は幼くして亡くなり実質長男)。本名・秀太郎。父の判六は藩の画家・酒井雪谷に絵を学び、「奇雪」と号した画家だった。
幼い永洗は父から絵の手ほどきを受ける。5、6歳の頃から紙を与えられると人物の顔を描いていた。障子や襖にほぼ隙間なく描き散らして、何度貼り替えてもたちまち真っ黒になるほど絵に夢中な少年だった。
明治11年(1878)父母に伴われて初めて上京したが、翌年の暮れに父と死別。若干14、15歳で父の跡を継いで陸軍参謀本部地図科へ出仕して一家を支えた。幼い頃より絵に親しんできたが、体系的な絵の教育を受けてこなかった永洗。それにもかかわらず、仕事の覚えが早く、普通は一年を経ても習得が難しいことをわずか三か月で習熟。大の大人も及ばないほどの出来に同科の人々は「この少年は必ず将来名を挙げる」と感服したという。
小林永濯に入門

富岡永洗
明治13年(1880)(または明治16年ともいわれる)に小林永濯に入門。平日の仕事は続けていたため、土曜の夜から日曜に掛けて師のもとに通い、平日は仕事を終えた後に夜遅くまで筆を執って自ら研究していた。当時、永洗は四谷に住んでおり、永濯の住まいは向島にあった。二里以上(約8km)の道のりを土曜夕方から師のもとに向かい、向島に住む親戚の家に一泊。翌朝早く起きて薄暮れまで教えを受け、夜に自宅に帰っていた。
大雨大雪でも毎週欠かさず師のもとに通い、明治18年(1885)頃には一門の弟子をしのぐほど上達。師の永濯は絵のことはもちろん、その他のことまで何かと世話をし、永洗を我が子のように扱った。そんなある日、永洗の母が永濯の家を訪問。さまざまなことを相談するなかで「息子が将来、画家として成功できるかどうか」を永洗の母がたずねた。永濯は笑って「それは私が保証する。ぼた餅ほどの印を捺して保証するから安心なさい」と答え、永洗の母は喜んで帰宅したという。永濯が永洗の将来にどれだけ期待を寄せていたかがわかる。

小林永濯
展覧会初出品、師との別れ
永洗が初めて自分の絵を公にしたのは、明治19年(1886)4月に東京上野公園で行われた東洋絵画共進会だった。目録によると、号・永洗、富岡秀太郎の名で「張良黄石公」「蝦蟇仙人」を出品している。このときも息子の技量を心配した永洗の母は小林永濯に「先生大丈夫ですか」と何度も念を押していたが、永濯は「私に任せておいてください」と出品させていた。
永洗の出品作はたちまち世間の注意を惹き、その名を知られるとともに「蝦蟇仙人」は陳列後すぐに売約済みとなった。会が終わると永濯は永洗の母に向かって「どうだ私の眼鏡は違わないだろう、私もいい弟子を持っておかげで鼻が高い」と言って喜んだといわれる。
その後も永洗は参謀本部の仕事を続けながら永濯の版下絵の補助などをしていたが、明治23年(1890)5月27日に小林永濯は48歳で亡くなってしまう。永洗は公私ともにお世話になった師匠の恩に報いるため、永濯の十三回忌の際には兄弟弟子たちと協力して亀戸天神内に顕彰碑「鮮斎永濯碑銘」を建立している。
挿絵の世界へ
以前から絵師としての独立を考えていた永洗は、改進新聞社から挿絵の依頼が来ると陸軍参謀本部に辞職を申し出る。今辞められたら困ると簡単には聞き届けられなかったが、弟の大病を理由にようやく辞職(弟はこの後すぐに亡くなる)。こうして明治23年10月から改進新聞社で挿絵を描くようになった。
明治25年(1892)1月からは都新聞へ移籍。明治27年には、村井玄斎が日清戦争を当て込んで書いた「朝鮮征伐」(後に「鎧の風」に改題)、渡辺乙羽の「人鬼」(後に「鬼仏」に改題)の新聞挿絵を描いて好評を博す。当時の挿絵の大家であった武内桂舟と肩を並べるばかりか、髪型や衣服の模様から顔かたちまで流行の模範として社会に影響を及ぼした。特に妖艶な美人画は喜多川歌麿以来ともいわれた。
永洗が挿絵を描くと描かないとでは新聞の売れ行きが大きく違ったという人気ぶりを出版社が放っておくわけがない。明治20年代から30年代にかけて、博文館・金港堂といった出版社から発行される単行本小説や雑誌の挿絵・木版口絵を数多く手がけている。
※1:法学政治学研究科附属近代日本法政史料センター(明治新聞雑誌文庫)所蔵
[amazonjs asin=”4892536342″ locale=”JP” title=”富岡永洗口絵集”]日本画画壇への参画
永洗は前述した東洋絵画共進会より後、藻斎永洗の号を名乗る。新聞挿絵と並行して挿絵・木版口絵を手がける一方、展覧会出品からは離れていた。しかし明治31年(1898)に日本画会が興ると、永洗は創立委員および評議員に選ばれた。
上野で開催された第一回展覧会には、大作「井筒女之助」を出品。村上浪六の同名小説の主人公を描いた。挿絵で名前を知られた永洗の肉筆とあって、普段は展覧会に行かない人々も展示に訪れ、絵を前に恍惚としていた者が多かったといわれる。一方で「技巧に囚はれたとか色彩が何うとか」浮世絵系の作という差別的な目で「画品が卑しい」といった批評もあった。その後に日本画会を脱会した永洗は、日本美術院の特別賛助員となって積極的に日本画を出品し、受賞を重ねた。
| 出品年 | 出品展覧会 | 出品作 |
| 明治19年(1886) | 東洋絵画共進会 | 「張良黄石公」 「蝦蟇仙人」 |
| 明治31年(1898) | 第一回内国絵画共進会 | 「井筒女之助」 |
| 明治31年(1898) | 第五回日本絵画協会第一回日本美術院連合絵画共進会 | 「今様美人」(一等褒状受賞) |
| 明治32年(1899) | 第七回日本絵画協会第二回日本美術院連合絵画共進会 | 「秋雨」(銀牌受賞) 「双美春装」 「美人」 |
| 明治33年(1900) | 第八回日本絵画協会第三回日本美術院連合絵画共進会 | 「新内」 「落葉」 「春暁」 |
| 明治33年(1900) | 第九回日本絵画協会第四回日本美術院連合絵画共進会 | 「蓬莱」 |
| 明治34年(1901) | 第十回日本絵画協会第五回日本美術院連合絵画共進会 | 「美人(娼妓)」(銀章受賞) 「美人(姉妹)」 |
| 明治34年(1901) | 第十一回日本絵画協会第六回日本美術院連合絵画共進会 | 「加藤清正」(銀牌受賞) 「嫦娥」 |
| 明治35年(1902) | 第十三回日本絵画協会第八回日本美術院連合絵画共進会 | 「浴後美人」 「雄快」 |
| 明治36年(1903) | 第五回内国勧業博覧会 | 「六歌仙」(三等賞受賞) |
※2:福富太郎コレクション資料室蔵
※3:展覧会出品作と同名の別作品
病との闘い
明治36年(1903)1月から、永洗は大阪開催の第五回内国勧業博覧会出品作の制作を開始。日中は騒々しく夜間は静かなので集中できるとして、日中に寝て夕方から起き出し、肌を刺す寒さのなか徹夜の制作作業を繰り返した。すると翌月に風邪で臥せってしまい、4月に入ると病状が悪化。病名は当時の不治の病、肺結核であった。病を押して出品作「六歌仙」をどうにか完成させると、同作は三等賞を受賞した。
病中にあっても筆を執っているあいだは健康な人と何ら変わらなかった。来客があれば熱があっても普段と変わらない様子で話していたため、傍目には病人には見えなかったという。たしなんでいたお酒は病後に一切断つなど、回復への望みも捨てていなかった。
病気を理由に美術界の動きに乗り遅れるのを良しとしなかった永洗。弟子を展覧会に行かせて様子を報告させたり、近所に住んでいた日本画家・寺崎広業に自作を持って来させて批評をしたりするのを楽しみとしていた。ところが、無理を押して明治38年(1905)6月15日に上野で行われた二葉会の展覧会に出かけ、帰宅後に弟子たちに批評を説き聞かせたのが展覧会の見納めとなってしまう。
悲しき遺言
明治38年(1905)8月3日、朝から頭痛がすると病床に横たわり、筆を執って何か文字を書いていた永洗。午後3時頃に「目が見えない」と言ったのを最後に、目を開けることなく午後5時に永眠。41歳という若さだった。
年来の画家仲間であった鈴木華邨・寺崎広業が同月5日に揮毫会を開き、その収入を永洗に病気見舞いとして贈ろうとしていた矢先の出来事だった。訃報を知った二人は永洗宅に駆けつけ、涙ながらに通夜が行われた。生前に永洗から筆を注文されていた製筆の名人・宮内徳応も訃報に驚き、完成していた筆を霊前に供えていった。
永洗が最期に病床で書いていた遺言状には、かねてより計画していた画会「藻斎会」その他のことが記されていた。なかでも寺崎広業・鈴木華邨・野村文挙・水野年方の名を挙げて、後のことはすべてこれらの人々と相談して、指揮に従うよう書き残している。指名された画家仲間のなかには名前の頭文字だけを記すに止まったものもあった。遺言状を見た人々は涙が出るのを抑えることができなかったという。
永洗には実母、妻と4人の子どもがいた(※4)が、遺言状は絵画に関することばかりで家族のことまでは書かれていなかった。一家より絵画を優先した永洗の遺言状は、会葬者のさらなる悲しみを誘った。
※4:子どもを4人とする典拠は『都新聞』の「永洗画伯逸事」。掲載した家族写真は明治34年当時のもの。子どもが3人映っているが、その後にもう1人生まれたと思われる。
逸話
江戸っ子肌
永洗は信州長野出身であるため「江戸っ子」ではなかったが、友情に厚く、困った人を見ると進んで助けに入る、細かいことは気にしないなど、いわゆる「江戸っ子肌」の一面があったと周りから言われている。名前を知られていない友人や弟子たちを他に紹介して引き立てるのを最も好んでいた。
性格は穏やかで交流範囲が広く、日本美術院で岡倉天心に目をかけられる一方、展覧会を遠ざけ孤高の立場となった渡辺省亭に「若いが気合のいゝ男だ」と気に入られるほどだった。顔の広さは師の小林永濯の顕彰碑建立時に協力者集めで生かされることとなる。
また家に出入りする植木屋などに対しても何ら上下の区別を設けず親切に接した。弟子に対しても同様で、前述した「六歌仙」制作時には草稿の批評を求め、弟子の言葉を聞いて訂正することもあったという。弟子への教育に際しては、人となりが悪い者はたちまち退けられたが、将来見込みのある者に対しては絵に限らず生計その他のことまで助力を惜しまなかった。これは師の小林永濯が永洗含めた弟子に接していた姿勢と重なる。
永洗の弟子、小林洗美が永洗の葬儀の際、「生等の先生に於けるは師にして且つ父の如し」と弔辞(祭文)を読んだのは、弟子一同を代表する思いそのものだった。
九代市川團十郎の大ファン
永洗は歌舞伎鑑賞を好み、特に「劇聖」と呼ばれた九代市川團十郎を大の贔屓にしていた。母親や寺崎広業・鈴木華邨・尾形月耕ら画家仲間とともに観覧し、病気を患う前は「団菊」と呼ばれた九代團十郎と五代尾上菊五郎の芝居を見逃すことはなかったという。「団菊」が永洗の家に訪れるほど交流も深かった。前掲の展覧会出品作「加藤清正」は、團十郎の演目「地震加藤」を見て感動したことをきっかけに描き、清正が手に持つ薙刀の紋様も團十郎に質問して考えたとされる。
実際には、講和交渉による段階的な軍縮と明国の勅使を迎える要員として清正は呼び戻されたと考えられており、日本に帰国した理由が異なる。さらに清正は「秀吉様や我々は皆無事である。伏見に我々の屋敷がないのは幸運だった。」旨の書状を書き残しており、秀吉の安否を気遣っていたものの、秀吉のもとに一番に駆けつけたとは考えにくいとされている。
團十郎と紋様の話としてもうひとつ。團十郎に縁の深い三升格子・弁慶格子、あるいは市松格子の柄を永洗も好んで使った。使い方も徹底しており、浴衣・手ぬぐい・提灯・羽織の裏・下着・襦袢の袖など永洗自身で使うものはもちろん、新聞挿絵の服装に最も使用したのも格子柄だった。
マネたのは服装ばかりではない。お酒の席で酔い心地になると、永洗は團十郎の顔つきや身振り声色をマネて、よく座をにぎわせた。下村観山と紀州和歌山へ旅行したときにも、土地の名士に呼ばれた歓迎会の席で團十郎のモノマネを披露。しかし座にいた芸者は團十郎を知らず、「成田屋!」の掛け声どころか、不思議そうに永洗の顔を見るばかり。しまいには「あなたは苦しそうな声が出るから切腹などはうまいだろう」などと言われ、《スベり倒し》てしまった。その後、友人たちと酒をともにすると「かくの如く不覚を取りたる事なし」と頭をかきながら話すのであった。
母思い
早くに父親を亡くした永洗は母親孝行でも知られた。芝居や珍しい興行があると母親を伴って観覧に出かけた。近所の者は人力車に永洗と母親が乗っているのを見ると「また芝居か」と噂されるほどだったという。朝夕起臥のときには母親に身体の具合をうかがい、外出したときには必ず土産物を携えて帰宅し、母親が喜ぶ姿を見るのを自身の喜びとした。
永洗自身が死に直面したときでさえ、母に心配をさせまいとふるまった様子を弟子の桐谷洗麟が書き残している。
不治の病を得られた当時、老母が居られて、大変心配された為めに、亡くなる半月程前にも、それを非常に心配されて態と室内を手を振つておどつて歩いて見せて、是れくらゐだから確かに癒ると言つて母に安心を与えられたことや、其の芸術の非常に進んだものであつたこと、又門人も沢山あつたことなどを考へて、もう少し長命をして居られたならばと何時も私は思ふのである。
-「富岡永洗先生の芸術」より
まとめ
「永洗の美人画の艶色は歌麿以来」と美人画家として評価されながらも、それに安住することはなかった富岡永洗。席画会(依頼に応じて即興絵を描く会)が流行し出すと、家族を集めて希望の画題を出させて、画題に適したものを即興で描く研究を重ねた。特に挿絵や口絵で描く機会が少ない花鳥山水には苦心していたという。
前半生は挿絵や口絵を中心に活動していたこと、そして早世したことにより現代に残った日本画の作品数が多くないことが、鑑賞機会や名前を知る機会を減らしているように思える(春画「八雲の契り」の作例も残されているが、公の場での鑑賞機会がほとんどないのは前述同様)。
桐谷洗麟も書いているようにもう少し長生きであったなら、日本画の大作を数多く残す名の知られた画家となっていただろう。美人画の名手として知る人ぞ知る画家に留まっているが、最後はあえて美人画以外の作例をいくつか紹介してこの記事の締めとしたい。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
よろしければ応援クリックをお願いします!
![]()
にほんブログ村
参考資料
『生誕450年記念展「加藤清正」』「加藤清正の実像」大浪和弥(2011)
『明治期美術展覧会出品目録』(1994)
『芸術新潮』1994年3月号「福富太郎のアートキャバレー」(1994)
『都新聞史』土方正巳(1991)
『日本美術院百年史』第2巻(1990)
『松代町史 下巻』「第六編 人物史」(1986)
『水巴全集(上)』渡邊水巴(1984)
『こしかたの記』鏑木清方(1961)
『美術之日本』12巻5~7号 大正9年5月~7月「富岡永洗先生の芸術」桐谷洗麟(1920)
『都新聞』「永洗画伯逸事」明治38年8月5、6、8、9、10、12、13、15日(1905)
『第五回内国勧業博覧会審査報告 第9,10部』(1904)
『第五回内国勧業博覧会美術出品目録』(1903)
『日本美術』第35号 明治34年12月(1901)
『日本美術』第34号 明治34年11月(1901)
『新小説』第6年第1巻 明治34年1月(1901)
『少年世界』第4年第5号 明治31年2月(1898)
『絵画叢誌』第49号(1891)
『東洋絵画共進会出品目録』(1886)
[amazonjs asin=”4892536342″ locale=”JP” title=”富岡永洗口絵集”]
[amazonjs asin=”4892536067″ locale=”JP” title=”木版口絵総覧”]















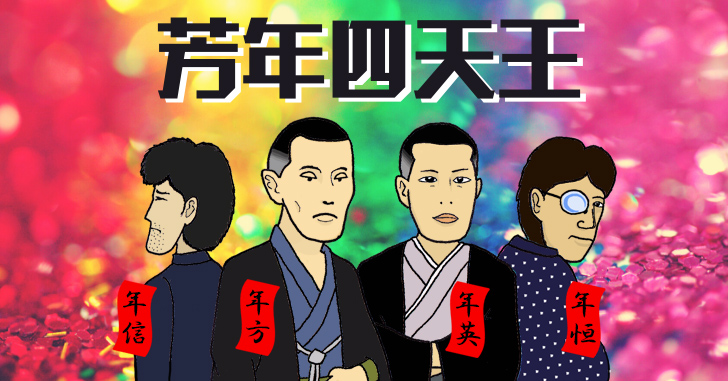


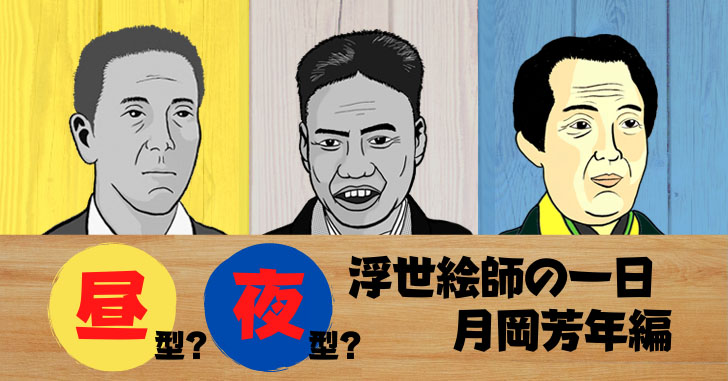





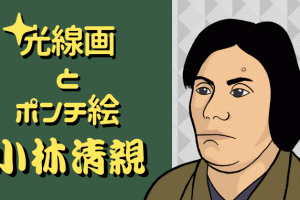

















コメントを残す