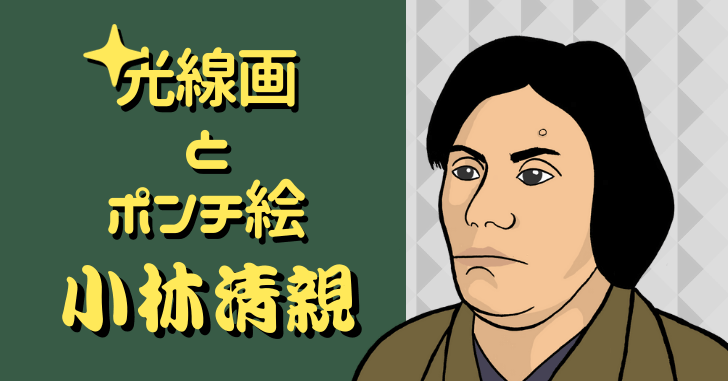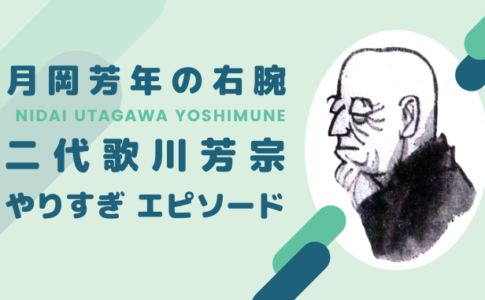明治期に西洋画の陰影を意識した「光線画」や世相を痛烈に皮肉った「ポンチ絵」を描いた浮世絵師、小林清親。その生涯と逸話を清親自身が最晩年に半生を振り返った「清親自画伝」を中心に紹介。
スポンサードリンク
目次
来歴
小林清親は、弘化四年(1847年)8月1日、本所御蔵役屋敷に生まれる。父・茂兵衛は年貢米の陸揚げを行う本所御蔵小揚総頭取を勤めた。祖先は三河(愛知県)の人で、徳川家に従って江戸に移り住んだ幕臣の家柄。父・茂兵衛と母・ちかのあいだに生まれた9人兄弟の末っ子が清親だった。幼名は勝之助。
幼い頃から絵が大好き
幼少の頃から絵に夢中だった勝之助(清親)。3、4歳頃には父親の部下から「坊ちゃんにはこれだ」と錦絵を買ってもらい、絵の玩具では少しも喜ばない勝之助が、錦絵には「絵紙だ絵紙だ」と喜んだため、珍しいと面白がられたそうだ。
そんな頃、年の離れた兄の家に遊びに行った時に絵を描いてとせがんだ勝之助。その兄は源義経が八艘飛びをする場面を描いた。ところが兄はいたずら心で義経がオナラをして飛んでいる図に書き換えてしまったため、勝之助はすっかり機嫌を損ねてしまった。兄嫁におぶわれて絵草子屋で極彩色の武者絵を買ってもらってようやく機嫌を直したという。(「小林清親」より)
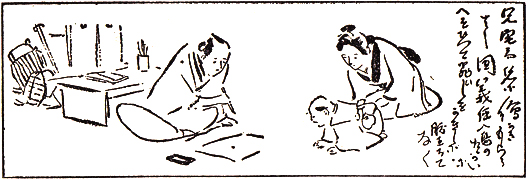
鳥羽伏見の戦い・上野戦争に参加
文久二年(1862)10月14日、清親の父・茂兵衛が亡くなった。病気に伏していた父の看病をしたのはもっぱら母・ちかと姉と勝之助の3人だけだった。他の姉たちは他家に嫁ぎ、兄たちは気ままに別居しており、家にも寄り付かなかったことから末っ子の勝之助が家督を継いだ。同時に元服し、名を清親と改めた。
江戸幕府14代将軍徳川家茂のもと長州征伐軍に参加した清親は、15代将軍慶喜にも従って幕府軍に所属していたため、鳥羽・伏見の戦いに参加することとなった。ただし、実戦部隊というより後方勤務で戦争の行方を遠くから見ていたにすぎないとも言われる。江戸に戻った清親は、緊迫した世情を考えて、これまで書き溜めていた画稿や参考のために蒐集していた絵本などを全て焼き、一度は絵の道をあきらめて武術の修練を積んだ。
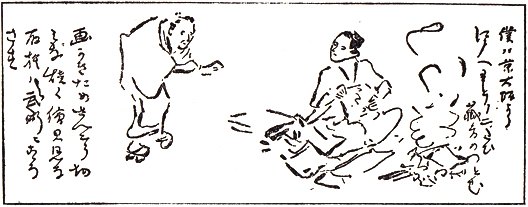
この後、旧幕臣たちが上野山に立てこもり、彰義隊という一団を組んで官軍と戦った上野戦争にも旧幕臣として参加した。この時の清親の役割は戦場の偵察だった。股引に半纏、手ぬぐいで頬かむりした人足姿に化け、広小路の雁鍋という料理店の用水桶の影に身を隠して戦争の成り行きを見ていた。すると流れ弾が用水桶に当たってひっくり返ったため、清親はあわてて逃げかえったという。(「小林清親」より)

剣術興行で食いつなぐ
徳川慶喜に従い、駿府(静岡県)に移り住んだ清親と母・ちか。武士の家の生まれだった母は絵の道に進むことを喜ばなかったため、清親は猟師や漁師の仲間に入れてもらい、その日暮らしをしていたこともあった。
やがて「最後の剣客」とも呼ばれる榊原健吉を団長とした剣術興行の一団を組み、地方巡業を行った。興業の呼び物は「飛び入り勝手」という他流試合。身長が六尺(約180センチ)以上という清親が出てくると、大抵の飛び入りは怖気づいて逃げ出した。他流の一団から不意打ちを食らって、逃げ遅れた清親が病院の2階の天井を破って屋根に上り、追手に対して屋根瓦を投げつけて退散させたこともあった。(「小林清親」より)
謎に包まれた画系
明治七年(1874)9月19日、清親の母・ちかが亡くなった。絵筆をとっても叱る人のいなくなった清親は、ついに本格的に画業で身を立てようと決意する。横浜では「THE ILLUSTRATED LONDON NEWS」の美術通信員として来日していたチャールズ・ワーグマンに入門したと言われるが、娘の小林哥津はドイツ人の画家に学んだと証言しており、はっきりしていない。清親がささいなことからワーグマンにクツで蹴られて腹を立て「一生カンバスとパレットは手にしない」と言って、出て行ったとも言われる(「清親と暁斎」より)。
横浜ではさらに淡島椿岳に泥絵(顔料に胡粉を混ぜ、直接筆を用いて不透明な色調で描かれた浮世絵の一種)を学び、東京では河鍋暁斎に絵の手本を受け、柴田是真に漆絵を、下岡蓮杖に写真術を学んだとする説もある。いずれにせよ、特定の絵師について学ぶのではなく、写生や絵師たちとの交流から独学で学びとったようだ。
光線画の大家へ
清親が日々行っていたスケッチはやがて版画となった。明治九年(1876)に絵師としてデビュー。その年の8月には「光線画」と呼ばれる、従来の浮世絵版画にはなかった光や影を駆使した表現で、江戸から生まれ変わった東京の季節や時間、天候を描いた「東京名所図」が好評を博す。
木版画での写実表現にも挑み、明治十年(1877)には清親の代表作とも言われる「猫と提灯」を第一回内国勧業博覧会に出品した。石版画を思わせる網目模様を駆使した表現は、35回も摺りを要する手の込んだものだった。井上安治が清親の弟子となるのもこの頃(明治十一年頃)である。

明治十四年(1881)には両国の大火に遭遇し、自分の家が燃えるのも構わず火事現場の写生を行い、これらの写生を元に木版画を刊行している。
新聞挿絵・ポンチ絵
両国の大火を契機に明治十四年から清親はいわゆる「洋風版画」から手を引いている。これには妻に去られた心理的要因や、世の中が行き過ぎた欧化主義の反省から、明治十二、三年頃に画壇においても国粋主義が広まり、「洋風版画」の受けが悪くなったとも言われる。(『清親と安治 明治の光の版画家たち』より)
さらに低コストの石版画に錦絵が押されぎみのなか、清親が選んだのは、物事をほのめかせる風刺を効かせた「ポンチ絵」だった。清親はワーグマンの「THE JAPAN PUNCH」から派生した「清親ぽんち」シリーズを明治十四年(1881)から刊行。明治十五年(1882)頃からは「団々珍聞(まるまるちんぶん)」に毎号風刺画も描き始めていた。

もっとも多忙な加賀町時代
明治十七年頃、田島芳子と再婚。明治十九年(1886)には三女・奈津子が生まれるが、妻・芳子の産後の肥立ちが悪く、占い師に方角が悪いと言われて引っ越しを繰り返し、京橋加賀町一丁目(現在の銀座七丁目)に落ち着く。清親が一番長く住むこととなったこの家には、弟子入りした土屋光逸が同居して家族に仕えた。
加賀町時代の清親は画業が最も忙しくなった頃だった。新聞挿絵や日清戦争の戦争画に加え、肉筆の注文を多く受けた。政治家でジャーナリストの末松謙澄は清親の写生を見て惚れこみ、たびたび清親の家を訪問。国会内の控室で清親をよく話題にしたため、地方出身の代議士たちが帰国の際の土産として、清親に肖像画の揮毫を頼んだという。
また政治家で実業家の秋山定輔の誘いを受けて二六社に入社し、娼妓自由廃業や財閥攻撃といった当時過激な内容で知られた二六新聞の挿絵も手がけるようになる。また門下生が増えたため、門人の田口米作を監督者とした清親画塾を自宅とは別の場所に開設した。
冤罪事件の受難
ある家の不倫記事が二六新聞の三面に大々的に書き立てられたことがあった。この人物が清親の妻、芳子の遠縁であることから清親に何とかしてくれと泣きついた。もともと人が良く、頼まれると放っておけない性格の清親は二六社に連絡し、報道を中止すべく世話を焼いた。
ところが、あいだを取り持った人物がいくらかのお金をとったとらぬという話になり、果ては清親自身がそういう恐喝手段を使ったのだと決めつけられて刑事事件に発展。明治三十四年(1901)、清親は一時的に警察に拘束されることとなった。これには清親が描いていた皮肉めいた新聞挿絵や、二六新聞の関係者として「危険人物」とみなされていたことが大いに影響したものと考えられる。
結局、無罪放免となった清親だったが、この一件により二六社を退社。しばらく画業からも離れ、妻とも一時別居するなど精神的に一番厳しい時期を過ごした。
写生旅行と晩年
明治三十年(1897)頃を境に、清親は各地へ写生旅行に出かけるようになる。友人や親類などを頼って席画会を開いて肉筆画を描きながら、信州を中心に桐生・足利・仙台・松島・米沢・福島・須磨・明石・福山・金沢・弘前を訪れていることがわかっている。自宅では書き溜めた絵を知人や弟子に見せて、その評価を聞いていた。そんな絵の中には後期印象派風の風景など日本画の約束事を無視した独創的なものがあったという。

晩年には清親の「東京名所図」などの洋風版画が偽物が出回るほど売れたとあって、当時の版元だった大平(松木平吉)や具足屋(福田熊次郎)が清親のもとを訪れて、昔のような風景画の出版依頼を打診した。ところが清親は「昔のようなと云っても、さてあんなものは今更らしくかけやしない」と筆をとろうとはしなかったという。
しかし絵師としての意欲は衰えることなく、明治四十一年(1908)に61歳となった清親は友人の勧めで、両国美術倶楽部で千画会を開いた。一日に千幅の席画を描いたのである。最晩年の大正三年(1914)にも京橋築地クラブで「清親百画頒布会」と称した会を行っている。
墓
晩年まで精力的な清親だったが、旅先で持病のリウマチが悪化し帰宅を余儀なくされ、大正四年(1915)11月28日に亡くなった。享年69歳。
台東区元浅草の龍福院に小林清親の墓がある。しかし、お墓自体は現在非公開。小林清親の墓の画像(白黒)は昭和十一年に発行された『東京美術家墓所誌』に掲載されたもの。
龍福院の本堂向かって右には「清親画伯之碑」の石碑があり、石碑裏には清親の法名「真生院泰岳清親居士」が刻まれている。
逸話
明治期の浮世絵師としては珍しく、早くから研究が進んでいた小林清親。残された逸話も少なくない。ここではそのいくつかを紹介する。
筋金入りの写実主義
絵に夢中な幼い勝之助(清親)のことを思い、父・茂兵衛は近所にいた絵の先生のもとへ弟子入りさせようとした。母・ちかに連れられて、絵師先生のもとへ行くと、先生はまず絵手本にと梅と竹を描いた。ところが勝之助は「こんな梅や竹があるものか」と言ってその絵を先生のもとへ投げ返して家に帰ってしまった。残された母はいたたまれない思いをしたことだろう。(「清親の追憶」より)

按摩さんにいたずら
1升2升は平気で飲んでいたというお酒の強かった清親。そんな清親が酒宴で行ったおふざけについての証言が残されている。
小林清親が京橋加賀町にいた頃、何とかいう按摩が毎日のように出入していた。この盲人は面白い男で、唄をうたうのみか踊りを得意にしているので、客が来て飲む時に座を持たせる事もあり、就中(なかんずく)新春の書初めの時などは、この按摩さん、盛んに余興の芸をやった。或年の試筆の夜も、酔って頻(しき)りに踊っていたが、
「先生、わたくしの顔に目を描いてください」と言うと清親は、
「宜し宜し(よしよし)、好男子にしてやろう」と胡粉、緑青、朱の絵具皿を引寄せて、物凄い化物の顔にしてしまった。これを見て一座の人々、ワッと笑い出し、手を叩いて囃し立てると、当人は凄い顔になったとは思わず「どうです、色男になりましたろう」と踊り狂っていたが、やがて帰る時分に顔を洗うのを忘れて表へ出かけ、芸妓町へさしかかると、向うから来た雛妓(はんぎょく)がそれを見て「キャア」と叫んで逃出す、箱丁(はこや)は笑い出す、怒り出す姐さんもあり、大騒ぎを演じた。(『明治のおもかげ』より)
お酒をやめて始めたこと
大酒飲みだった清親だったが、日清戦争の頃にはお酒をやめたという。注文を受けた日清戦争の戦争画を次々と描く一方で、戦争画で得たお金を酒には費やさず、戦争に出向くことになった彫り師・摺り師といった画工職人たちに全て渡していたそうだ。(「清親の追憶」より)
甘いものが大好き
お酒をやめて、甘いもの好きとなった清親。清親の甘党ぶりは娘によって書き残されている。
お酒をやめてから、めっきりと、お菓子づきになりまして、まるで子供の様に、お八つを催促しました。何にもなくて、一寸(ちょっと)口さみしい時には、干したかきもちを、ちゃんとかんの中からもち出して行って、絵ノ具をあぶる網の上で、ぷんぷん匂ひをさせて、一人やいてゐる事もありました。
ある時は、例の通り、少しさみしくなった時分と見え、本をよんでゐた私一人の茶の間にのっそりと入って来て、その長い手をのばして、仏様(注:仏壇と思われる)の中から何やらつまみ出して、頂いてをりますのを、ふっと見ると、それは親戚の女が、先刻持って来て呉れました、七面様(注:七面山、古くから山岳信仰の対象で法華経信仰の聖地)のお砂を、おき場にこまり、一寸仏様に入れておいたのを、出して食べてゐますので、私はなみだが出る程おかしく、父はまた、落雁(らくがん、穀類の粉に砂糖や水あめなどを入れて練り、木型に押して乾燥させたお菓子)だと思って、半分もうすでに、のみこんで了(しま)ったと云って、さすがにしぶい顔をしてゐるおかしさで、さんざんお腹をかゝえたことがありましたが、落雁を見ると、今だにこの時のおかしさを忘れられないのでございます。(「清親の追憶」より)
まとめ
さまざまな絵師と交流しながら、独学で絵を学びとった清親は光線画で浮世絵に一石を投じることになった。特に海外の石版画や新聞の影響を受けながら、日本にマッチした画風へと昇華させる手腕は生前から現在まで変わらず評価されている。
光線画やポンチ絵以外の清親の画業は見過ごされがちとなっていたが、近年は肉筆画の傑作も見出されており、清親の真の評価はむしろこれから進むかもしれない。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
よろしければ応援クリックをお願いします!
![]()
にほんブログ村
参考資料
『浮世絵志』第22号「清親と暁斎」
『浮世絵志』第27号「小林清親」大曲駒村
『中央公論』第39年6月号「清親の追憶」小林哥津
『東京美術家墓所誌』結城素明
『清親と安治 明治の光の版画家たち』近藤市太郎
『小林清親 東京名所図 解説編』学研
山田書店オンラインストア
ボストン美術館デジタルアーカイヴ
フリーア美術館デジタルアーカイヴ