奇想の絵師として伊藤若冲、曾我蕭白らとともに注目を集めてきている長沢芦雪(ながさわろせつ)。ユーモアあふれる絵が知られる反面、その最期は他殺説・自殺説がささやかれている。そこで今回は長沢芦雪の死因について追ってみた。
目次
長沢芦雪略歴

宝暦四年(1754)京都に生まれる。『平安人物志』天明二年(1782)版に名が掲載され、京都文化人の仲間入りを果たす。師である円山応挙が完成させた絵を携え、応挙の代理として向かった紀州・無量寺や帰途の紀州路にて多くの作品を残す。写生を重んじた画風の師とは対照的に、奇抜な筆致・大胆な構図・機知に富んだ画風として知られ、現在では「奇想の絵師」の一人に数えられている。
師の円山応挙の場合、応挙自身は「圓山應挙」と旧字体でしか表記していないが、現在では「円山応挙」という新字体が一般的となっている。今後は芦雪の場合も「長沢芦雪」と新字体で統一される流れになりそうだが、旧字体表記派も根強く、現在みられるような表記ブレ状態となっている。
ちなみに本記事内では「長沢芦雪」の新字体を採用し、アイキャッチ画像のみ「長澤蘆雪」と旧字体表記としている。

長沢芦雪の死にまつわる諸説
長沢芦雪の死に関しては諸説がある。大坂(現在の大阪)で死んだことは、生前の芦雪と親交のあった儒者の皆川淇園(みながわきえん)の証言で明らかだが、死因に関しては他殺説・自殺説が語られてきている。これまで語られてきた芦雪の死因に関してまとめると以下の通り。
怨恨説1
- 証言者:碓井玉輪(うすいぎょくりん、明治期の絵師・歌人)
- 動機:淀藩士の怨恨による殺人
- 詳細:淀城の障壁画を描くよう命じられた芦雪は、「絵が完成するまで誰も見てはならない」との条件付きで承諾。ところが藩士のひとりが描いているところをのぞいてしまったため、芦雪は彼を切り殺した。これが原因で藩士に憎まれており、ついには大坂で殺されるに至った。※碓井玉輪は、淀藩士のひとりから聞いたと証言
怨恨説2
- 証言者:竹川友広(たけかわゆうこう、明治期の(円山派)絵師)
- 動機:淀藩士の怨恨による毒殺
- 詳細:淀藩主の芦雪の寵愛ぶりが「一方ならず」、芦雪が「わがままな振る舞い」がひどくなっていた。これに淀藩士の恨みを買い、ついには大坂で毒殺されるに至った。
嫉妬説1
- 証言者:竹川友広(たけかわゆうこう、明治期の(円山派)絵師)
- 動機:広島藩付き絵師の嫉妬による毒殺
- 詳細:広島藩主が芦雪の絵を気に入り、淀藩を通じて招こうとした。広島藩に仕える絵師がこれに嫉妬し、大坂で毒殺。※竹川友広は、怨恨説2の異説として証言
嫉妬説2
- 証言者:森川曾文(もりかわそぶん、明治期の(四条派)絵師)
- 動機:土佐藩付き絵師の嫉妬による毒殺
- 詳細:土佐藩主が芦雪の画名が高いのを知って、藩に招こうと土佐藩に仕える絵師を派遣。芦雪に嫉妬した絵師は、土佐藩に向かう途中に大坂で芝居見物に誘い、観劇中に食べる幕の内弁当に毒を仕込んで殺害。
自殺説
- 証言者:東東洋(あずまとうよう、江戸中・後期の絵師)
- 動機:貧乏を苦に首吊り自殺
- 詳細:芦雪は、円山応挙の死後、慢心したあげく絵が悪くなり(注文もなくなり)、貧乏生活にあえいだ。友人の皆川淇園に頼み込み、祇園で描いた絵に讃を書き入れてもらったものを売って一日の糧を得ていた。しかし、いよいよ貧窮極まって、大坂に行って首吊り自殺をとげる。
芦雪が「ろくな死に方はしない」と思われた要因
芦雪の死因に諸説が飛び交っているのはひとえに芦雪が「ろくな死に方はしない」と思われていたからと推測される。それを裏付けるような逸話がいくつか残っている。
師・円山応挙をも恐れぬ振る舞い
芦雪は常にシャレを利かせた自由奔放な「粗画」を描いていたため、師匠の応挙からお叱りを受けることがたびたびあった。ある日、応挙の弟子たちが集った画会で、登竜門(鯉の滝登り)の「粗画」を描いて応挙に提出した。応挙は眉をひそめてその絵を眺めていたが、押された印章を改めてよく見るとそれは印章ではなく、わずか一寸四方に描かれた十六羅漢の細密画を印章に似せて描かれたものだった。これに気づいた応挙は初めて芦雪の画才は細密画も上手いと知って、ほめたたえたという。(堀成之『今古雅談』より)
またこんな逸話もある。
ある時、芦雪は応挙から受け取った絵手本をそのまま応挙のもとに持っていき、絵の添削をお願いした。すると応挙は「これは悪い」と少々の直しを入れられた。今度はそれを芦雪自身で清書して再び応挙に絵の添削をお願いした。今度は応挙から「これで良い」と言われた。しかし、事の顛末を知った応挙から破門されたという。(安西雲煙『近世名家書画談』より)
近年の研究では、応挙が芦雪を破門したという事実はないという。しかし、このような逸話が残っているのは、芦雪がいつも師を恐れぬ態度で接していたからだろう。これらの逸話から、応挙を敬愛する兄弟弟子からは良く思われていなかったのでは?と察せられるところがある。
武家出身であることを誇る
和歌山県高山寺第十世住職の義澄和尚が残した日記『三番日含』のなかで、芦雪のことについて書かれている。芦雪に関する内容は師の応挙の代理として紀州を訪れた芦雪自身が義澄和尚に語ったことと考えられている。そこにはこんな記載がある。
もと丹波篠山の青山下野守の家臣で、父親が上杉彦右衛門尉といった。父は後に淀城主である稲葉丹後守の家臣となった(記載が混乱しており、稲葉丹後守の家臣は、父ではなく芦雪自身という説もある)。芦雪は絵師となる道を選んで父の上杉姓から分かれた(長沢姓を名乗った)。(中略)父は後に和左衛門に改名した。(後略)
こうして武家の出であることを述べる一方で、応挙の代理で紀州に来たことは全く触れていない。このことから、旅先で知り合った相手に対して、ふだんから「私はもとは丹波篠山青山家の家臣で・・・」うんぬん、相手が興味なさそうな父親の改名まで話に出して、武家出身であることを誇っていた証拠ではないかとする説がある。
義澄和尚が、よその小さな藩や下級武士の名前を誤字なく、聞き取りながら書き留めるのは難しいのではないかとする考えもある。しかし、先ほどの師を恐れぬ態度と考え合わせると、その根底には自らの画才だけでなく武家の生まれ(※師の応挙は農家の生まれ)というプライドのようなものが芦雪のなかにあったのではないだろうか。
調子にノッた振る舞い?
前述の自殺説と酷似するものの、結末が違うエピソードも伝わっている。
友人である皆川淇園とふたりで京都祇園の某寺で、芦雪が絵を描き、淇園がその絵に讃を書き入れた作品を頒布する会を催した。人が争って買い求めたため、数日のうちに大金が手に入った。その金を手に妓楼で宴会をあげて、夜を徹して飲み明かし、得た金を使い果たしたという。(白井華陽他『画乗要略』より)
この逸話から、話が伝聞されていくなかで「調子にノッていた話」と「大坂での死去」という話が合わさって捻じ曲げられ、最終的に「貧窮のあまり一日の糧を得るため」という自殺説となった可能性がある。現に晩年の芦雪は兵庫県大乗寺の「群猿図」や広島県厳島神社の「山姥図」といった代表的な作品を残しており、注文が減って貧乏生活で困っていたとは考えにくいからだ。
まとめ
芦雪の死因をめぐるこれまでの経緯を追ってみたが、いずれの説も証言者自体が伝聞情報を元にしていたり、推測の域を出なかったりしており、死因を決定づける説にはなっていなかった。
芦雪の死んだ場所が慣れ親しんだ京都から少し離れた大坂の地であったこと、そしておそらく予期せぬ突然の死であったことがさまざまな憶測や噂を生み、それが口伝で残っていたのではないかと思われる。噂をするなかには、画才を誇り、武家の出を誇っていた芦雪の態度をよく思わなかった者たちも少なからずいたのだろう。
本当の死因が何であろうと、生前の芦雪を知る京都に残った者たちの噂によって芦雪は「殺された」あるいは「自殺した」ことになったのは間違いなさそうだ。今後、芦雪の死因を決定づける手紙等の史料の発見がのぞまれる。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
よろしければ応援クリックをお願いします!
![]()
にほんブログ村
参考資料
『中央美術』四ノ八所収「蘆雪物語」相見香雨
『書画聞見集』澹斎
『今古雅談』堀成之
『画乗要略』白井華陽他
『近世名家書画談』安西雲煙
『開館二十五周年記念 長沢芦雪展 京のエンターテイナー』図録 愛知県美術館・中日新聞社編
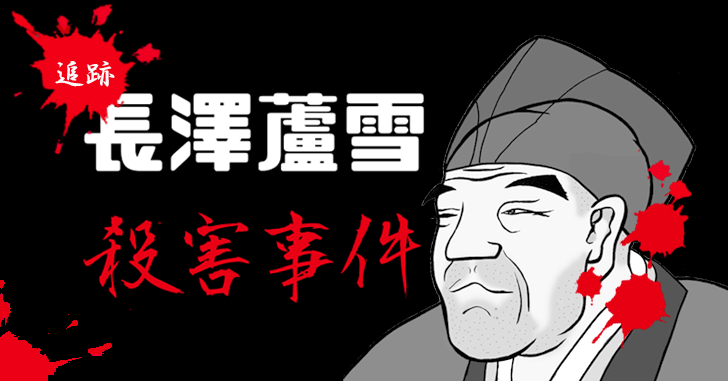




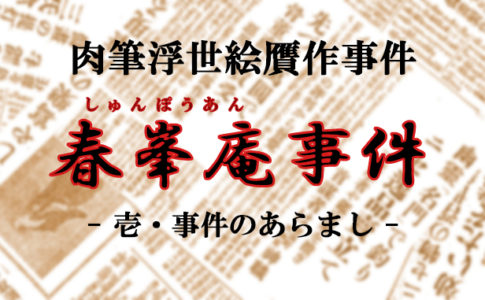


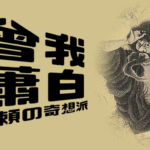
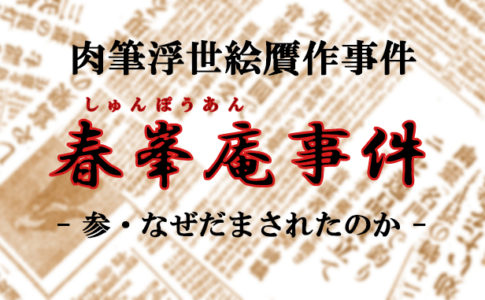

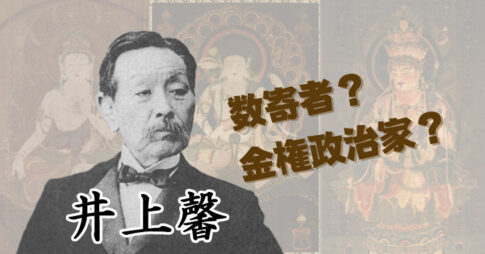
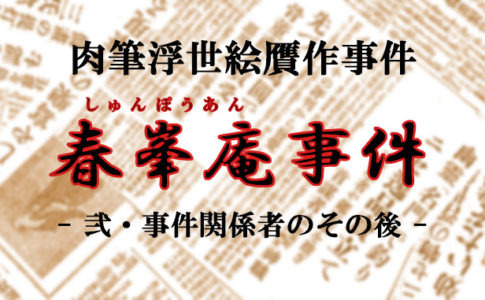
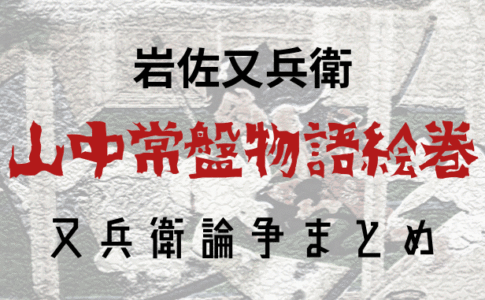
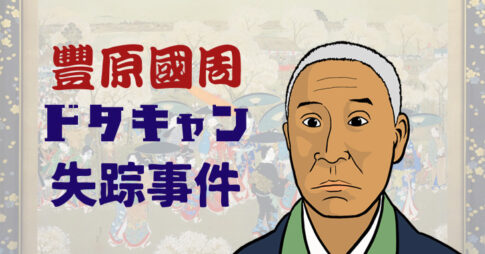









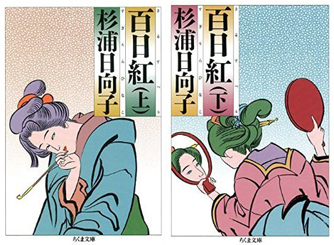

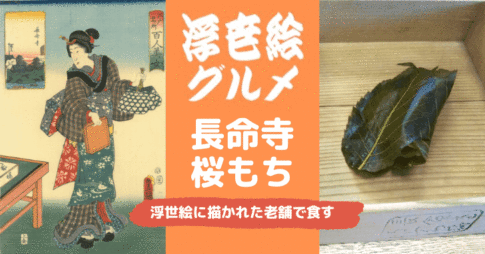

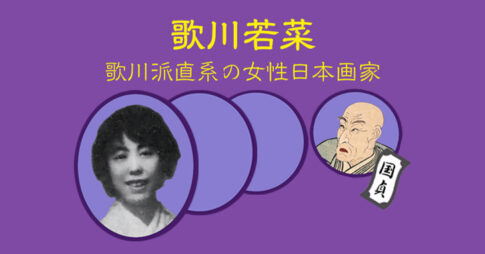
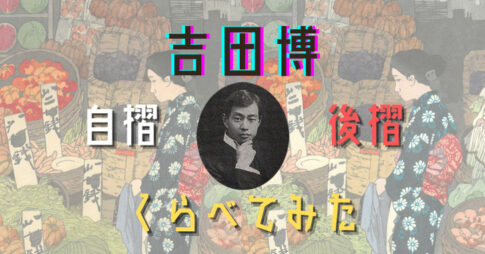
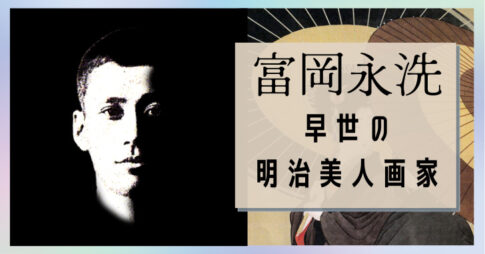
突然すみません、一般的な表記は皆川淇園だと思います…
よろしくお願いします。
ご指摘ありがとうございます!
さっそく修正しました。