浮世絵グルメシリーズ4回目は山本屋の長命寺桜もちについて取り上げる。現在の建物に江戸中期創業の面影こそないが、老舗の歴史は随所に感じられる。長命寺桜もちが描かれた浮世絵や逸話の紹介とともに長命寺桜もちを食レポしてみた。
目次
長命寺桜もちとは
創業秘話
元禄4年、下総銚子から江戸に出て長命寺の門番として住み込んでいた山本某が、享保年間に川端の桜の葉を塩漬けにして餅を包んだ桜もちを作り、売り出したのが長命寺桜もち・山本屋の始まりである。
早くから評判のお店となり、曲亭馬琴の随筆「兎園小説」のなかでは、文政7年(1824)の売上について、以下のように税務署顔負けの細かさで記載されている。
去年甲申一年の仕入高、桜葉漬込三十一樽(但し一樽に凡二萬五千枚ほど入れ、)葉数〆七十七萬五千なり。(但し餅一つに葉三枚づゝなり。)此のもち数〆三十八萬七千五百、一つの価四銭づゝ、この代〆千五百五拾四貫文なり、金に直して二百二十七両一分二朱と四百五十文、(但し六貫八百文の相場、)この内、五拾両砂糖代に引き、年中平均して、一日の売高四貫三百五文三分づゝなりといへり。
新狂言「都鳥廓白浪」で話題に
安政元年(1854)3月に演じられた猿若町河原崎座の新狂言「都鳥廓白浪」。歌舞伎狂言作者の河竹新七(のちの河竹黙阿弥)は、「義経千本桜」の登場人物“いがみの権太”をもじって、市川小団次が演じる“忍の惣太”の家を桜もちの山本屋にしてみせた。
この芝居には裏話がある。演者がそろった本読み(台本の読み合わせ)段階で不満気だった市川小団次の様子をみた座元の河原崎権之助は、河竹新七を小団次へ遣いに出して話を聞きに行かせた。
小団次いわく「高い金を出してこの小団次をお抱えなすって、明盲で子供を殺すだけの役をお見立てなすったのはどういうお見込みか。名人歌右衛門さんならいざ知らず私のほうに考えはない。この小団次の体にはまるようにしてくださるか、さもなくばご辞退申そうと思います」とのこと。
新七は驚いて座元に話を持ち帰ると「どうにか工夫して納めてくれ」と台本の書き直しを命じられることとなった。
堤の殺しの場にチョボ(地の文を義太夫節で語る場面)を入れて、舞台と花道を割り台詞とする手直しを徹夜で仕上げて、新七は翌朝その台本を小団次のもとへ持っていった。
小団次は台本に目を通すと「よく直りました。これなら私にも出来ましょう。どうも昨日はわがまま言って」と機嫌を直したという。
市川小団次の見せ場を増やした芝居は大いに受け、長命寺の桜もちの評判はさらに高まった。

老中・阿部正弘と看板娘・おとよ

山本屋の二代目・山本金五郎には二人の子どもがいた。弟の新六は三代目の主人、姉・おとよは無類の美女と評判だった。
おとよが生まれて数年後の天保14年(1843)閏9月11日、福山藩阿部伊勢守正弘はわずか25歳で老中となった。安政年間となり、阿部正弘は生母が住む下屋敷があった本所石原町をしばしば訪れている。その折、話題の美女として名を馳せていた看板娘・おとよに目が留まったとされる。
ちょうどそのころ、徳川御三卿・田安家の慶頼公が牛島神社参詣の際におとよに桜もちを持参させたという話に意を決したか、阿部正弘はおとよを側室に迎えたという。
正岡子規と看板娘・おろく
時代は下って明治21年(1888)、正岡子規は22歳の夏のひとときを牛島月香楼で過ごした。月香楼とは彼が間借りした長命寺桜もち屋の二階を自称したもので、特にそんな名があったわけではない。
そこで店の看板娘・おろくと男女の関係にあったのではと仲間内で噂を立てられた子規は、デマであることを友人たちに示すために「七草集」という文集を作ったといわれている。そのなかで詠まれた歌をいくつか紹介しよう。
花の香を若葉にこめてかくはしき桜の餅家つとにせよ
(桜の餅をあきのふ主人に代りてよめる)
思ひきやかくまてなれし景色さへ今は恨のたねならんとは
(あらぬ噂きゝしよりよめる)
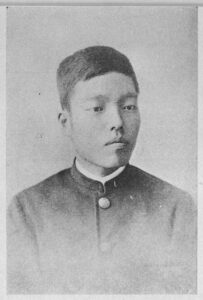
さらに「七草集」のなかでも「寄隅田川名所恋」として詠まれた歌には子規の片思いと読み取れるものもあった。
鐘の音に夢さめはてゝ浅草や朝の別れのつらくもあるかな
うけぬとは知れとも祈る三めくりやめくりあひたし別れにし君
我恋は秋葉の杜の下露と消ゆとも人のしるよしもなし
おろくは明治5年(1872)生まれで、子規からのラブレターをもらったかもしれない明治21年には16歳になっていたが、子規からの手紙や遺品はおろく自身で始末したらしく、今は何も残っていないという。
長命寺桜もちが描かれた浮世絵
浮世絵に描かれた看板娘・おとよ
長命寺の桜もちが描かれている浮世絵として今回取り上げるのは「江戸名所百人美女 長命寺」。「江戸名所百人美女」は三代歌川豊国(歌川国貞)が人物を、三代豊国の弟子で娘婿でもある二代歌川国久が美人画に添えられたコマ絵を描いている。
三代豊国は同時期の浮世絵師だった歌川広重、歌川国芳と並び称され、「豊国にかほ(似顔絵)、国芳むしや(武者絵)、広重めいしよ(名所絵)」とうたわれた当時随一の浮世絵師。「江戸名所百人美女」は三代豊国が七十歳頃に描いた円熟期の作である。

「江戸名所百人美女 長命寺」で描かれているのは、前述した看板娘・おとよ。髪型は「つぶし島田」と呼ばれる、島田髷の髷先をつぶしたような当時の流行髷。
着物は味噌漉格子と呼ばれる、味噌を漉すときに使う竹ざるの目をかたどった格子柄。帯は葉付きの菊柄で、裏地には緋色の地に白抜きで菊の文様が配されている。前掛けには上部に桜、下部には隅田川に浮かぶ都鳥と桜の花びらと隅田川の春の光景が描かれている。
おとよが左手に持っているのは、お土産用の桜もちが入った竹ざる。この形の竹ざるは、当時の隅田川周辺を描いた浮世絵に時おり登場するが、まず長命寺の桜もちと考えてよいだろう。
この浮世絵が出た安政4年(1857)11月には、看板娘・おとよはすでに阿部正弘のもとにおり、店番には出ていなかった。しかも阿部正弘は同年6月17日に39歳という若さで亡くなっている。
ペリー来航・幕府の弱体化と内憂外患の状況で老中の座にいた阿部正弘。早すぎる死は心労もたたったように思うが、おとよが阿部家に入って間もないこともあってか、若い娘に精力を使い果たしたというあらぬ噂も立てられた。そんな「炎上」している状況で出された浮世絵だったのである。
その後のおとよ
阿部正弘の死去後も福山藩邸に住んでいたおとよだったが、明治維新後に向島の生家に戻ってきた。当時の年齢が40代のことというから、明治10年代であろう。
内縁の夫と長命寺裏門の脇に二階建ての家を建てて、桜もちならぬ桜寿司を始めたという。おとよには娘が一人いたが、娘の急病と入院の報に大きな衝撃を受けたおとよは、ほどなくして体調を崩し、大正3年(1914)9月19日、75歳でこの世を去った。
長命寺桜もちを実食

押上駅または曳舟駅から徒歩で10数分、長命寺桜もちの山本屋に到着。さっそく店内でいただく。
昭和に建てられた建物は江戸の風情こそないものの、お店にまつわる浮世絵が店内に飾られているのは老舗ならでは。
コロナ禍前には、年季の入ったお盆で供されていた桜もちが、近年ではキレイなお盆で提供されているようだ。

前述した曲亭馬琴の随筆「兎園小説」に餅一つに葉三枚づゝなりと書かれていた通り、現在も葉っぱ三枚が使われている。
桜もちといえば、葉っぱごと食べるか食べないか問題がある。わたしは葉っぱは食べない派。塩漬けの葉を三枚も食すのはさすがに多いのか、食べる派の友人は一枚はもちと一緒に食べて、余った二枚は持ち帰ったあとで刻んでお茶漬けにいれるという。
葉っぱを食べなくとも葉っぱから桜の香りを楽しむことができるし、塩漬けの葉っぱから薄皮もちに移った塩味があんこのほどよい甘さとマッチしている。
名残惜しさを感じつつ少しずつ口に運んだつもりが、気づけばあっという間に平らげていた。近くに寄った際にはまた是非訪れたい。
長命寺桜もち営業情報
営業時間 8:30から18:00まで
月曜・火曜定休日
公式サイト
https://sakura-mochi.com/
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
よろしければ応援クリックをお願いします!
![]()
にほんブログ村
参考資料
『謎解き「江戸名所百人美女」江戸美人の粋な暮らし』山田順子(2016)
『のれんは語る〈東京篇〉老舗食べあるき』高瀬勝治(1978)
『隅田川の今昔』鹿児島徳治(1972)
『近世日本国民史』「第29 幕府実力失墜時代」(1934)
『日本随筆大成』㐧二期 卷一「兎園小説」曲亭馬琴(1928)
『江戸から東京へ』第6編「桜餅のおとよ」矢田挿雲(1923)
『大名生活の内秘』三田村鳶魚 早稲田大学出版部(1921)
「近代日本人の肖像」国会図書館
早稲田大学浮世絵データベース
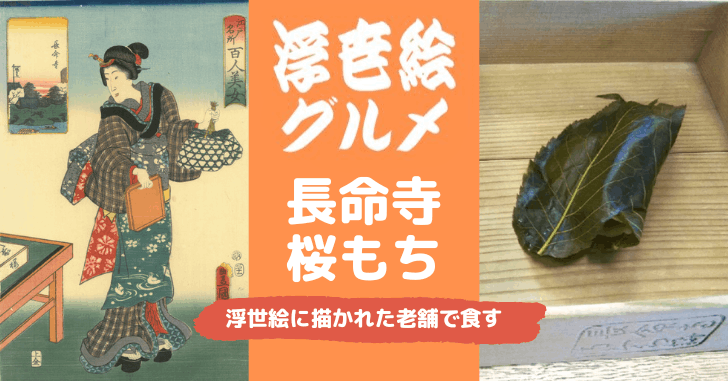






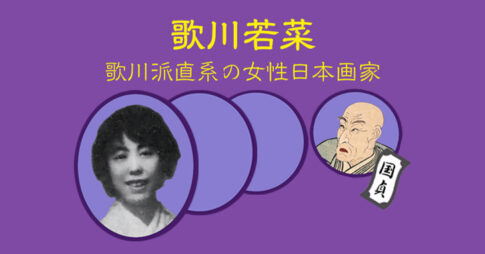

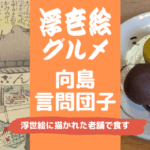
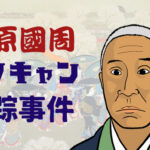
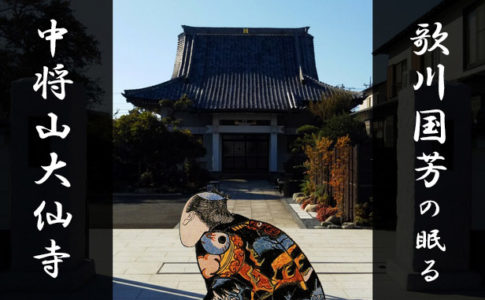














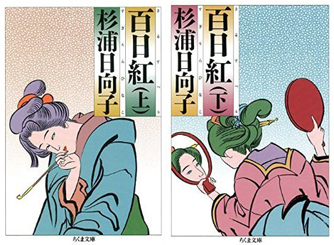
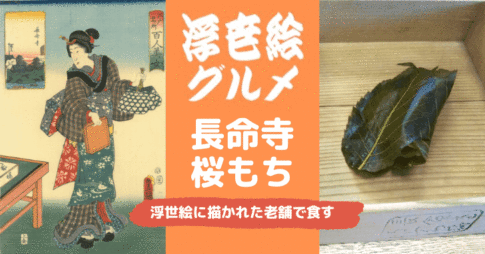
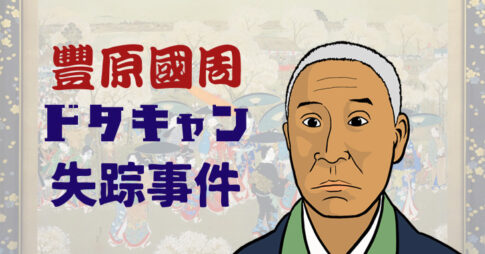

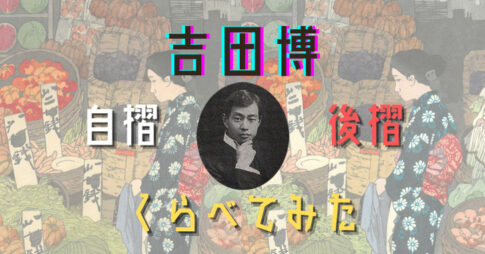
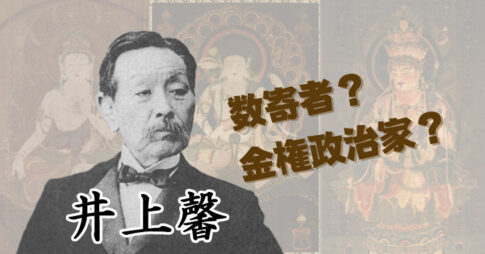
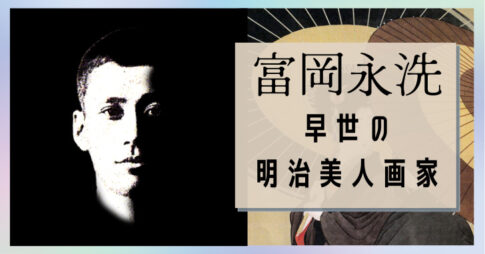
コメントを残す