明治期に衰退していた日本画に新しい変革をもたらした狩野芳崖。その生涯と逸話を弟子・岡不崩が著した『しのぶ草』を中心に紹介。
スポンサードリンク
目次
来歴

狩野芳崖は、文政十一年(1828)に現在の山口県下関市長府の城下町に生まれる。幼名・幸太郎。父は徳川幕府直属の奥絵師四家のひとつ、木挽町狩野家に学び、長府藩狩野派の御用絵師だった狩野晴皐(せいこう)。絵師になることを運命づけられた出自の通り、幼い頃から父・晴皐の厳しい手習いを受けることとなる。
木挽町狩野家への弟子入り
弘化三年(1846年)、19歳で江戸へ上京し、父も学んだ木挽町狩野家の狩野晴川院養信(せいせんいんやすのぶ)に入門。同じ日の入門者には後々まで盟友となる7歳下の橋本雅邦がいた。しかし、入門からわずか一カ月で晴川院は亡くなったため、後を継いだ二十代半ばの勝川院雅信(しょうせんいんただのぶ)から学ぶこととなった。
狩野派秘蔵の絵手本を模写する修行を重ね、芳崖は入門から3年後の嘉永二年(1849)には師匠の一字をとって「勝海(しょうかい)」と号し、その翌年には弟子頭に任命された。さらに嘉永五年(1852)には再度師匠から「雅」の字をとって藤原雅道(ただみち)と改名。25歳にして早くも長府藩お抱えの絵師として独立した。
しかし、旧来の狩野派に不満をもっていた芳崖は、つねづね「探幽・常信の糟粕をなめず(狩野派ビッグネームの真似事では終わらない)」と公言していたという(橋本基「橋本雅邦小伝」)。さらに弟子頭時代に画塾を抜け出して因州(現在の鳥取県東部)まで行ったり(『書画骨董雑誌』鍬形蕙林)、師匠の勝川院雅信に叱責されて、結城正明(画塾では芳崖の後輩、若き日の横山大観・菱田春草を指導した日本画家)に理由を聞かれた芳崖が「師匠は画を知り玉わず」と答えた(「狩野芳崖」横山健堂)との逸話も残っている。
明治維新前後の貧乏時代
安政四年(1857)、30歳となった芳崖は生まれ故郷の長府に向かった。その理由として、母の逝去、山水画や仏画を描くための取材旅行、あるいは佐久間象山とも交流があったことから政治的な動きとの説もある。我が家に戻った芳崖は父・晴皐や親族が手はずを整えたであろう結婚式にのぞみ、豊浦藩(下関)の医者・田原俊貞の長女「よし」を妻に迎えた。
御用絵師として、江戸(東京)と長府を幾度となく往復しつつも画業を止むことはなかった。しかし、明治維新の急変する世の中で芳崖は貧苦にあえいだ。一時は故郷の邸宅を売って養蚕業や山林開拓を行ったが全て失敗に終わったという。
この頃から芳崖の号を使い始める。菩提寺の覚苑寺(かくおんじ)の霖龍如沢(りんりゅうにょたく)和尚から教わった禅の言葉から「決まったやり方の外に出る」を意味する「法外」としようとしていたのを、近親者から雅びでないからと「芳崖」の字を勧められたのに従ったと言われている。
岡倉天心、フェノロサとの出会い
芳崖が覚悟を決めて故郷の長府を出て上京したのは50歳になってから。生活の困窮、養子・廣崖(こうがい)の慶應義塾への入学、そしておそらくは知人のすすめも理由にあっただろう。画塾時代に芳崖を含めて「勝川院四天王」と呼ばれた橋本雅邦・狩野友信・木村立獄も東京にいたからだ。上京から2年後の明治十二年(1879)、芳崖の困窮ぶりをみかねた橋本雅邦は鹿児島の島津家から依頼された『犬追物図』の製作を芳崖に譲った。ここから3年のあいだ島津家に月俸数十円で雇われる身となり、生活は安定していく。
この頃、芳崖は岡倉天心(覚三)、さらには岡倉が政治学・経済学を学んでいた先生でもあったアーネスト・フェノロサとも出会ったとされる。岡倉という優秀な「通訳」を介して、日本美術に傾倒していったフェノロサ。来日した実業家のウィリアム・スタージス・ピゲローの日本美術蒐集を手助けするため、さらにフェノロサは古美術鑑定など実地研究に勤しむことになる。
明治十五年(1882)、農商務省主催による第一回内国絵画共進会が開催された。芳崖は8点を出品したが、狩野派でも守旧派が審査を行う会においては落選の憂き目にあうしかなかった。この結果に憤った岡倉は明治十八年(1885)、新たに鑑画会を立ち上げる。主任にフェノロサ、参加した画家のなかに芳崖や橋本雅邦の名があった。
日本美術の命運を賭けた伊藤博文との会見
鑑画会で芳崖は自身の代表作となる作品を次々と出品。第一回鑑画会では『伏龍羅漢図』(福井県立美術館蔵)で三等賞、第二回鑑画会では『仁王捉鬼図』(東京国立近代美術館蔵)で一等賞を受賞する。
第二回鑑画会に招待された、時の総理大臣・伊藤博文は『仁王捉鬼図』に感銘を受け、芳崖に絵を依頼した。芳崖は絵を飾る場所の光の当たり具合や画題の好き嫌いを聞くことを理由に、伊藤博文の自宅で会うことを約束して絵の依頼を受ける。芳崖は以前から後継者育成のための学校の必要性を考えており、総理大臣に直談判を考えていたのだ。
芳崖は、話が途切れれば多忙な大臣に立ち去られてしまうと考え、間断なくどう話すか入念に手帳に記して、伊藤博文との会見に臨んだ。会見の場で芳崖は、西洋画好きの伊藤に日本画の美点や美術学校の必要性を説き続けた。伊藤博文は熱のこもった芳崖の話を3時間も聞き続けることになり、後の予定に遅れるしかなかったという。
この会見がきっかけとなったのか、明治二十年(1887)十月勅令をもって東京美術学校の設立が公布される。伊藤博文から依頼された『大鷲』は動物園での写生や弟子の岡不崩の助けも借りて完成させた。現在、東京藝術大学が所蔵している。
狩野芳崖遺作の悲母観音
明治二十年(1887)7月10日、貧乏時代から芳崖と共にした妻の「よし」が亡くなった。芳崖は亡き妻についてこう述懐している。
小共は母親の感化により善くも悪しくもなる夫は妻女の為めにいかやうにも左右せらるゝものである。女史はちやうど観音様のやうである。(中略)わしは仕合せにも観音様(細君を云ふ)が能くして呉れたからなあ。(『しのぶ草』より)
そんな芳崖が最後に取り組んだのが屈指の名作『非母観音』(東京藝術大学蔵)。『非母観音』はパリ日本美術縦覧展のため、明治十六年(1883)頃に描いた『観音』(フリーア美術館蔵)をさらに深化させ、新たに描き直したものだった。


よく似た構図の両者のなかでも細かい違いがあるが、一番異なる点は観音様のご尊顔だろう。『観音』では男性を思わせる顔つきだが、『悲母観音』では女性的な顔になっている。これは『悲母観音』のモデルが女性(文部省官僚・九鬼隆一の妻、波津子)だったからだと言われる。九鬼波津子をモデルとした説については『狩野芳崖 受胎観音への軌跡』に詳しい。
墓
肺を侵され咳に苦しむなか、息を殺して金砂を蒔き、遺作となった『悲母観音』を仕上げた芳崖だったが、明治二十一年(1889)11月5日に亡くなった。享年61歳。狩野芳崖の墓は台東区谷中の長安寺にある。法名は「東光院臥龍芳崖居士」。墓石には芳崖の法名と妻「よし」の法名「性静院花室妙愛大姉」が刻まれている。
同寺の本堂前には、狩野芳崖の生涯と功績をたたえた「狩野芳崖翁碑」(大正六年(1917)造立)が建つ。高さ220センチ・幅85.5センチという大きな碑の題字は、岡倉天心の文部省時代の上司、浜尾新(はまおあらた)によるもの。
アクセス:JR日暮里駅から徒歩8分、東京メトロ千駄木駅から徒歩9分
逸話
狩野芳崖については、弟子の岡不崩(おかふほう)が著した『しのぶ草』をはじめ、多くの逸話が書き残されている。そのいくつかを紹介する。
狩野芳崖による絵師評
『しのぶ草』では、芳崖が他の絵師(葛飾北斎・河鍋暁斎・菊池容斎・柴田是真)に対してどう思っていたのかを示す言葉が残されている。
(狩野芳崖)先生は又、絵をかくには人格が高くなければいかぬ。人格が高ければ、自然描く絵も高尚になるものだ。よく気を付けねばならぬ。それから又、腕が達者過ぎるも宜しくない。器用過ぎるのも同じ事だ。所謂過ぎたるは猶及ざるが如しだ。北斎や暁斎は腕が余り達者過ぎて下品なものになったのだ。容斎だとか是真なども器用が過ぎたのである。むしろ不器用の方がよい。絵の尚いのは精神である。精神の入らぬものはいくら筆力があらうが手際が好からうが、真の美術として見る事が出来ないのだ。なまじっかなものより、小供の書いたものに採るべき点がまゝある。何んでも無我の界に入らなければいかぬのだ。と色々と教訓された。-『しのぶ草』より
異常なニンニク信仰
芳崖は生前、よくニンニクを食べていた。それは味の好みからではなく、毎日食べていれば病気にならないというニンニク信仰からだった。外出の際は着物の袖に常にニンニクを持ち歩いていた。そんな芳崖は当然ニオイがキツく、ある時フェノロサの妻に「先生、クサい!」と言われて、芳崖は「馬鹿!」と一喝したとか。
芳崖四天王と呼ばれた弟子(岡不崩、岡倉秋水、高屋肖哲、本多天城)のなかでも、一番おとなしい性格だった本多天城は特に芳崖から目をかけられていた。そんな天城が「脳が悪いか頭が病める」という話をすると、芳崖は「ニンニクをすりおろして、頭にすりつけるとよい」とアドバイス。天城がその通りにすると、はじめは少しヒリヒリ、しまいには大変に痛み出して手に負えなくなったという話がある。また、フェノロサが船酔いで弱っていた時もすりおろしたニンニク汁を飲ませたという。(『しのぶ草』より)
いきなり裸で能を舞い出す
能楽師の松本金太郎は狩野芳崖との初めての出会いについて次のように語っている。
麻布市兵衛町の私の家へ、初めての人が来て、是非逢ひたいとのことだつたので、何の用事か分らぬけれども、とにかく上つて貰つて逢つた。その人は木綿の紋附に、小倉の袴を穿いてゐる。何となしに、むさくるしい感じのする人であつた。
「わしは、狩野芳崖といふ絵かきだが、きのふ旧主人(毛利家)の邸で、お前さん方の乱舞を見た。それに就いて、舞の骨髄をお前に教へたいので遣つてきた」(中略)「もともと、わしは絵かきなのだから、何事も絵から割出すのだが、その第一番に、能では神様になる、その神様のことをいはう。たとへば高砂の神でもいいが、人間が面を附けて、神様のまねをするといふのでは駄目だよ。その時は神になつてくれなくては困る。では、神の形から教へよう」
そこで芳崖先生は、いきなり着物を脱ぎすてて、丸裸になつた。そしていろいろの形をして見せる。「神になるのに、頭が上つたり下つたりしてはならん。それには、踵(かかと)の浮かないやうにしなくてはならん」
さういひながら、先生は形で見せたり、口で説明したりする。謡も知らず、小舞も知らぬ人だのに、そのいふところは、私達が工夫に工夫を凝してゐるところの壷に嵌ってゐる。それには私も驚いた。どうしてかやうなことまでに気が附くのだらうか、と思はれることが、つぎつぎと語られる。私は初対面の先生に、心から推服した。―「狩野芳崖遺聞」より
まとめ
狩野芳崖の絵師人生や逸話を紐解くと、自分の納得する道をみつけたら、そこに真っすぐに突き進む一本気な性格が見えてくる。ニンニクの例のように時に暴走することもあるが、その推進力は伊藤博文を動かし、美術学校開校の礎となった。自らが教壇に立つことはなかったが、西洋画一辺倒に傾きかけた美術界にあって日本画の重要性を説き、職人的な徒弟制度から学校における教育制度へと変わっていく地ならしの役割を果たしたのではないだろうか。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
よろしければ応援クリックをお願いします!
![]()
にほんブログ村
参考資料
『しのぶ草』岡不崩
『東京美術家墓所誌』結城素明
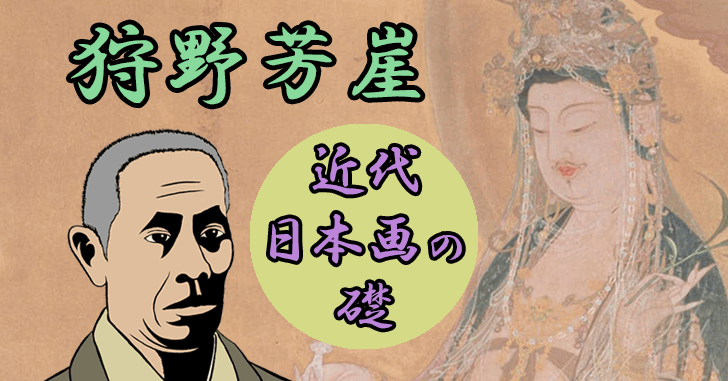






























コメントを残す