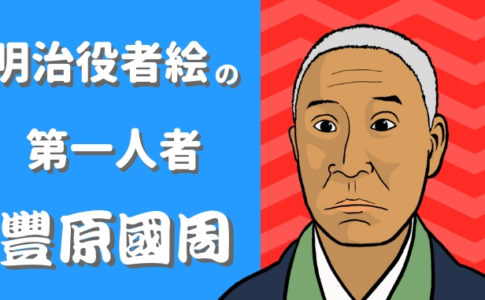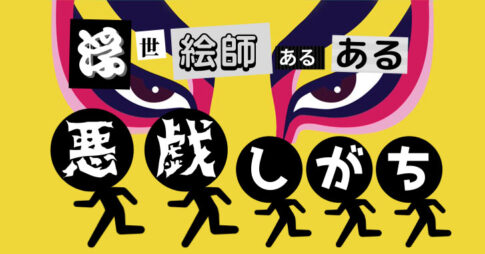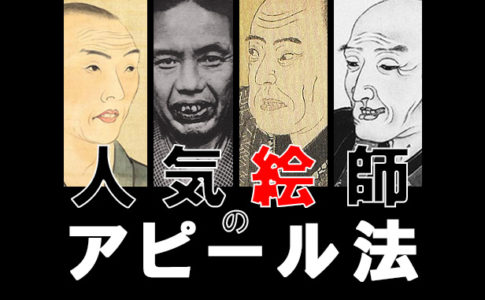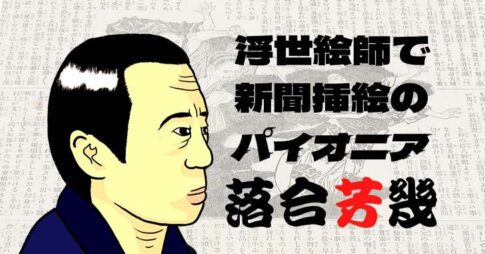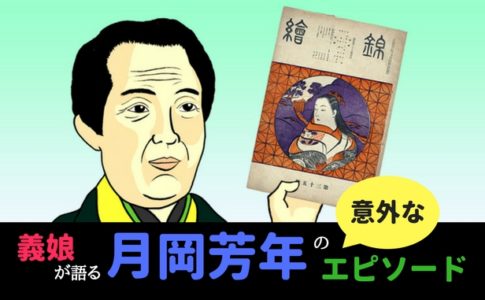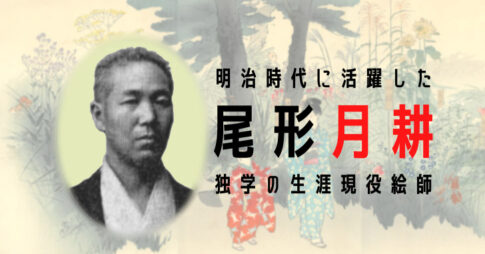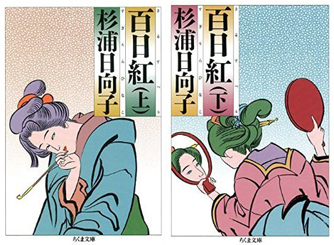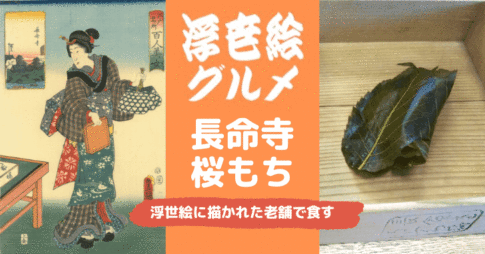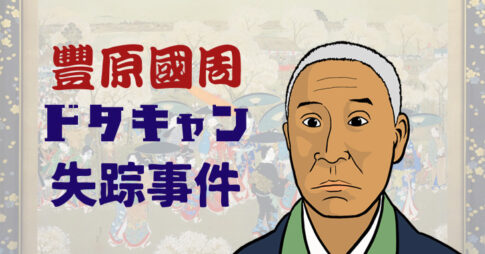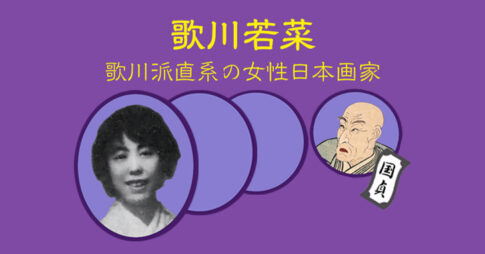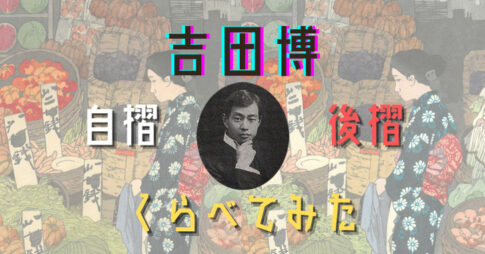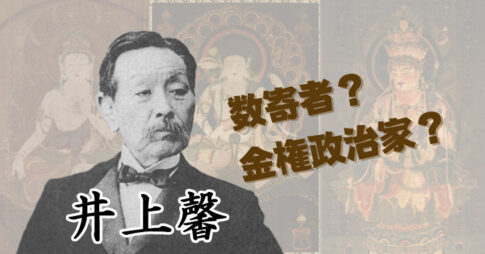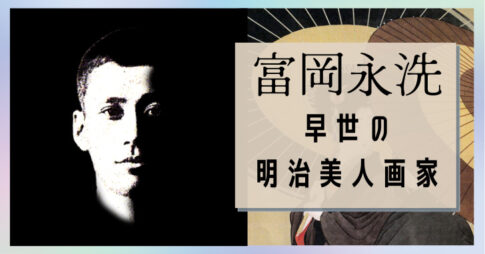大正6年(1917)創刊の浮世絵研究雑誌。大正浮世絵ブームにのって乱立した浮世絵雑誌のひとつ。付録に木版画をつけるためか、大判(ほぼB4版)なのが特徴。喜多川歌麿・歌川広重・歌川国芳の研究など収録。浮世絵と地続きの日本画特集もあり。
第1号(大正6年(1917)4月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:細田栄之画 扇屋瀧川 | – |
| 挿絵:一立斎広重画 高輪の月 | – |
| 挿絵:勝川春扇画 雪中の美人 | – |
| 挿絵:久保田米斎画 墨染 | – |
| 浮世絵の賛 | 高安月郊 |
| 春扇について | – |
| 欧米における豊国の鑑賞 | 野口米次郎 |
| 巻頭の挿絵(解説) | – |
| 錦絵と俳優名 | 石井研堂 |
| 春信の舞踏的特質 | 森口多里 |
| 大津絵の紋と鳥居の名 | 淡島寒月 |
| 新聞小説の挿絵 | 小川煙村 |
| 錦絵版画研究資料 | 皿彩 |
| 広重筆高輪の月(解説) | – |
| 浮絵の版画 | 皿彩 |
| 帝国劇場の二月興行 | 久保田世音 |
| 付録:錦絵版画落款集 | – |
第2号(大正6年(1917)5月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:歌川豊国画 関寺小町 | – |
| 挿絵:一立斎広重画 大はしの雨 | – |
| 挿絵:久保田米斎画 紋と模様 | – |
| 挿絵:小川千甕画 ベニスのゴンドラ | – |
| 浮世絵の賛 | 高安月郊 |
| 土佐の絵金 | 香雨楼主人 |
| 浮世絵の募集 | 野口米次郎 |
| 挿絵につきて(豊国の美人画、広重の風景画) | – |
| 芝居絵師としての国周 | 村上静人 |
| 錦絵ノートより | 皿彩 |
| 二代豊国となった豊重 | 石井研堂 |
| 私の幼かりし頃 | 淡島寒月 |
| 錦絵版画研究資料 | 皿彩 |
| 新大津絵ベニスのゴンドラについて | 小川千甕 |
| 編集を終りて | 相場朱雀 |
第3号(大正6年(1917)6月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:五渡亭国貞画 海の風 | – |
| 挿絵:勝川春章画 洲崎の帰帆 | – |
| 挿絵:磯田湖龍斎画 ほおづき | – |
| 奈良絵、錦絵源流 | 赤堀又次郎 |
| 海の風(巻頭の挿絵につきて) | – |
| 浮世絵版画の構図 | 藤懸静也 |
| 版画の時代的雅味 | 宮武外骨 |
| 浮世絵の募集(其の二) | 野口米次郎 |
| 洲崎の帰帆(巻中の挿絵につきて) | – |
| 広重と洋画 | 高安月郊 |
| 国芳の芸術 | 森口多里 |
| 俳優の遊画 生島新五郎の絵 | 好迂郎 |
| 諸名家の錦絵観 | 八名 |
| 錦絵版画研究資料 | 皿彩 |
| ほおづき(巻中の挿絵につきて) | 皿彩 |
| 編集を終りて | 相場朱雀 |
| 付録:錦絵版画落款集 | – |
第4号(大正6年(1917)7月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:二代目豊国画 政岡 | – |
| 挿絵:喜多川歌麿画 涼しき姿 | – |
| 当世顔 | 三田村鳶魚 |
| 豊国の政岡 | – |
| 浮世絵師と小説家 | 高安月郊 |
| 錦絵の価値 | 赤堀又次郎 |
| 歌麿筆『涼しき姿』(巻中の挿絵につきて) | – |
| 諸名家の錦絵観(二) | 六名 |
| 錦絵版画研究資料 | 皿彩 |
| 編集を終りて | 相場朱雀 |
| 付録:錦絵版画落款集 | – |
第5号(大正6年(1917)8月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:一立斎広重画 廊中東雲 | – |
| 挿絵:栄松斎長喜画 丁子屋内雛鶴 | – |
| 挿絵:一筆斎文調画 橋場の夜の雨 | – |
| 広重画、近江八景の色摺 | 石井研堂 |
| 京阪の錦絵 | 久保田世音 |
| 浮世絵師と小説家(二) | 高安月郊 |
| 挿絵につきて(広重、長喜、文調) | – |
| 歌川国貞論 | 村上静人 |
| 二つの展覧会 | – |
| 側面から見た浮世絵三名人(一世広重) | 樋口二葉 |
| 七月の日誌より | 木星 |
| 編集を終りて | 相場朱雀 |
| 付録:錦絵版画落款集(歌川国芳) | – |
第6号(大正6年(1917)9月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:鳥居清長画 江の島詣 | – |
| 挿絵:一立斎広重画 猿若町夜景 | – |
| 挿絵:一鵬斎芳藤画 ほうづき遊び | – |
| 鳥居派の栄えし時代 | 水谷不倒 |
| 『おもちゃ絵』について | 權田保之助 |
| 挿絵について(猿若町夜景) | – |
| ウイスキーと版画 | 野口米次郎 |
| 拝みの画、悟りの画、ながめの画 | 赤堀又次郎 |
| 時代の絵顔 | 森口多里 |
| 挿絵について(江の島詣、ほおづき遊び) | – |
| 広重追善展覧会、錦絵展覧即売会 | – |
| 一好斎芳兼 | 相見香雨 |
| 諸名家の錦絵観(三) | 七名 |
| 謹告、募集、紹介 | – |
| 八月のノート | 木星 |
| 編集を終りて | 相場朱雀 |
| 付録:錦絵版画落款集(国貞、国麿、広重、二代広重) |
第7号(大正6年(1917)10月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:渓斎英泉画 水茶屋の美女 | – |
| 挿絵:一勇斎国芳画 橋立の雷雨 | – |
| 挿絵:細田栄之画 遊女 | – |
| 浮世絵義考 | 朝倉無声 |
| 浮世絵について | 山中共古 |
| 十返舎一九忌法要 | – |
| 人形俳優浮世絵論 | 三田村鳶魚 |
| 役者絵の進化 | 高安月郊 |
| 英泉筆水茶屋の美女 | – |
| 錦絵と水野越前守 | 赤堀又次郎 |
| 国芳筆橋立の雷雨 | – |
| 広重追善展覧会(出陳目録) | – |
| 同展覧会雑感 | 相場朱雀 |
| 広重の音楽 | 野口米次郎 |
| 側面から見た浮世絵三名人(国芳) | 樋口二葉 |
| 歌麿の建碑追善・吉澤の常設陳列室 | – |
| 細田栄之筆遊女 | – |
| 錦絵応用の看板 | – |
| 八月から九月へかけて | 木星 |
| 編集を終りて | 相場朱雀 |
| 付録:錦絵版画落款集 | – |
第8号(大正6年(1917)11月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:喜多川歌麿画 七五三子宝合帯解きの図 | – |
| 挿絵:広重画 先帝御入京高輪通御の図 | – |
| 挿絵:月岡芳年画 同京橋通御の図 | – |
| 団十郎と似顔絵 | 井原青々園 |
| 初代広重立絵二枚継雪景山水 | 小島烏水 |
| 明治維新前後の錦絵 | 石井研堂 |
| 浮世絵と女の顔 | 佐々醒雪 |
| 七五三の祝(挿絵について) | – |
| 喜多川歌麿 | 野口米次郎 |
| 好と嫌の錦絵 | 池田輝方 |
| 先帝御入京(挿絵について) | – |
| 錦絵に残る江戸 | 高安月郊 |
| 奠都と錦絵 | 赤堀又次郎 |
| ノートの中より | 木星 |
| 付録:錦絵版画落款集 | – |
第9号(大正6年(1917)12月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:芳虎画 坂東三津五郎志うかの夕しで | – |
| 挿絵:広重画 江戸百景 観音の雪 | – |
| 挿絵:長喜画 風俗挿花会 | – |
| 錦絵美人 | 笹川臨風 |
| 浮世絵から錦絵へ | 坂本蠡舟 |
| 錦絵と能画の将来 | 坂元雪鳥 |
| 喜多川歌麿(其の二) | 野口米次郎 |
| 鈴木春信と司馬江漢 | 高安月郊 |
| 珍しき石燕の額 | 兼子伴雨 |
| 錦絵の新生命 | 赤堀又次郎 |
| 挿絵について | – |
| 歌麿建碑と遺作展覧会 | 編集局 |
| 錦絵界 | – |
| 十号(正月号)予告 | – |
| 付録:錦絵版画落款集 | – |
第10号(大正7年(1918)1月1日)
| タイトル | 著者 |
| 窪俊満画 祇園一力之図 | – |
| 広重画 江戸百景 十万坪 | – |
| 北斎画 汐くみの図 | – |
| 板画の趣味 | 藤懸静也 |
| 浮世絵より錦絵へ(二) | 坂本蠡舟 |
| 錦絵と演劇の表裏 | 石井研堂 |
| 歌川国芳論 | 村上静人 |
| 北斎の花鳥画と人為 | 池上秀畝 |
| 筆はじめ | 鶯亭主人 |
| 口絵について | – |
| 新年大付録について | – |
| 一新せんとする十一号につき | – |
| 錦絵界 | – |
| 付録:大でけ双六 | – |
第11号(大正7年(1918)2月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:磯川亭永理画 美人潮汲み | – |
| 挿絵:広重画 江戸百景 佃島 | – |
| 挿絵:北斎画 春の美人 | – |
| 挿絵:豊国画 役者画(一) | – |
| 挿絵:豊国画 役者画(二) | – |
| 初代と二代と三代との豊国に連関する種々の疑問について(一) | 坪内逍遥 |
| 浮世絵より錦絵へ(三) | 坂本蠡舟 |
| 歌川国芳論(二) | 村上静人 |
| 挿画につきて | – |
| 懐月堂の流罪 | 兼子伴雨 |
| 付録:錦絵版画落款集 | – |
第12号(大正7年(1918)3月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:田村貞信画 漆絵の内裏雛 | – |
| 挿絵:歌川国芳画 宮戸川の図 | – |
| 挿絵:豊国画 役者画(三) | – |
| 初代と二代と三代との豊国に連関する種々の疑問について(二) | 坪内逍遥 |
| 雛祭と錦絵 | 久保田米斎 |
| 墨本に見えたる絵師の名 | 水谷不倒 |
| 歌川国芳論(三) | 村上静人 |
| 浮世絵より錦絵へ(四) | 坂本蠡舟 |
| 挿画につきて | 編集局 |
| 貴答芳名と方針発表について | 編集局 |
| 鳥居派の系図 | 石井古城 |
| 付録:錦絵版画落款集 | – |
第13号(大正7年(1918)4月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:勝川春潮画 浅草境内三美女 | – |
| 挿絵:一立斎広重画 玉川堤の花 | – |
| 挿絵:二代目豊国画 千本桜の役者絵 | – |
| 初代と二代と三代との豊国に連関する種々の疑問について(三) | 坪内逍遥 |
| 歌川国芳論(四) | 村上静人 |
| 浮世絵より錦絵へ(四) | 坂本蠡舟 |
| 挿画につきて | 編集局 |
| 宋明時代の花鳥画と春の流行 | 編集局 |
| 付録:錦絵版画落款集 | – |
第14号(大正7年(1918)5月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:喜多川歌麿画 遊女 | – |
| 挿絵:二代目広重画 赤坂桐畑 | – |
| 挿絵:玉川舟調画 お七、吉三 | – |
| 初代と二代と三代との豊国に連関する種々の疑問について(四) | 坪内逍遥 |
| 刷師と江戸っ子気質 | 松井栄吉 |
| 国芳の戯画 | 石井柏亭 |
| 鳥居派の系図につきて | 渡邊庄三郎 |
| 芝居と浮世絵 | 井原青々園 |
| 耳鳥斎の背景(上) | 三田村鳶魚 |
| 挿絵について | 皿彩 |
| 浮世絵雅談 | 石井研堂 |
| 付録:錦絵版画落款集 | – |
第15号(大正7年(1918)6月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:奥村政信画 袖崎三輪野の化粧坂少将 | – |
| 挿絵:北尾政演画 当世美人色競 | – |
| 挿絵:一立斎広重画 駒形堂 | – |
| 初代と二代と三代との豊国に連関する種々の疑問について(五) | 坪内逍遥 |
| 耳鳥斎の背景(下) | 三田村鳶魚 |
| 浮世絵と現代画 | 高安月郊 |
| 挿絵につきて | 皿彩 |
| 錦絵の「改め印」考証と発行年代の推定法 | 石井研堂 |
| 絵も非凡人も非凡の暁斎の逸事 | 児玉蘭陵 |
| 付録:錦絵版画落款集 | – |
第16号(大正7年(1918)7月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:芝居絵 | – |
| 挿絵:住吉御田植 | – |
| 挿絵:鎧の渡し | – |
| 挿絵:役者似顔画(其の一) | – |
| 挿絵:役者似顔画(其の二) | – |
| 初代と二代と三代との豊国に連関する種々の疑問について(六) | 坪内逍遥 |
| 浮世絵画師の書画会 | 久保田米斎 |
| 浮世絵と自然の情趣 | 鏑木清方 |
| 錦絵の「改め印」考証と発行年代の推定法(二) | 石井研堂 |
| 挿絵につきて | 皿彩 |
| 浮世絵談叢 | 石井研堂、浮世仙人 |
第17号(大正7年(1918)8月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:筆者不詳 坊主小兵衛 | – |
| 挿絵:鳥居清長画 芝居絵 | – |
| 挿絵:勝春山画 吉原俄廊全盛 | – |
| 挿絵:五雲亭貞秀画 長府の沖 | – |
| 初代と二代と三代との豊国に連関する種々の疑問について(七) | 坪内逍遥 |
| 子興の在世年代 | 久保田米斎 |
| 北斎と馬琴 | 兼子伴雨 |
| 錦絵の「改め印」考証と発行年代の推定法(三) | 石井研堂 |
| 水茶屋の女 | 広瀬菊雄 |
| 挿絵について | 皿彩 |
第18号(大正7年(1918)9月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:喜多川歌麿画 婦人手業十二工 | – |
| 挿絵:二代豊国画 熱海夕照 | – |
| 挿絵:初代広重画 木曽街道の望月 | – |
| 挿絵:初代豊国画 晩年の筆 | – |
| 初代と二代と三代との豊国に連関する種々の疑問について(八) | 坪内逍遥 |
| 子興の年代 | 水谷不倒 |
| 錦絵の「改め印」考証と発行年代の推定法(四) | 石井研堂 |
| 挿絵につきて | 皿彩 |
| 月岡芳年 | 野口米次郎 |
第19号(大正7年(1918)10月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:鳥居清長画 柏筵の外郎売 | – |
| 挿絵:一筆斎文調画 上総家の総角 | – |
| 挿絵:一勇斎国芳画 橋場の夜の雨 | – |
| 挿絵:初代豊国画 団扇絵 | – |
| 挿絵:四名家画 傑作名画集 | – |
| 初代と二代と三代との豊国に連関する種々の疑問について(九) | 坪内逍遥 |
| 式亭三馬旧蔵の紋番付序文 | 石井研堂 |
| 水茶屋 | 三田村鳶魚 |
| 錦絵の「改め印」考証と発行年代の推定法(四) | 石井研堂 |
| 五雲亭貞秀の密画 | 筑山浪人 |
| 挿絵について | 皿彩 |
| 清長の役者絵について | 町田博三 |
第20号(大正7年(1918)11月10日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:上村松園画 焔 | – |
| 挿絵:池田輝方画 浅草寺 | – |
| 挿絵:鈴木春信画 楊枝屋お藤 | – |
| 挿絵:菊池契月画 夕至 | – |
| 挿絵:鏑木清方画 ためさるる日 | – |
| 挿絵:和気春光画 消えゆく鐘の音 | – |
| 挿絵:伊藤小玻画 ふたば | – |
| 挿絵:島成園画 日ざかり | – |
| 挿絵:吉岡千種画 をんごく | – |
| 挿絵:太田秋民画 まうで | – |
| 挿絵:池田龍甫画 桐花薫る桃山の栄 | – |
| 挿絵:三木翠山画 祇園会 | – |
| 挿絵:西山翠嶂画 落梅 | – |
| 挿絵:松本姿水画 ほととぎす | – |
| 挿絵:栗原玉葉画 朝妻桜 | – |
| 挿絵:三宅皆山画 もの日のつどひ | – |
| 挿絵:松島白虹画 ジャガタラ文 | – |
| 挿絵:谷角雪斎画 知恵頂ける児 | – |
| 挿絵:川北霞峯画 風景三題 | – |
| 挿絵:植戸観海画 鏡の池 | – |
| 挿絵:織田観湖画 島の朝 | – |
| 「焔」と「ためさるる日」 | 笹川臨風 |
| 時代錯誤と画題 | 久保田世音 |
| 板画と肉筆画 | 藤懸静也 |
| 「焔」の作意 | 上村松園 |
| 「浅草寺」の作意 | 池田輝方 |
| 「ためさるる日」 | 鏑木清方 |
| 文展雑俎 | 編集局 |
| 第十二回文展日本画目録 | 編集局 |
| 初代と二代と三代との豊国に連関する種々の疑問について(十) | 坪内逍遥 |
| 国周の一面と孝女お幸 | 秋花 |
| 大坂における役者絵 | 井原青々園 |
| 錦絵の「改め印」考証と発行年代の推定法(五) | 石井研堂 |
| 挿絵につきて | 皿彩 |
| 二十一号予告 | 編集局 |
第21号(大正7年(1918)12月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:喜多川歌麿画 化粧 | – |
| 挿絵:二代豊国画 大山の図 | – |
| 浮世絵に現れたる歌舞伎劇場の内外(一) | 坪内逍遥 |
| 江戸時代の流行と人気役者(上) | 齋藤隆三 |
| 五雲亭貞秀(上) | 大塚瞿圃 |
| 建設期の浮世絵(一) | 藤懸静也 |
| 近世錦絵製作法(一) | 石井研堂 |
| 細田栄之 | 三田村鳶魚 |
| 挿絵について | 皿彩 |
第22号(大正8年(1919)1月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:石川秀葩画 石川太夫 | – |
| 挿絵:鳥居清倍画 人形つかひ | – |
| 挿絵:広重画 蘆に鴨 | – |
| 舞台絵(其の一) | – |
| 舞台絵(其の二) | – |
| 浮世絵に現れたる歌舞伎劇場の内外(二) | 坪内逍遥 |
| 大蘇芳年 | 饗庭篁村 |
| 近世錦絵製作法(二) | 石井研堂 |
| 貞享頃の大阪役者 | 中井浩水 |
| 江戸時代の流行と人気役者(中) | 齋藤隆三 |
| 紙鳶画について | 巌谷小波 |
| 挿絵につきて | 麦仙史 |
| 勅題「朝晴雪」に因める錦絵について | 茂枝隆俊 |
第23号(大正8年(1919)2月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:鳥居清長画 芝居絵 | – |
| 挿絵:細田栄之画 盃合 | – |
| 挿絵:舞台絵(其の一) | – |
| 挿絵:舞台絵(其の二) | – |
| 浮世絵に現れたる歌舞伎劇場の内外(三) | 坪内逍遥 |
| 五雲亭貞秀(下) | 大塚瞿圃 |
| 建設期の浮世絵(二) | 藤懸静也 |
| 江戸時代の流行と人気役者(下) | 齋藤隆三 |
| 挿絵につきて | 皿彩 |
| 北斎筆の悪魔降服 | 児玉蘭陵 |
第24号(大正8年(1919)3月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:奥村政信画 雛祭 | – |
| 挿絵:晩器画 權八、小紫 | – |
| 挿絵:昇亭北壽画 高輪海岸 | – |
| 挿絵:舞台絵 | – |
| 浮世絵に現れたる歌舞伎劇場の内外(四) | 坪内逍遥 |
| 近世錦絵製作法(三) | 石井研堂 |
| 挿絵につきて | 皿彩 |
| 到着した「大首」の首筋(上) | 三田村鳶魚 |
| 浮世絵師寸談 | 麦斎 |
| 側面から観たる亀戸豊国(上) | 樋口二葉 |
第25号(大正8年(1919)4月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:初代豊国画 初鰹三枚続 | – |
| 浮世絵に現れたる歌舞伎劇場の内外(五) | 坪内逍遥 |
| 挿絵につきて | 皿彩 |
| 京阪における浮世絵師 | 久保田米斎 |
| 近世錦絵製作法(四) | 石井研堂 |
| 観花 | 坂本蠡舟 |
| 毛色の変わった地本問屋 | 麦斎 |
| 側面から観たる亀戸豊国(下) | 樋口二葉 |
| 帝国博物館と錦絵 | 根本 |
第26号(大正8年(1919)5月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:勝川春英画 役者絵 | – |
| 挿絵:菊川英山画 風流五節花鳥合 | – |
| 挿絵:五岳画 安治川 | – |
| 挿絵:舞台絵(其の一) | – |
| 挿絵:舞台絵(其の二) | – |
| 浮世絵に現れたる歌舞伎劇場の内外(六) | 坪内逍遥 |
| 明治初年の浮世絵 | 饗庭篁村 |
| 建設期の浮世絵(三) | 藤懸静也 |
| 近世錦絵製作法(五) | 石井研堂 |
| 到着した「大首」の首筋(下) | 三田村鳶魚 |
| 鈴木春信記念碑建設につきて | 池田輝方、坪内逍遥、鏑木清方、永井荷風、笹川臨風他 |
| 挿絵につきて | 皿彩 |
| 浮世絵寸談 | 麦斎 |
| 米国と浮世絵の影響 | 小島烏水 |
第27号(大正8年(1919)6月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:東洲斎写楽画 役者絵 | – |
| 挿絵:舞台絵及地図(其の一) | – |
| 挿絵:舞台絵及地図(其の二) | – |
| 浮世絵に現れたる歌舞伎劇場の内外(七) | 坪内逍遥 |
| 広重の芸術 | 中井宗太郎 |
| 浮世絵漫筆 | 高安月郊 |
| 近世錦絵製作法(六) | 石井研堂 |
| 判じ物風の雅印 | 麦斎 |
| 明治の版画家小林清親 | 落合直成 |
| 吉田半兵衛 | 三田村鳶魚 |
| 春信会 春信建碑除幕式と展覧会につき | 編集局 |
| 挿絵につきて | 美山 |
第28号(大正8年(1919)7月21日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:鼓打ちの若衆 | – |
| 挿絵:鈴木春信画 おせん | – |
| 挿絵:鈴木春信画 初恋 | – |
| 挿絵:鈴木春信画 各種 | – |
| 挿絵:舞台絵 | – |
| 春信百五十回忌辰記念展覧会を見て | 笹川臨風 |
| 春信の製作期 | 橋口五葉 |
| 春信と疑問 | 落合直成 |
| 鈴木春信の肉筆 | 藤懸静也 |
| 春信に対する望み | 鏑木清方 |
| 鈴木春信 | 漆山天童 |
| 春信の絵と明和風俗 | 齋藤隆三 |
| 春信会 | – |
| 春信展覧会出品目録 | – |
| 浮世絵に現れたる歌舞伎劇場の内外(八) | 坪内逍遥 |
| 崋山筆の似顔画 | 児玉蘭陵 |
第29号(大正8年(1919)8月14日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:喜多川歌麿画 浮世七ツ目合 | – |
| 挿絵:一立斎広重画 高輪の月 | – |
| 挿絵:舞台絵及芝居町地図 | – |
| 浮世絵に現れたる歌舞伎劇場の内外(九) | 坪内逍遥 |
| 鍬形蕙斎 | 大河落葉 |
| 近世錦絵製作法(七) | 石井研堂 |
| 浮世絵門外漢 | – |
| 初期の浮世絵における群衆描写の作例(上) | 藤懸静也 |
| 江戸絵鑑賞会録 | 石井研堂 |
| 浮世絵草紙 | 麦斎、清風 |
| 前号挿絵について | – |
第30号(大正8年(1919)9月16日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:喜多川歌麿画 画世踊子揃 | – |
| 挿絵:勝川春好画 美女 | – |
| 挿絵:安藤広重画 両国の夜月 | – |
| 二世豊国問題の再調査 | 坪内逍遥 |
| お竹大日如来の前掛 | 子浚 |
| 難波屋おきた | 夜潮閣主人 |
| 挿絵につきて | – |
| 仮名草紙の挿絵と雛屋立圃 | 水谷不倒 |
| 春信の建碑について | 笹川臨風 |
| 初期の浮世絵における群衆描写の作例(下) | 藤懸静也 |
| 同号または類号の浮世絵師 | 村上静人 |
| 江戸絵鑑賞会録 | 石井研堂 |
第31号(大正8年(1919)11月10日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:鳥居清満画 市川八百蔵の義経 | – |
| 挿絵:鳥居清信画 美人揮毫 | – |
| 挿絵:勝川春章画 坂東三津五郎の曾我十郎 | – |
| 挿絵:西鶴自画讃 | – |
| 挿絵:舞台絵 | – |
| 挿絵:能舞台橋懸りの進化 | – |
| 挿絵:歌舞伎舞台の進化 | – |
| 浮世絵に現れたる歌舞伎劇場の内外(十) | 坪内逍遥 |
| 豊国問題の再調査の補遺 | 坪内逍遥 |
| 地方出来の錦絵 | 久保田世音 |
| 闇暗ばなし | 烏有 |
| 西鶴本の挿絵について(一) | 水谷不倒 |
| 増補めづらしき落款 | 子浚 |
| 浮世絵類考特に其著者笹屋邦教について(上) | 星野朝陽 |
| 錦絵の印刷(一) | 石井研堂 |
| 曙会展覧会 | 石井直三郎 |
第32号(大正8年(1919)12月9日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:鳥居清経画 役者絵 | – |
| 挿絵:磯田湖龍斎画 美人画 | – |
| 挿絵:葛飾北斎画 亀井門 | – |
| 挿絵:一立斎広重画 阿波の鳴戸 | – |
| 挿絵:井原西鶴画 数種 | – |
| 挿絵:舞台絵 | – |
| 浮世絵に現れたる歌舞伎劇場の内外(十一) | 坪内逍遥 |
| 天保七年の飢饉と浮世絵師 | – |
| 浮世絵類考特に其著者笹屋邦教について(中) | 星野朝陽 |
| 同号または類号の浮世絵師 | 村上静人 |
| 西鶴本の挿絵について(二) | 水谷不倒 |
| 美人風俗画の全滅は当然 | 鏑木清方 |
| 帝国風俗画 | 齋藤隆三 |
| 第一回帝展出品目録 | – |
第33号(大正9年(1920)1月9日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:窪俊満、加藤隣松画 万歳 | – |
| 挿絵:樹下石上画 二美人 | – |
| 挿絵:歌川国芳画 浅草今戸 | – |
| 挿絵:舞台絵 | – |
| 浮世絵に現れたる歌舞伎劇場の内外(十二) | 坪内逍遥 |
| 一世広重初期の版画について | 朝倉無声 |
| 一立斎広重 | エドワード・F・ストレンヂ |
| 宮崎友禅と友禅染 | 次郎坊主人 |
| 江戸の正月 | 齋藤隆三 |
| 浮世絵類考特に其著者笹屋邦教について(下) | 星野朝陽 |
| 烏羽絵と浮世絵師 | – |
| 窪俊満の百年忌 | カグラドウ |
| 豊原国周 | 樋口二葉 |
第34号(大正9年(1920)3月13日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:五渡亭国貞画 二見浦 | – |
| 挿絵:勝川春好画 役者絵 | – |
| 挿絵:喜多川歌麿画 曾我五郎と化粧坂の少将 | – |
| 挿絵:舞台絵 | – |
| 挿絵:吉田半兵衛画 数種 | – |
| 浮世絵に現れたる歌舞伎劇場の内外(十三) | 坪内逍遥 |
| 西鶴本の挿絵について(三) | 水谷不倒 |
| 春信図録の初に | 笹川臨風 |
| 一勇斎国芳の別号は柳燕なり | 石井研堂 |
| 歌麿と国貞、巨大なる古板本 | 久保田世音 |
| 五雲亭貞秀 | 樋口二葉 |
| 松本芳延 | – |
| 三十三、四号の挿絵 | – |
第35号(大正9年(1920)6月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:勝川春潮画 美人集会 | – |
| 挿絵:勝川春潮画 三美人 | – |
| 挿絵:舞台絵 | – |
| 浮世絵に現れたる歌舞伎劇場の内外(十四) | 坪内逍遥 |
| 錦絵の印刷(二) | 石井研堂 |
| 月岡芳年先生 | 山中古洞 |
| 五渡亭の額 | 筑波 |
| 亡父芳年の思ひ出 | 小林きん |
| 狂言と錦絵 | 仲小路靄軒 |
| 国貞時代と豊国時代 | 村上静人 |
| 年方十三回忌及建碑展観 | – |
第36号(大正10年(1921)2月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:勝川春潮画 美人集会 | – |
| 挿絵:一立斎広重画 岡部 | – |
| 挿絵:宮川長春画 肉筆美人 | – |
| 挿絵:尾形月耕画 花見 | – |
| 勝川春潮の版画 | 橋口五葉 |
| 芳年の画風変遷 | 石井研堂 |
| 歌川派盛時の鼎足戦(上) | 山中古洞 |
| 漫画家としての北斎と暁斎(上) | 竹内梅松 |
| 北斎と油画 | 兼子伴雨 |
| 国芳の制作 | 宇世喜 |
| 月耕小伝(上) | 尾形月山 |
| 父を通して見た国芳先生 | 新井芳宗 |
| 仏蘭西における版画 | 芳江孤雁 |
第37号(大正10年(1921)12月5日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:歌麿画 にくまれ頃 | – |
| 挿絵:北壽画 お茶の水 | – |
| 挿絵:石井柏亭画 京の踊妓 | – |
| 挿絵:小杉未醒画 琉球の女風俗 | – |
| 挿絵:近藤浩一路画 獅子舞 | – |
| 挿絵:伊藤深水画 長襦袢 | – |
| 挿絵:長原止水画 子守 | – |
| 挿絵:鏑木清方画 初冬 | – |
| 挿絵:石井鶴三画 木曽の子供 | – |
| 挿絵:大林千萬樹画 所作事 | – |
| 挿絵:蔦谷龍岬画 淀君 | – |
| 挿絵:小川千甕画 漁村の女 | – |
| 挿絵:池上秀畝画 支那の貴婦人 | – |
| 挿絵:山内多門画 朝鮮の風俗 | – |
| 挿絵:鴨下晃湖画 モデル女 | – |
| 挿絵:栗原玉葉画 雛菊 | – |
| 挿絵:小堀鞆音画 名古屋帯 | – |
| 挿絵:野田九浦画 澤住検校 | – |
| 挿絵:山田敬中画 渡場 | – |
| 挿絵:大野麦風画 麦笛 | – |
| 挿絵:松村巽画 髪すき | – |
| 挿絵:福井義朋画 とんぼ | – |
| 錦絵の印刷(三) | 石井研堂 |
| 歌川派盛時の鼎足戦(下) | 山中古洞 |
| 浮世絵書論 | 故正岡子規 |
| センセイ室の清親翁 | 山本柳葉 |
| 北斎の神的霊腕 | 石井研堂 |
| 漫画家としての北斎と暁斎(下) | 竹内梅松 |
| 板画の今昔 | ファッケー |
| 噫池田輝方君 | 大野静方 |
| 故橋口五葉氏 | 岩波茂雄 |
| 亡父尾形月耕(下) | 尾形月山 |
| 父芳斎豊国 | 竹内こう |
| 第一回風俗画展覧会 | 編集者 |
第38号(大正12年(1923)1月1日)
| タイトル | 著者 |
| 挿絵:勝川春章画 羽子板 | – |
| 挿絵:一立斎広重画 東海道程ヶ谷 | – |
| 挿絵:小説挿絵 | – |
| 小説の挿絵と浮世絵師 | 水谷不倒 |
| 初春の気分 | 笹川臨風 |
| 保永堂主人の画 | 石井研堂 |
| 古版画の中から | 山村耕花 |
| 歌麿瑣事 | 山中古洞 |
| 肉体義を露はした錦絵類 | – |
| 帝展一巡 | 大夢童 |
| 女性美の陶酔 | 竹内梅松 |
| 院展における風俗画 | 林石 |